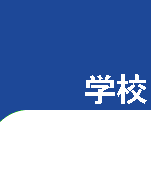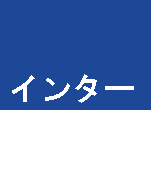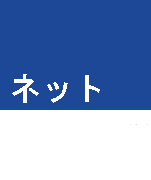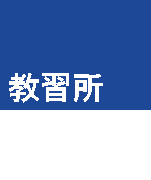小学校における情報モラル育成教材の開発
−学校インターネット教習所の取り組みから−
埼玉県熊谷市立籠原小学校 教諭 関根達郎(熊谷教育工学研究会) |
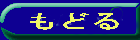 |
5 授業実践の考察
(1)授業を実践して
児童にとって「免許証」が取得できるという動機付けは効果的であった。例えば平素得意ではない図書室での書籍探しに懸命に取り組んだり、確認テストに合格するまで熱心に取り組んだりする様子がみられた。3年生後半で学習した本教材の内容が、4年生のインターネットによる調べ学習の中でも生かされており、即断はできないが効果が表れ始めている。
課題として考えなければならないのは、情報活用能力の基本であるプリントメディアの活用能力の育成である。必要な資料を的確に探し出し活用する、そこでの知力やセンスがインターネット利用に生きるのである。情報モラルについても同様である。まさにオフラインの知識や技能あるいは倫理がオンラインに通じるのである。オフラインでの積み重ねが大切となってくる。つまり、情報モラルの育成には、オフラインを含めた調べ学習全体の明確な指導方法の確立が重要となってくる。児童に調べ学習の導入段階で「自由に調べてごらん」といった投げかけをし、情報を集めさせる中で帰納的に指導する従来の方法にとどまらず、調べ学習の導入段階から効果的な教材を利用し演繹的に指導する方法の導入も考えなくてはならない。そのためには、より汎用的で確実にメディアの活用能力を育成できる演繹的な教材が必要である。
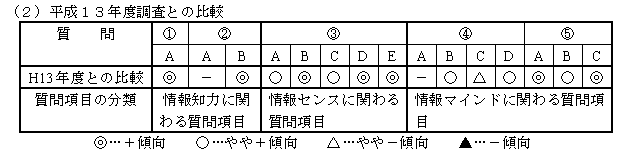
平成13年度調査時には、情報モラル教育の意識は薄く、ほとんど実践されていない状況にあった。また、インターネットの利用についても、4割以上の児童は「使用経験がない」という状況であった。これらを考慮すると、今回の調査結果は、「インターネット教習所」の実践とインターネットの教育的利用の拡大という2つの側面からとらえられる。後者の影響を考えても、前者の結果が、今回の調査結果に大きな影響をもたらしたことは、疑い得ない。ほとんどの質問項目において、+傾向を示した意義は大きい。特に、情報センスに関わる項目が顕著であり、情報を使いこなす感性の素養が「インターネット教習所」により、身につきつつあることがうかがえる。そのような中で、質問項目4は、あまり優位性が認められない結果となった。この質問項目は「資料で調べたことをまとめる時、どのようにしていた」問うたものである。これは、インターネット特有のものでなく、調べ学習のルールにも大きく関わってくる。今回の「インターネット教習所」は、その名の通り「インターネット」に重点をおいたものであった。この結果から、情報モラル育成のためには、もっと広範囲をカバーする教材も必要であるという課題が浮かび上がる(調査結果の詳細は、別紙資料参照)。
(3)汎用教材としてのインターネット教習所に関する教師の評価
また、実際に指導にあたった教師は「インターネット教習所」について、どのような評価をしたであろうか。実践された方に記述式で回答していただいた。以下は、その結果である。
「インターネット教習所」実践後の教師の評価
| 質問項目 |
回 答 |
| 1 教材としてどうか |
・わかりやすく指導することができ、とてもよい。
・インターネットの使い方の導入としては、とてもよい。
・自分のためにも、勉強になった。 |
| 2 児童に情報モラル は身についているか |
・身についていると思う。
・身についた。 |
| 3 課題や問題点はなにか |
・実技プリントにある図書やホームページが現存しているか、 活用されやすいか、毎年チェックする必要がある。
・教師サイドに、情報についてのたくさんの知識と技能がない と指導が中途半端になってしまう可能性がある。
・きちんと研修してから指導する必要がある。
・内容を教えるだけで精一杯であった。 |
この結果を考察すると、教材としての「インターネット教習所」の評価は高く、その効果としての情報モラルの定着に関しても「進んでいる」という認識を指導にあたった教師は感じているようである。課題や問題点も、何点かあげられている。特に、指導前に教師自身の情報モラルを高めておく必要性を指導の有効性からあげている点は重要である。これは、当然のことではあるが、新しい試み(情報モラル教育)をより多くの学校に定着させるためには、大きな障害と成りかねない問題点である。「インターネット教習所」以上に、誰もが、いつでも、簡単に指導できる教材、さらに言うなら、教師と児童がともに学べるような教材が、情報モラル教育の浸透には必要といえる。
|
|
|