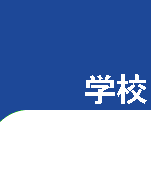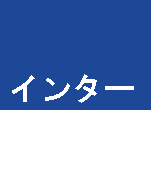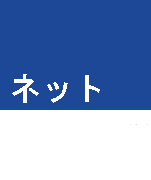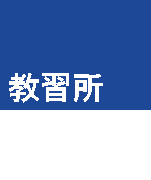| 情報モラル教育の指導カリキュラム |
|
著作情報との関わり |
コミュニケーション |
コンピュータ・データの保守 |
レベル
(場面) |
著作権 |
引 用
(他人の著作権) |
プライバシー
(自分の生活を守る) |
匿名によるいたずら
(他人のプライバシー) |
情報や情報機器、
情報社会への関わり方 |
セキュリティー
(コンピュータやデータを守る) |
教室内での学習・生活
|
●自分の作品
に名前をつける。
・自分の作品にはきちんと名前をつけて、大切にすること。 |
●キャラクターを使った作品を作らない。
・自分の創造したものとして発表するとき安易に商標は使わない。 |
|
●ともだちに匿名でいたずらの手紙をださない。
・相手への主張は人前か他人に相談する。 |
●テレビ視聴・テレビゲーム等をやりすぎない
・テレビやコンピュータに夢中になって、人との関わりをたつことがないようにする。 |
|
| インタビューや話を聞く学習(電話も含む) |
●聞いたことは正しく伝える。●内容を他人に伝えることの承諾を得る。 |
●利用目的を告げる。・学習内容をつげてから聞くこと。●相手の名前を聞いておく。 |
●初めての相手には自分の名前を告げない・学校名、学年で対応する
●知らない人に聞かれても自分や友だちの家の電話番号等は教えない・学校等の電話番号で対応する。 |
●うわさ話を伝えない。・誰が言ったかわからない情報は他に人に伝えない。 |
●複数の人の話を聞いてよく考える。・情報源によって話が変わるので一人ですべてを判断しない。 |
|
| 本や資料・CDーROM使って調べ学習 |
●調べたことに自分の感想や考えたことをつけて、自分の情報として発表すること。 |
●出典の明示・本の名前・出版社・著者名等を作品に明示すること。
●本に載ってる内容を改変しない
・必要最小限を利用し内容を変えない
●CDROM等のプログラムを勝手にコピーしない |
|
|
●複数の本、複数の情報を会わせて判断する。・情報源によって内容が変わるので一つですべてを判断しない。 |
●出所のはっきりしないフロッピー等はコンピュータに入れない・フロッピーからの情報●自分のデータのバックアップをとっておく
・自分で作ったデジタル情報を守る |
| ネットワーク(webページを含む)で情報収集する学習 |
●引用コピーしたことを明示して、自分の感想や考えたことをつけて、自分の情報として発表すること。 |
●個人として引用するときには、サイト名、URLを明示する。 |
●ネット懸賞等に応募しない。・自分の氏名年齢住所電話等の情報を簡単に入力しない。●ネット販売でものを購入しない。・トラブルに巻き込まれない。・自分の責任がとれないものの売り買いはしない。 |
●なりすましてネット懸賞やネット販売に関わらない。●チェーンメールを送らない |
●複数のサイトや他のメディアの情報を会わせて判断する。・情報源によって内容が変わるので一つですべてを判断しない。 |
●プログラムのダウンロードはしない。・ウイルス侵入や海外への接続がないようにする。 |
|
| Eメール・掲示板チャット等で交流(テレビ会議を含む) |
●メールで知った内容に自分の感想や考えたことをつけて、自分の情報として発表すること。 |
● 引用するときには、相手にメール等で承諾を得てサイト名、URLを明示して発信する。 |
●初めての相手に氏名を公表しない・知っている相手でも教師の判断で公表する。●自宅の住所・電話番号等は相手に伝えない。・学校のパソコンからは絶対に伝えない |
●掲示板、チャットで中傷の言葉を書き込まない |
●メール・チャット等に夢中になりすぎない。●実社会と情報社会のバランスをとった生活をする。・パソコン・携帯電話を購入してからの生活の仕方を振り返りながら、 |
●大量のデータを添付したメールは送らない。・高画質写真・写真を添付したワープロ文書など300KBを越えるもの●相手のプログラムのことを考えて情報を送る・相手のプログラムを確認する、あるいはテキスト・JPeg等にする。●他のコンピュータに侵入しデータやプログラムを改ざんない
(不正アクセス) |
| webページ等に情報発信する学習 |
●自分の作品の著作権の所在を明確にする・学校の帰属する事を承諾するか、親の承諾書等をとって氏名を公表するか選択する。 |
●二次発信するときは相手にメール等で承諾を得て、サイト名、URLを明示して発信する。 |
●自分が特定できる写真を載せない●自宅の写真、住所・電話番号等はwebページにのせない。 |
●人の写真を載せるときは相手の承諾をとる (肖像権を含む) |
●webページを公開したら、情報を定期的に更新する。 |
●大量のデータを載せない。・高画質写真などをのせてサーバーに負荷をかけない。 |
| 学校卒業時に身につけたいこと |
●自分の著作権を主張する。
●相手の著作権を尊重する |
●引用のルールがわかる。
●webページの二次発信のルールがわかる。 |
●個人情報を安易に流さない。 |
●相手のプライバシーを侵害しない。 |
●実社会と情報社会のバランスをとった生活をする。 |
●相手を考えたメール等ができる。 |