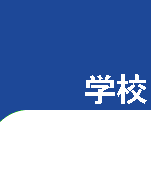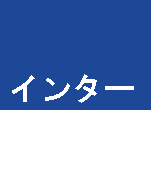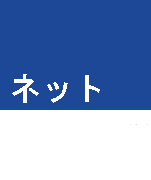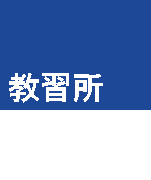| 学習内容 |
モラルカリキュラムの目標 |
学科 1 インターネットとじょうほうの仕組み
インターネットってなに?
情報って何?
情報は人が作っている |
●聞いたことは正しく伝える。
(A2)参画する態度
科学的な理解 |
学科2 インターネットを使う心構え
調べるって何?
人のじょうほうを使う |
●人の情報をつかうときは出典の明示をする
(B3/B4)
科学的な理解
参画する態度 |
学科3 インターネットじょうほうの使い方
引用 個人じょうほうろうえい
ウイルス 有害じょうほう |
●知らない人に聞かれても自分や友だちの家
の電話番号等は教えない(c2/c5/c6)
参画する態度 |
学科4 インターネットの世界
調べるときは
まとめるときは
便利だけど気をつけて
インターネットを使う約束 |
籠原小学校インターネットガイドライン
参画する態度 |
実技1 じょうほうのさがし方
図書館の本の中からじょうほうを探す
じょうほう源を記録する |
●人の情報をつかうときは出典の明示をする
(B3/B4)パフォーマンステスト
情報活用の実践力
参画する態度 |
実技2 インターネットの見方
ブラウザの使い方 戻る 進む |
○コンピュータ操作カルテ
インターネットホームページを見る
パフォーマンステスト |
実技3 インターネットでのじょうほうのさがし方
リンク集から カテゴリ検索
サイトの記録 コピー貼り付け |
●人の情報をつかうときは出典の明示をする
(B3/B4)パフォーマンステスト
○コンピュータ操作カルテ
カテゴリー検索
図と文字のコピー貼り付け
パフォーマンステスト |
実技4 じょうほうの使い方
レポートの作り方
出典の明示 |
●人の情報をつかうときは出典の明示をする
(B3/B4)パフォーマンステスト |