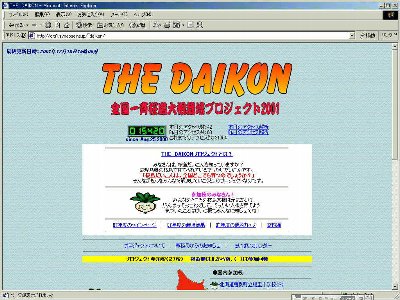 インターネットをはじめとして、マルチメディア通信技術が、学校の場にも普及するようになった。子どもたちは教室をとびだし、異学年、遠く離れた学校、世代間、外国に至るまで、相互の情報提供をしたり、会議をもったり、共通のプロジェクトを展開することができるようになった。このような学習形態を交流学習と言っている。
インターネットをはじめとして、マルチメディア通信技術が、学校の場にも普及するようになった。子どもたちは教室をとびだし、異学年、遠く離れた学校、世代間、外国に至るまで、相互の情報提供をしたり、会議をもったり、共通のプロジェクトを展開することができるようになった。このような学習形態を交流学習と言っている。交流学習では、出会う人たちの間の異質性に注目し、「違い」を学び、相互に活かし合い、協力することによる相互理解の深化、共同で調査研究、作品の創作などの実践が行われている。参加する人たちの協力、協調の上に成り立つ学習であることから、共同学習の意味合いもある。従来は、技術もなかったこともあり、このような交流学習はなかなか進まなかった。
本校では、米の販売に伴う、米作りを行っている学校との交流、米の購入者との交流、ダイコンプロジェクトへの参加、ケナフ栽培を進めている学校との交流などを進めている。情報の豊富化、視点の転換、他者理解、異質への寛容性の獲得などが成果としてあげられるのではないかと考え、実践を進めている。
写真は、本校も参加しているダイコンプロジェクトである。桜島ダイコンの産地である鹿児島県の小学校が中心になり、全国の呼びかけ、桜島ダイコンの栽培を行い、成果を報告しあおうというプロジェクトである。参加校のホームページにダイコンの項目を載せ、成長の具合を報告・情報交換しあいながら、交流を深めることを目的としている。