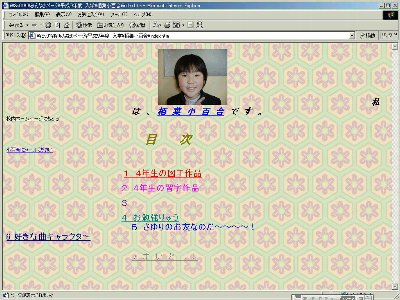 本校の情報環境の基盤となるものである。一人一人のページの充実がそのまま、子どもの情報技術の習得状況や様々な学習の進展状況を物語っている。
本校の情報環境の基盤となるものである。一人一人のページの充実がそのまま、子どもの情報技術の習得状況や様々な学習の進展状況を物語っている。本校の最も基本になる技術は、ホームページ作成技術である。ホームページ作成ソフトを利用して、ページに様々な情報を書き込みながら、発展させるのである。現在、4年生以上(3年生も始めたが)が自分のページを自力で作成できる。(作成できるというのは、ホームページ作成ソフトでテキスト文の入力、画像、映像の取り入れ、ページ作成ができ、掲載する材料の切り取り、複写、貼り付け、ファイル操作ができるというレベルを指している)
子どもたちのホームページ作りは、平成10年度に学校のホームページを公開した際に子どもを参画させるということから始まっている。学校のホームページ上に、「学校日記」の項目を設け、子どもがデジタルカメラでその日の事件(?)を撮影し、圧縮加工し、コメントを付け、ホームページに載せている。この「学校日記」の作成は子どもたちが自力で行っており、「学校日記」作成を通して、子ども同士で技術(操作方法や取材方法)を伝えている。上下の学年でペアを組むことで技術を伝え、現在、4年生(3年生も修得しつつある)にまでホームページ作りの技術は伝わっている。
一人一人のページは、以下のような内容で作成されている。メインのページに自己紹介が入り、そこからいろいろな項目へとリンクされる。(子どもが工夫したページ構成が行われる)
ア 自分の作り上げたものの記録
自分の作品や観察記録、見学先のまとめ、授業などを記録し、デジタルポートフォリオ的に利用できる。(テキスト、写真、映像による記録が行われる)
イ 調べ学習に利用したWebサイトへのリンクや結果のまとめ
インターネットの利用は、教科の授業で積極的に行われる。そのほとんどが調べ学習である。方言、地域の生活、植物検索など、百科事典代わりにも利用している。その記録をリンク集としてページに記録していく。
ウ プロジェクトの記録・作業ページとして (共同作業を進める際に中心となる)
実行委員や班長になった子どものページがプロジェクトを進めるために利用するページとなり、関係の情報が蓄積される。グループや共同で利用する。(米作りや宿泊学習の計画などで利用されている)
エ 他の子どもへのリンク
子どものページ同士の相互リンクである。ある種の情報を持つ子どものページへのリンクが張られる。共同で何かを行っている子ども同士は同じ項目をそれぞれのページに掲載し互いにリンクすることで、情報が得られるようになっている。
オ 交流
リンクと同じようだが、メールの欄を作ることで、交流を深められる。Hotmailを利用して、メールの交換を行っている。外部との連絡にも使用される。
オ 掲示板
意見の交換をすることが出来、相互評価をしやすくすると考え、設置を予定している。
ホームページ作成について
・パソコン室のサーバーに、一人一人のフォルダがある。
・フォルダは、入学年度ごとにまとめられ、一人一人のフォルダには、行事、写真などのフォルダを作っている。一人一人のフォルダ内は自由に使うことができる。
・作成ソフトは、ホタルver.6を使い、自分のフォルダからファイルを呼び出し、自分のフォルダに保存する。ファイル操作(切り取り、コピー、貼り付け)は、4年生以上ができるようになった。
・操作方法は、担任の指導の他に、上級生に教わるという学習の体制ができている。(職員は新東小学校のホームページ作りを担当することで技術を習得している)
一人一人のページの発展性
・例えば、毎日の授業記録、1時間の授業が終わると板書が残る。板書は、その時間学習したことの集積である。デジタルカメラで撮影し、個人のホームページに掲載する。板書事項から、クリッカブルマップを作り、更に詳しい情報をリンクさせることで、1枚の写真からWeb式の発展をさせることが出来る。これらは将来に亘って継続される行為となる。そこに独自の情報環境が構築されていく。
・一人一人のページは、単に現在を記録するためにだけに作るのではなく、将来に亘って継続的に発展できる可能性のあるものである。校内に築いた自分のホームページは、CDROMその他の媒体を使って、携えて卒業でき、他のパソコンに移すことで新たな展開を始めるのである。