(1)「お絵かきソフトでスライドショー作り」(3年生〜)
子どもたちが一番利用する機会の多いお絵かきソフト(インタープログ社のキットピクススタジオ2001)では,スライドショーが作成できる設定になっている。紙にかいた下絵をもとに,お絵かきソフトで表現する。一つひとつの絵を自分のイメージしたサウンドやタイミングでアニメーション設定し,スライドショーづくりをしている<図7>。
この活動では,子どもたちに,自分の作品をつなげて一つのお話に仕上げる面白さを味わってもらいたいと考えている。同時に,創造的表現活動を経験することで,コミュニケーション能力の高まりを期待している。将来,簡単なプレゼンテーションを作ることを求められた時に,この活動で身に付けた力を生かして,データや自分の思いを表現してもらいたいという願いも込められた活動である。
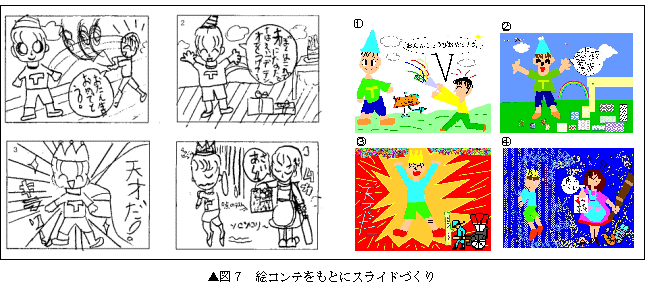
|
(2)「電子メールでの交流を教科・総合の学習に生かす」(4年生〜)
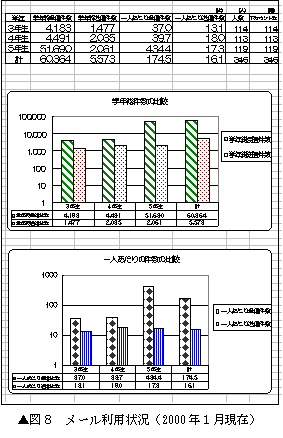 3年生の2学期から練習を開始する電子メール。実際に校外の人とメールを交換するようになるのは,4年生の後半くらいになることが多い。休み時間をふくめて,教科,総合,パソコンタイムの時間に,主に個人または小グループ単位で活動していく。<図8>
3年生の2学期から練習を開始する電子メール。実際に校外の人とメールを交換するようになるのは,4年生の後半くらいになることが多い。休み時間をふくめて,教科,総合,パソコンタイムの時間に,主に個人または小グループ単位で活動していく。<図8>
(3)「Web化技術を教科・総合における表現活動に生かす」(4年生〜)
教科,総合の時間において,学習成果や思いをレイアウトし,パソコンタイムを使って,Web表現していく。ワープロソフト(Microsoft社のWord2000)を活用し,お絵かきソフトで作成した絵や図,デジカメで撮影した画像などをテキストデータに貼り付けながら,それをWeb保存している。できあがったWebに作品をみて,電子メールを使って意見・感想交流をしている。
本年度の主な取り組みとしては,国語科の詩づくりを通しての実践と,社会科における水道学習の調査結果を紹介する実践と,総合学習としての自分が体験したことについての交流ページの実践などがある。
ア. 実践例 国語科「詩の広場」<4年生>
まず,ワープロソフトを利用して,あらかじめ名前や題など必要最小限のフォーマットされたファイルに,自分の思いを文字として表現した。今回は,全員が「何のことかな?あっそうか!」というテーマで詩づくりをした。<図9>の例のようにあきひろ君は,「ぼくは,小さな森のじゅうにん」という題の詩の中で,冬眠からさめた森の生き物になったつもりで,春になった喜びを表現している。
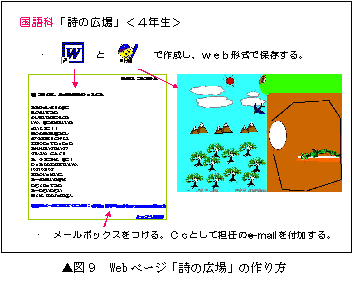
次に,その情景をお絵かきソフトで描き,挿し絵とした。
いったい森の住人が何なのか,考えさせられる。
作品を通して,コミュニケーションが深まるように,詩の最後には,メールボックスを用意した。
ボックスには,カーボンコピーとして,担任へも,子どもたちのメールがとどき,やりとりが把握できるしかけにして,評価に役立てることができるようにした。
<図10>はWeb化保存した作品である。4年生では,すでにこの段階でテキスト文書に,図のレイアウトや貼り付けなどができるようになっている。
できあがると友達から電子メールが届き始め,交流がスタートした。
子どもたちの保護者を中心に外部へ公開してもらえないかという要望が届き,本校のホームページから,期間限定掲示ページとしてアクセスできるようにした。
それぞれの詩に対して,家でみた家族から電子メールが届き始めた。家で相対して会話をするだけでなく,文章表現を通して,親子のコミュニケーションがはじまった。<図11>
全く知らない人や転校した友達から突然電子メールが届いたりして,子どもたちは,詩づくりや,表現への興味・関心を高めることができた。
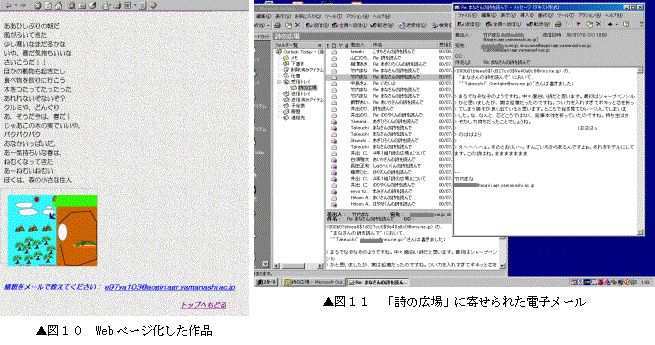
イ. 実践例 社会科「みんなでつくった水道百科〜私たちの生活と水〜」<4年生>
本実践では,自分たちの生活に必要な水道の水は,どのようにたくわえられ,どのように送られてくるのか,また,どんな工夫や努力がされているか,自分たちが使った水は,どのような状態でどこへ流れ,どのように処理されているか学習した。
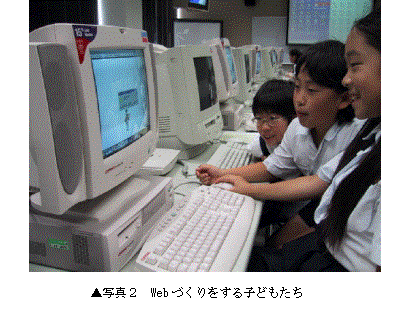
学習にあたっては,ダムや浄水場,浄化センターについて見学の機会や資料を均等に用意するが,子どもたち一人ひとりは,それらを網羅的に学習するのではなく,自分が疑問に思ったことを興味関心に応じて追究学習できるような場を設定した。それぞれが得た情報や思いについては,Webページとして保存した。ワープロソフトを活用し,お絵かきソフトで作成した絵や図,デジカメで撮影した画像などをテキストデータに貼り付けながら表現した。できあがった作品を仲間と見合い,電子メールを使って交流することで,情報や思いを共有し,社会的事象の見方・考え方を深めることをねらった。
<図12>は,実際に子どもがつくった作品である。当初は,普段使い慣れた鉛筆やペンを使って紙に表現する方が細部にわたってうまく表せるのではないかと予想した。しかし,パソコンタイムの時間(週1時間)に培われたリテラシーは高く,ダムや浄水場の絵など,お絵かきソフトを使っても,自由に描くことができている。
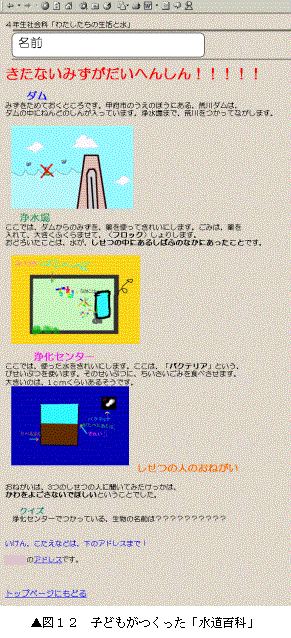
|

|
子どもたちが作ったWebページは,それぞれサーバに保存し,校内のどのクライアントマシン(パソコン)からもブラウザを通して見ることができるようにした。
その結果,休み時間を利用してWebページを見る子どもたちが現れた。発表時間や掲示スペースを気にすることなく仲間とコミュニケーションを図ることが可能となった。実際にこの実践についての,メールは,きちんと担任にカーボンコピー(Cc)されたものだけで160通あるが,そのうち27のメールが社会科やパソコンタイム以外の時間での交流であった。
次に子どもたちのメールのやりとりを示す。<図13>
初めのうちは,お互いのWebページについての質問が中心であったが,後半になると別の子のWebページを参考にして,自分たちの疑問を解決しようとしている。コミュニケーションが高まり,社会的事象の見方・考え方の深まりを期待できるまでになってきた。
4年生にとって,社会科学習で,Web化技術を取り入れた表現活動を行うのは,本実践が最初であった。今まで行われてきた新聞づくりなどの活動にあわせて,子どもたちの表現方法の選択肢を広げたことに意義があったと考える。今後は,今回の学級内で行った交流を,どこまで広げることが有効であるか,単元の内容をみながら検討して,表現活動の助けとなる交流の輪を広げていくことが必要である。
(4)「交流校とのテレビ会議」(3年生〜)
| 広い視野で物事を考え,学習問題を解決できるように,教科,総合で積極的に交流学習を行っている。パソコンタイムでは,テレビ会議システムを使っての交流を,学年全体または小グループで推進している。平成11年度には,3年生が総合学習の中で,上海日本人学校の友達と交流した。互いの中にある,物の感じ方を知り,共生の素地を養った。5年生もやはり総合学習の中で,宮城教育大学附属小学校と交流した。自然,環境に関わる課題を見いだし,お互いに意見交流した。 | 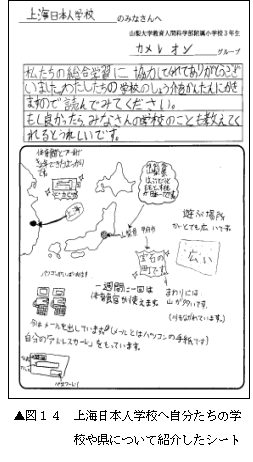 |
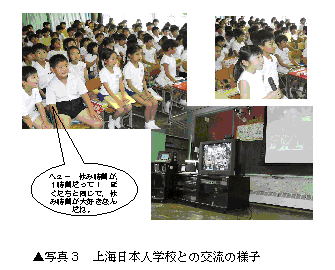 |