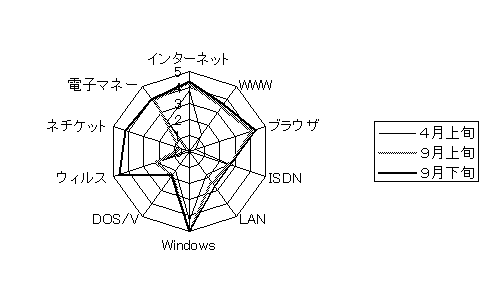
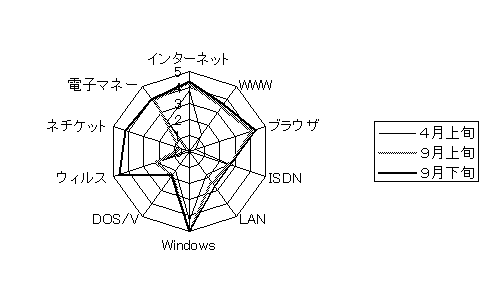
図 4-1 用語知識の変化
4.4.2 意識の変化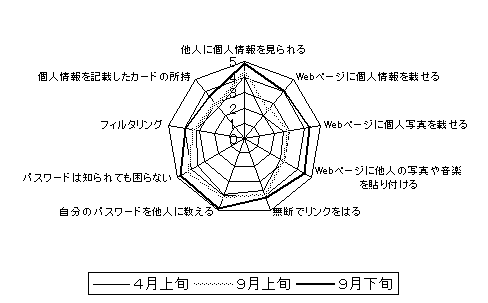
図 4-2 倫理意識の変化
4.4.3 態度の変化| 人前で意見を言うのはやっぱり今でも恥ずかしいけど、メディアを使って意見を主張することには抵抗が少ない。これをきっかけにだんだん人前でしゃべれるように慣れるような気がする。 |
| もっとコンピュータを触る授業だと思っていた。そうでないと聞いてちょっとがっかりしたが、取り上げられる内容が他のどの教科にも出てこないものばかりでとても面白かった。 |
| 授業以外の時間にインターネットが自由にできるようにしてほしい。 |
| 歴史の中に情報を見出す授業が印象に残っている。情報ってコンピュータがなくてもいいんだと思った。 |
| コンピュータはまだ家にないけど、とりあえず電話とファックスをもっと使いこなせば今より生活は情報化されるような気がする。 |
| コンビニの授業や情報倫理の授業などで、情報社会の裏側を見たような気がする。ボヤーッとしてたら生き残れないような気がする。 |
| ひとつのことをいろんな角度から見る癖がついた。ちょっとへそ曲がりになった気もするけど。 |
| いつの間にかワープロ打てるようになっていた。 |