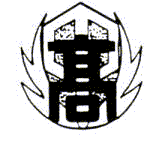
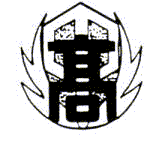
図3-2 兵庫県立神戸甲北高等学校の校章
まず、生徒を中央に集め、生徒手帳にある校章を拡大コピーしてホワイトボードに貼り付けた。この校章のデザインに何が込められているかを生徒たちに尋ねた。まず、学校名から「甲」「北」「高」がデザインされていることは見たとおりである。そこから「甲」の上部が六角形にデフォルメされている理由、「北」の変形は何を意味するかの二つについて考えさせた。生徒手帳にはそのすべてが記載されているが、生徒はそうした記述があること自体知らない。常時携帯するように指導されている生徒手帳を持っていない生徒も多く、授業の本題に入る前にそうした点について指導する時間を取らざるを得なかった。


図3-3 日本の道路標識
生徒は、多数ある道路標識も形と配色で分類すると非常に単純な類型化ができることを発見していった。
図3-4 文字を含む標識「止まれ」



図3-5 日本、ドイツ、ニュージーランドの速度制限標識



図3-6 関西電力、携帯電話使用禁止、暴力禁止
3.3.6 生徒の感想