電子会議室は、教師のホームページからそれぞれの会議室に入ることができるようにリンクが張ってある。図1は、各会議室への案内があるホームページである。
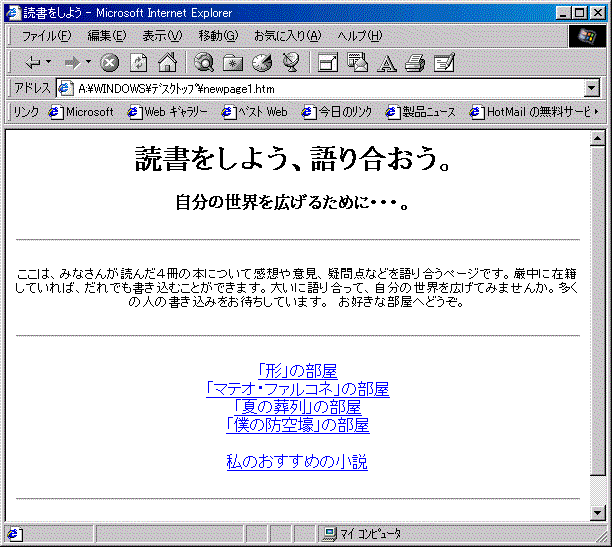
図1 教師のホームページ
それぞれの作品ごに電子会議室を用意し、感想や疑問点を書き込ませた。また、別フレームで他の書き込みを参照した。
仲間の書き込みに応えるには、書き込みの題をクリックすると書き込みフォームが現れるので、それに書き込んだ。図2は電子会議室の画面である。
① 授業実践プログラム
| 学年 | 第3学年 |
| 教科 | 国語科 |
| 担当者 | 石田史明 |
| 単元・領域 | 理解領域「読書の秋~短編小説を読もう」 |
| 学習目標 | ・短編小説を読んで感想を持つことができる ・多くの人の感じ方や感想を知り、自分の読みを深めることができる ・深まった読みをレポートにして発表することができる |
| 目標設定理由 | 中学生の読書離れが指摘されて久しい。印象的な短編小説に出会わせること、また、多様な読み方、感じ方に触れさせて読みを深めさせることでこの現状を改善し、少しでも読書に親しむきっかけになることを願い、上記の目標を設定した。 |
| 実施時期 | 9月中旬~10月下旬 |
| 内容・時数 (全5時間) | 第1時 導入、学習の見通しの確認と授業で扱う短編小説の提示。 提示する小説は以下の4編。 ①「マテオ・ファルコネ」(メリメ 作、堀口大學 訳) ②「夏の葬列」(山川方夫 作) ③「形」(菊池寛 作) ④「ぼくの防空壕」(野坂昭如 作) 第2時 読みたい小説を選択し、各自が読む 第3時 (コンピュータ室)一読しての感想、疑問点をまとめ、校内 ネットワークの電子会議室を通して発表する。なお、4編の小説は全 校生徒・教職員にも提示し、3学年以外の生徒や教職員でも、小説へ の感想、疑問点があればメディア・スペースのコンピュータを用いて 電子会議室へ発表してもらう。 第4時 (コンピュータ室)校内ネットワーク上に作品別にまとめられ た感想、疑問点を読み、それらへの返信や感想を電子会議室に書き込 む。 第5時 仲間の感想、意見を参考に個々の課題をレポートにまとめる。 |
| 備考 | ※使用ソフト インターネットエクスプローラ(生徒) フロントページ(担当教師) 全校の読書活動を盛りあげる一助になるよう、優れたレポートや、生徒や教師による「おすすめの小説」をホームページ上で紹介することも考えている。 |
② 授業で利用した電子会議室
電子会議室は、教師のホームページからそれぞれの会議室に入ることができるようにリンクが張ってある。図1は、各会議室への案内があるホームページである。
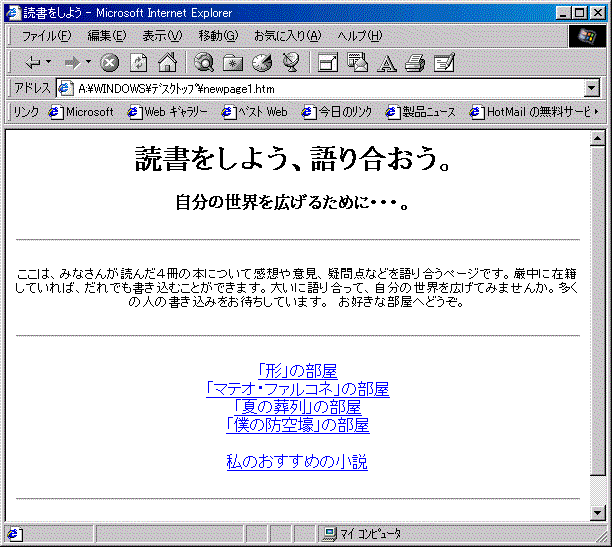
図1 教師のホームページ
それぞれの作品ごに電子会議室を用意し、感想や疑問点を書き込ませた。また、別フレームで他の書き込みを参照した。
仲間の書き込みに応えるには、書き込みの題をクリックすると書き込みフォームが現れるので、それに書き込んだ。図2は電子会議室の画面である。

図2 電子会議室の例
学習で使用したプリント等について次のようにした。
○4つの作品は人数分冊子を印刷し、全員に配布した。
○準備なしにコンピュータに向かわせるのは、考えをまとめてキーボードに打ち込む速度に差が生じるため、下書き用の原稿用紙を用意し、事前に書かせた。文字数は100字以上、200字以内を目安とした。
○コンピュータ室での時間を有効に生かすため、操作法をプリントにし、事前に指導した。また、匿名を認めたので、書き込む上でのマナーもそこで指導した。
③ 生徒の感想
○いろいろな小説を読むことができて楽しかった。
○自分の感想や疑問点を口頭や手書きの文字で発表するのではないこと、また書き込んだものがコンピュータで見られることが新鮮で楽しかった。
○他学級の人の書き込みも読めるので、参考になり、楽しかった。
○多くの人の意見が読めることがいちばん楽しかった。いろいろな感想があるのだなあと思った。
○仲間に通じる意見を書き込むには作品を何回も読まなければならないので大変だったが、読みが深まったように思う。
○自分の書き込みに返信が来るのが楽しみだった。
○時間がなく、二人にしか返信を送れなかったが、もっと多くの人に送りたい。
○返信で「よく意味が分からない」と言われて少し腹が立ったが、読み返してみてその通りだと思った。発表の前にもっときちんと読み直せばよかった。理由をきちんと書いてくれたので納得ができた。
○意見を発表するときは読む人のことを考えることが大切だと分かった。
○返信で自分の考えに賛成してくれると、とてもうれしかった。同じ感想でも印象に残った場面は人によって違うことがわかった。
○返信を読んで自分の読み方が浅かったところが分かって勉強になった。
○キーボードに文章を打ち込むのが大変だった。
○意味や言葉が難しい文章があって内容が十分理解できない小説があった。
○「書き込み」と「返信」を間違えてしまった。
○指定された文字数が少なく、自分の考えを十分に表現できなかった。

④ 反省・今後の課題
私にとって、文学作品を扱った授業では、個々の感想や疑問を授業の中でどのように生かしていくかが大きな課題である。従来の一斉授業では個々の感想や疑問をどのように引き出し、共有させるかに困難を感じていた。
今回、いわゆる「初発の感想」の発表とそれに対する質問・意見をネットワークで結ばれたコンピュータ上で行ったわけだが、自分の考えを発表したり、他の考えを知るためにコンピュータを使うこと、つまり、コミュニケーションの道具として国語科でのコンピュータの使用は非常に有効であることが分かった。
しかしながら、課題として残った点もいくつかあった。
今回の授業では「短編小説に親しもう」という目標のもと、生徒の興味・関心や適性に対応するため、4つの短編小説を取り上げたが、生徒の「書き込み一覧」を見ると基本的な読み取りに誤りがあるものが見られる。そのような生徒に対する指導が十分とはいえなかった。また、教師が提示した4作品が生徒の興味や関心に対応していたかという点でも少し課題が残ると思う。教師側での教材の発掘や開発にも力を入れていきたい。
また、今回の授業を生徒の今後の読書生活にどのようにつなげていくかも考えなければならない点であろう。 & ネットワークコンピュータの電子会議室を使用した授業では、いつでも、だれでも書き込み(情報発信)や閲覧ができるということが大きな利点ではあるが、比較的設備に恵まれた本校においてすら、「いつでも、だれでも」が実現されているとは言い難い。コンピュータは、従来の個々に計算をしたり文書を作成したりといった使用形態に加えて、今後はコミュニケーションの道具としての重要度がますます高まると思われる。そのために、今後はより一層の設備面での充実が必要であると考える。
コンピュータの使用においては、日本語入力の速度に個人差が大きく、電子会議室への書き込みに困難を感じる生徒が少なからず見られた。コンピュータを用いて情報を発信することを考えた場合、文字の入力は重要な技能である。訓練である程度克服できる部分と思われるので、小学校や中学入学時からの継続的な指導の必要性を感じた。
⑤ 生徒の書き込みの一例 (菊池寛 作「形」への書き込み)
NO.6 題名:形とは・・・。
書き込んだ人: シキ 3年
《コメント》
新兵衛殿も猩々緋と唐冠の兜を貸さなければあんなことにはならなかったもの を。本当にバカなことをした。きっと、後悔していることだろうに。この題名の 形というよりかは、見た目といった感じで、本当は強くなかったということだな。 結局は。これを読んでいると、本当に見た目とは大切なものだと感じるが、やは り見た目より中身だと思えてくる。
返事:Re: シキさん
書き込んだ人: カリブの海賊$3年
《コメント》
僕もシキさんの意見には、賛成です。僕も新兵衛は後悔してると思いま す。しかし、僕は新兵衛は強かったと思います。なぜなら、どんなに有 名でも昔は無名の侍、そこから自分の実力で数々の武勲をたてて、ここ まで恐れられるようになったのだから、決して新兵衛は弱くはないと思 います。どうですか???