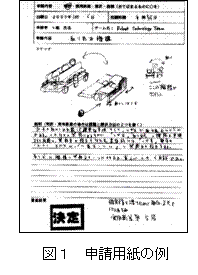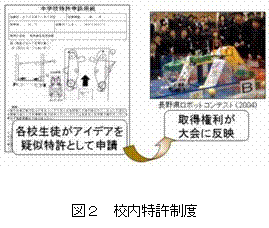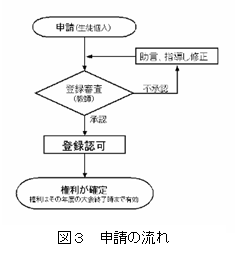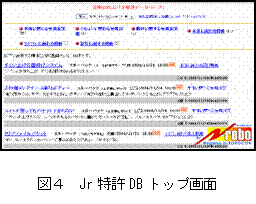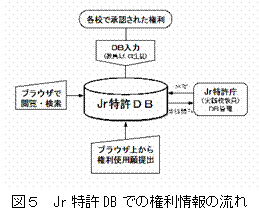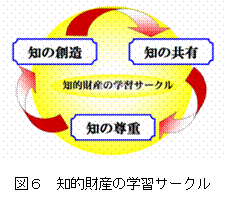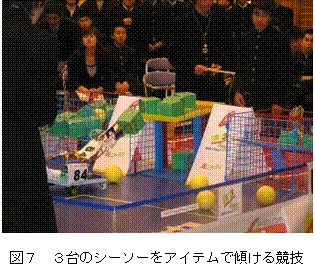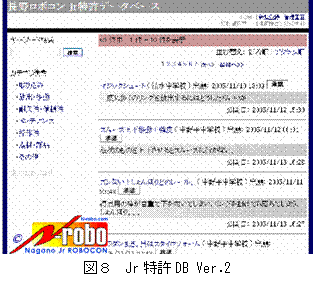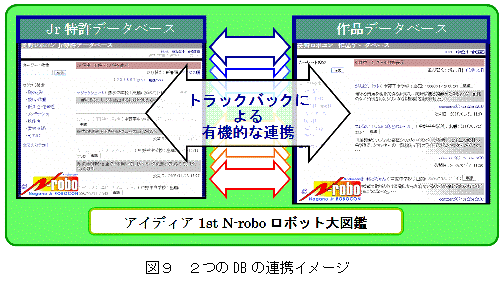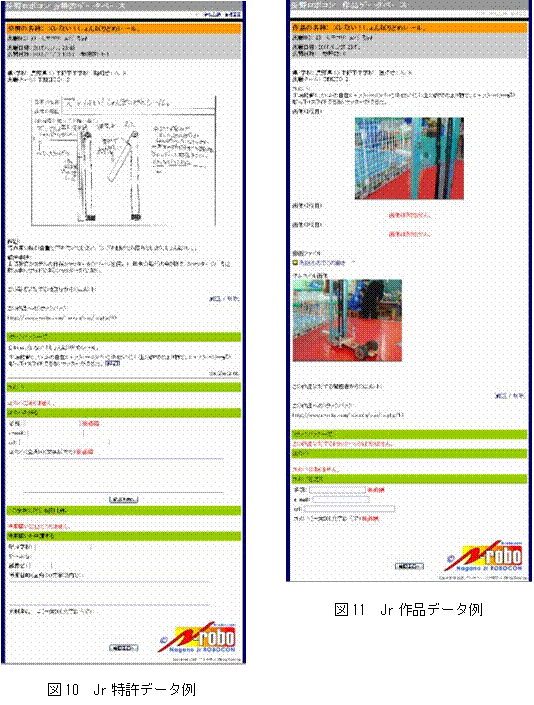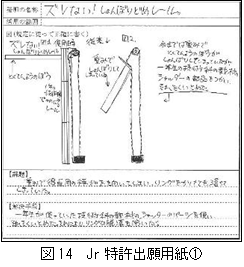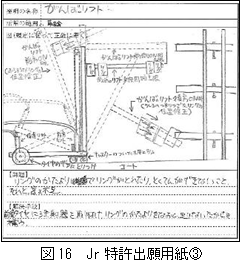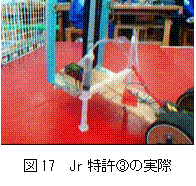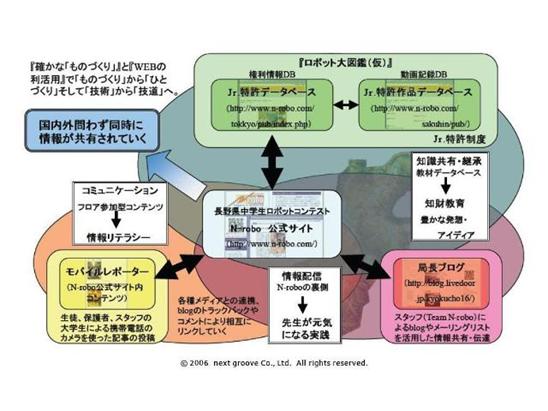|
�Z�������f�[�^�x�[�X�����ɂ����m�I���Y���w�K�Ə�p�̎��H�͂̈琬 �`���w�Z�Z�p�ȁu���{�b�g�R���e�X�g�v�ɂ����鎎�݁` ��\�ҁ@�y�c���� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�y�v��z |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
���w�Z�̋Z�p�E�ƒ�Ȃ̋Z�p����i�ȉ��Z�p�ȁj�ł͋ߔN���{�b�g�R���e�X�g�i�ȉ����{�R���j������ɍs����悤�ɂȂ��Ă����B���{�R���ł͑n���H�v�̗͂��d�v������Ă���C�n�ӍH�v�̗͂����L�����߂ɁC���{�b�g����̉ߒ��ŋ@�\����̍H�v�Ȃǂ��[���I�ȓ����Ƃ��Đ\������Z���������x��n�Ă��C���쌧�̒��w�Z�ɂ����Ď��H�������B���H�̐i�W�ɔ����C�����Z�œ����������L���邽�߂ɁCJr�����f�[�^�x�[�X���J�������BJr�����f�[�^�x�[�X�����p���C�̌��I�Ȓm�I���Y�̊w�K�����邱�ƂŁC�m�I���Y�ւ̈ӎ���A�C�f�B�A�̕\���͂Ƃ�������p�\�͂̈琬�����҂����B �@�{�����́C�Z�������f�[�^�x�[�X�����ɂ����m�I���Y�w�K�������ʓI�ɍs�����߂ɁC�Z�������f�[�^�x�[�X�̉��ǂƍ�i�f�[�^�x�[�X�̊J���y�т��̋�����ʂ̌���ړI�Ƃ����B�O�N�܂ł̎��H���͂ɂ��ƂÂ��C�d�l���������C�Z�������f�[�^�x�[�X�̉��ǂƍ�i�f�[�^�x�[�X���J�����C���쌧�̒��w�����{�b�g�R���e�X�g���Ŋ��p�������B �@���H�̒��ł́C�����̌�����Q���e�Z�ɂ���ēo�^����C�����������L���邱�Ƃ��ł����B���H�Z�̐��k��Ώۂɒ����������ʁC�m�I���Y�̖�ڂ�d�v���̗�����n�ӍH�v�ȂǂɐL�т�����ꂽ�B�\���͂ɂ��Ă͍���̉���ł���B�w�����t��Ώۂɂ��������̌��ʁC�m�I���Y�̊w�K�ɍm��I�ȕ]���邱�Ƃ��ł����B �@�ȏ�̂��Ƃ���C�{�������ړI�Ƃ����V�X�e���͊J���ł������ƂƁC�m�I���Y�𒆐S�Ƃ�����p�\�͂̈琬�Ɍ��ʂ����������Ƃ������ꂽ�B����́C��i�f�[�^�x�[�X�̊��p��i�߂�Ƌ��ɁC����ɏڍׂȕ��͂����Ă����\��ł���B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�P�D�@�͂��߂� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�@�P�D�P�@�Z���������H�̊T�v�@�@
�@�Z���������x�Ƃ́C���{�b�g����̉ߒ��ŋ@�\����̍H�v�Ȃǂ������̓����Ɠ����悤�ɐ\���p���Ő\�������C��������p�V�ĂƂ��ď��F�����ƌ����������Ƃ����A�C�f�B�A��F�߁C�ی삷�鐧�x�ł���i�}�P�j�B���F���ꂽ�����͌f���Ō��J����C���݂��ɋ��L����C�L�鐧�x�ł�����B���`�[�������̌������g���ꍇ�͎g�p�肢���o����`��������B�����Ă��̌������������̃n���f�B�|�C���g�ƂȂ�C�����𐔑������`�[���������������ŗL���ƂȂ鐧�x�ł���B�܂����{�b�g��܂�A�C�f�B�A�܁C�����܂ȂNJe�܂̑I�l���ɂ�����������e���l�������i�}�Q�j�B�A�C�f�B�A�̐\���̗����}�R�Ɏ����B �@����13�N�x�܂ł̎��H�͊w�Z���݂̂ŁC�����̊w�Z�Ԃŏ�L���ł��Ȃ������B�����ŃC���^�[�l�b�g��ɍZ�������f�[�^�x�[�X�V�X�e���i�ȉ��C�Z������DB�j�����삵����14�x�̒��쌧���Ŋ��p�����Ƃ���C�������̊w�Z�ԋ��L��k�̑n�ӍH�v�̈ӗ~����C�m�I���Y���̊w�K�ւ̔��W�Ȃǂ̉\�����������ꂽ�B
�@�P�D�Q�@�i�������c�a�ɂ��ā@ �@�����Z�Ō����������L���邽�߂ɁC�ȉ��̗v���ŃV�X�e�����J�����C�i�������f�[�^�x�[�X�V�X�e��
�iJr����DB�j�ƌĂԂ��Ƃɂ���(�}�S)�B �i�P�j�C���^�[�l�b�g�ɐڑ�����CWeb�{�����ł���N���C�A���g�ł��悤�ł��� �i�Q�j�u���E�U�ォ��S�Ă̑��삪�ł��� �i�R�j�Z�������\���p���̓��e���S�ď����ł��� �@�u�Z���������x�v�̎��H�����Jr����DB�ł̌������̗����}�T�Ɏ������B�����܂��͐��k�ɂ����͂��ꂽ���������CJr����DB�ɒ~�ς�����B�������̏��F�͎Q���Z�̋������Ґ�����Jr���������������CJr����DB�̃V�X�e���Ǘ��S�����������F������B�e�Z�ł̓C���^�[�l�b�g���o�R���ău���E�U�Ō��������{��������C�K�v�ȍ�Ƃ��s�����肷��悤�ɂ���B�J�������V�X�e���͂�����A�̗�����l�b�g��Ŏ����ł�����̂ł���B �@�������̃J�e�S���͊e�Z�P�Ǝ��H���̌�����͂���C1)�{�̂Ɋւ����́C2)�����R���Ɋւ����́C3)����Ɋւ����̂̂R�ɕ��ނ����B�R�̕��ނ����ꂼ�������Ǝ��p�V�Ăɕ����C�v�U�J�e�S����ݒ肵���B���H�Z�����́C�ݒ肵���p�X���[�h�Ō������̏C����Ƃ��ł���B�o�^��Ƃ��o�ēo�^����C���F�����ƌ������͈�ʂɌ��J�ł��C�{���E�������邱�Ƃ��\�ɂ����B�@�g�p�肢���\�����ꂽ�ꍇ�C�o�^���[�U�̓p�X���[�h��p���ēo�^��ʂ���g�p�肢�̎��ł��C���̌��ʂ��ꗗ�ɕ\�������悤�ɂȂ��Ă���B
�@�P�D�R�@���ƍZ���������H�@
�@�Z���������H�̒��ŁCJr�����f�[�^�x�[�X�����p���钆�ŁC���k�B�͐V�����A�C�f�B�A�z���C�}�╶�͂ŕ\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ɔ��M���錠�����e�̋ᖡ������C�����Ɋ��ɓo�^����Ă��Ȃ����C�ގ��̌����͂Ȃ����������C��������Ƃ��������Ƃ��K�v�ɂȂ�B�����w�K�ߒ��̒��ŁC���̕\������W�Ƃ�������p�̎��H�͂��{���Ă����B�܂��{�V�X�e���̓I���W�i���e�B�̍����V�X�e���ł���Ɠ����ɁC���{�R���ȊO�ɂ����p�\�ȉ\��������C���H��ʂ�l�X�ȕ���ɍL�����邱�Ƃ����҂����B �@�ȏ�̂��Ƃ���C�Z���������x�����Ƃ����m�I���Y�̊w�K�ň琬�ł����p�̎��H�͂���я��ɖ𗧂��ƂƂ��Ĉȉ��̂R�_�����ߏo�����B �i�P�j�u��p�̎��H�́v�̈琬�ɂ��� �@�E�V�����A�C�f�B�A�z���C�\�����邱�Ƃɂ��Ă̊S�E�ӗ~ �@�E�C���[�W�����A�C�f�B�A��}�ƕ��͂ŕ\������\���� �@�E�A�C�f�B�A�����ǂ�����C���z�����肷�邽�߂ɕK�v�ȏ������W������W�� �@�E�f�[�^�x�[�X�ɓo�^�����茟�������肷��f�[�^�x�[�X�̑��삨��ь����Z�\ �i�Q�j�u���Љ�ɎQ�悷��ԓx�v�̈琬�ɂ��� �@�E�m�I���Y���̏d�v���ɂ��Ă̗��� �@�E�m�I���Y�̎d�g�݂ɂ��Ă̗��� �i�R�j���ɖ𗧂V�X�e����J���L������ �@�E�A�C�f�B�A���i�Ȃǂ̊w�K����~�ρE���L�ł���V�X�e���̊J�� �@�E�̌��I�E���H�I�Ȓm�I���Y�w�K�̃J���L������ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�Q�D�@�����̖ړI�ƕ��@ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�Q�D�P�@�����ړI�@�@ �@�Z�������f�[�^�x�[�X�����ɂ����m�I���Y�w�K�������ʓI�ɍs�����߂ɁC�Z�������f�[�^�x�[�X�̉��ǂƍ�i�f�[�^�x�[�X�̊J���y�т��̋�����ʂ̌���ړI�Ƃ���B �@�Q�D�Q�@�������@�@ �@���쌧�Ń��{�b�g����w�K�Ɏ��g�݁C���쌧���w�����{�b�g�R���e�X�g�ɎQ�����钆�w�Z��ΏۂƂ����B����15�N�x�܂ł̎��H�����ɁC�V�X�e���̉��P�_�����߂����C�V�����J������V�X�e���Ƌ��Ɏd�l����������B�d�l�Ɋ�Â��ăV�X�e�����J�����C���쌧���w�����{�b�g�R���e�X�g���̎��H�Ŋ��p���C�o�^�̒�����k����юw�����t��ΏۂƂ��������ŋ�����ʂ𑪒肷��B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�R�D�@�V�X�e���̊J�� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�@�R�D�P�@�i�������f�[�^�x�[�X�̉��Ǔ_�@�@ �@����15�N�x�ɐ\�����ꂽ�����Ǝ��p�V�Ă̓��e���J�e�S���ɕ������ނ����i�\�P�j�B �A�C�e���̎�荞�݁i�����Q�C���p�V��21�j�ƈړ��i�����T�C���p�V��10�j�����Z�ɒ��ڕς�镔���ł�����C�ł����������B�܂��C�A�C�f�B�A��\������ۂɁu�����v�Ɓu���p�V�āv�̂Q�{�ɕ����Ă������C���҂��ǂ��ŋ�ʂ��邩�Ƃ������m�Ȑ����Ȃ����߂ɁC���H�҂̒��ł����f�ɖ����C���k�ɂƂ��Ă��������ɂ������̂ł������Ƃ����ӌ����������B�Z�������c�a�ɂ��Ă��u�摜�t�@�C���̓��{�ꖼ�̏����v�u�J�e�S���̍ו����v�Ȃlj��ǂɊւ���ۑ肪���_��������ꂽ�B �@����ɁC�u���F���̏ڍׂ�m�肽���v�u�@�\�����Ȃ̂ŁC�\�ł���Γ�����Q�l�ɂ������v�Ƃ������H�҂���̗v�]�������������B����������Jr����DB������ɉ��ǂ���K�v��������C������܂ލ�i�f�[�^�x�[�X�i�ȉ���iDB�j�̍\�z���d�v�ł���ƍl�����B�܂���i�f�[�^�x�[�X�́CJr�����̃f�[�^�x�[�X�̌�������f����Ă���ꍇ���������Ƃ�����C�f�[�^���x���ŘA�����đ��ݎQ�Ƃł���K�v������ƍl�����B �@�ȏ�̂��Ƃ���Jr�����f�[�^�x�[�X�̉��ǂɂ͈ȉ��̂S�_���K�v�ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B �i�P�j�摜�t�@�C���̓��{�ꖼ�̏������\�ɂ��邱�� �i�Q�j�J�e�S�����Č������C�ו������邱�� �i�R�j�ł�����������i����܂߃f�[�^�x�[�X�������iDB���K�v�ł��� �i�S�j�Z������DB�ƍ�iDB�̓f�[�^���x���ŘA�����đ��ݎQ�Ƃł��邱�� �\�P ����15�N�x�̌������̓��e����
�@�R�D�Q�@�V�X�e���̉^�p�@�̌����@ �@����16�x�̌����ɐ旧���C����15�N�x�ɗp���Ă����Z������DB��15�N�x�̎��H���܂Ƃ߁C���������҂Ƌ��Ɋw��Ŕ��\���s�����B ���\���̎��^�ł́C�Z������DB�ɂ��č����]������Ɠ����ɁC�����̓����ł̓N���[���������d�v�ł��邪�C���̓_�͂ǂ����C�Ƃ�����������Ȃ��ꂽ�B ���������ɁC����15�N�x�̎��H���]�����Ȃ���C����16�N�x�̉^�p�@�ɂ��Č����������B �@����15�N�x�̎��H�������������ʁC�ȉ��̂R�_�����炩�ɂȂ����B �i�P�j�������Ǝ����̃n���f�B�|�C���g��A�������邱�Ƃ́C���k�̏o��ӗ~����ɗL���ł��� �i�Q�j���H�҂ƕʂɒS���҂�u���C���O�܂Ő\�����t������悤�ɂ���K�v������ �i�R�j�����̐R�������薾�m���C���ʉ�����K�v������ �@�������Ǝ����̃n���f�B�̊ւ��ɂ��Ắi�P�j�̒m������C���ԓ��ɑ���̃R�[�g�ɂł��邾����������̃{�[���𑗂�Ƃ�������14�x�̋��Z�uPanic Ball 13�v����C���n���f�B�����m�ɂȂ�Ƃ����_���l�����C�R�̃V�[�\�[�ɂQ��ނ̃A�C�e�����ڂ��Ă����C���ԓ��ɂ�������X�������������Ƃ����uPanic Seesaw 3�v�i�}�V�j�Ƃ������Z�ɕύX�����B���Z���̂�ς��邱�ƂŁC�V�������z���������܂�邱�Ƃ����҂����B �@�i�Q�j�̒m������CJr����DB�ɓ��e������ƁC���H�҂̃��[�����O���X�g�ɓ]������C���������҂ɂ��Q�����Ă��炢�C�S���ňӌ��������Ȃ���C�ŏI��������������҂ɂ��Ă��炤���ƂŐ\����Ƃ́Y���������Ƃɂ����B �@�i�R�j�ɂ��Ă͕���14�x�̌����������C�����̓����ٔ��̔���̂悤�ɁC��̗���Q�l�ɂ��Ȃ���C�����Ǝ��p�V�Ă���ʂ��Ă��������Ō����������B �i http://www.n-robo.com/kcn/index.html
�j
�@�R�D�R�@�V�X�e���̊J���@ �@�V�X�e���̉��ǂɕK�v�ȗv���͈ȉ��̂S�_�ł������B �i�P�j�摜�t�@�C���̓��{�ꖼ�̏������\�ɂ��邱�� �i�Q�j�J�e�S�����Č������C�ו������邱�� �i�R�j�ł�����������i����܂߃f�[�^�x�[�X�������iDB���K�v�ł��� �i�S�j�Z������DB�ƍ�iDB�̓f�[�^���x���ŘA�����đ��ݎQ�Ƃł��邱�� ���̗v���ɂ��ƂÂ��Č��������҂̋Z�p���͂̂��ƁCJr����DB Ver.2�����p���邱�ƂɂȂ����i�}�W�j�B (http://www.n-robo.com/tokkyo/pub/index.php)
�@Jr����DB Ver.2 �ƍ�iDB�̃V�X�e���̊J���ɂ́CPerl�����T�[�o���ׂ����Ȃ����Ƃ���CPHP��p�����B�f�[�^�x�[�X��Ver.1�ł̓e�L�X�g�f�[�^�ł��������C�������x�����コ���邽�߂�MySQL��p�����B�T�[�o��Ver.1�Ɠ������̖��Ԃ̃����^���T�[�o�iRed Hat Linux2.4.27�CApache1.3.33�j��p�����B �@��{�I�ȏ�����Ver.1�Ɠ����ł��邪�CPHP�ōĐv�����ۂɓ��{��̃t�@�C�����ɂ��Ή������C���������N���ēǂݍ��߂Ȃ��G���[�ɑΉ������B �@�J�e�S���ɂ��ẮC�قȂ������Z�ɂ��Ή��ł���V�X�e���ƂȂ�悤�ɋ��Z�ƒ��ڊւ�镔�����ו������J�e�S�����ĕҐ����邱�ƂŁC���㑝�������Ă����ł��낤�����ɑΉ��������i�\�Q�j�B Jr����DB Ver.1�ł́u�{�̂Ɋւ��v�u�����R���Ɋւ��v�u����Ɋւ���v�̃J�e�S���ɕ��ނ��C�����Ǝ��p�V�Ă��Ă������CVer.2�ł͎��p�V�ĂƓ�������{�����C�J�e�S�����ȉ��̂悤�ɐݒ肵���B �u��荞�݁v�u���o�E�ړ��v�u�ϋv���E�M�����v�u�����e�i���X�v�u���쐫�v�u�f�ށE���i�v�u���̑��v �u�e�J�e�S���̒��o�v��u�\�������בւ��v�C�u�A�N�Z�X�����בւ��v���e�Ղł��邱�Ƃɉ����C�u�L�[���[�h�����v�@�\���t�����Ă���B �V���ȃJ�e�S���ɂ��C�قȂ������Z�ɑΉ�����Jr.�����̃f�[�^�~�ρE�������\�ƂȂ����B �܂��Cblog �₻�̎��ӋZ�p�ɑΉ������邱�ƂŁC������ő̌n�I�ɐ�������C��m��C���^�[�l�b�g��̂��̑��̏��Ƒo�����ŗL�@�I�ɘA�g����V�X�e���ւƔ��W�������B �\�Q�@�J�e�S���̍ĕҐ�
�@�ł������������{�b�g�̊e�@�\�̎d�g�݂⓮����`���C��i�������L���邽�߂ɂi��������i�f�[�^�x�[�X�i�ȉ���iDB�j��V�K�ɊJ�������BJr����DB�ɋ@�\��lj����Ă������Ƃ��l����ꂽ���C�\������ۂɔώG�ɂȂ链�邱�Ƃ�{�����ɕ��G�ɂȂ�\���C�m�I���Y���̋^���̌��̈Ӗ�����������邱�Ƃ����O���ꂽ�B�����ŁCJr����DB�͂P���̉摜�ƕK�v�ȃR�����g�ɂăA�C�f�B�A��\�����邱�ƂŒm�I���Y���̊w�K���\�Ȃ��Ƃ��d�����C���H�҂���̗v�]�ł����鏳�F���ꂽ�������̏ڍׂ͍�iDB��ݒu���C�V���ȃf�[�^�x�[�X�Ƃ��邱�Ƃɂ����B �@��iDB�ł́C���F���ꂽJr�����f�[�^�ƘA�g������K�v������C���e�ł���f�[�^�𑝂₷���ƁC��������e�ł��邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B�܂��C�Ɨ������f�[�^�x�[�X�Ƃ��Ċ��p������ɓ���C�J�e�S����ݒ肵����C�����@�\��t�������肳�����B �@�������C�ȉ��̂悤�ɐݒ肵���B �@�@�o�^�\�摜���@�@�@�@�F�@�R�iGIF�y��JPEG�摜�^100KB�ȓ��Łj �@�@�J�e�S���@�@�@�@�@�@�@�F�@Jr����DB�Ɠ��l �R�����g�@�@�@�@�@�@�@�F�@�S�p200�����ȓ��� ���搔�@�@�@�@�@�@�@�@�F�@�P�impg�Aavi��/500KB�ȓ��Łj ����̐����@�@�@�@�@�@�F�@�Z�� ����̃T���l�C���摜�@�F�@�P�iGIF�y��JPEG�摜�^100KB�ȓ��Łj �i�������c�a�Ƃ̘A�g�@�F�@�g���b�N�o�b�N�����p �@�Q�̃f�[�^�x�[�X�̓o�^���ڂ�\�R�Ɏ������B��iDB��Jr����DB�̃X�N���v�g�����p���C����╡���摜�ւ̑Ή��̉��ǂ��s�����B �����f�[�^�́C�ۑ�Ɖ�����i�͂ŋL�q���邱�Ƃ��ɂ��C�����̐}�܂��̓f�W�J���摜�P���Ƃ����B��i�f�[�^�́C�}�܂��̓f�B�W�^���J�����摜���R���Ƃ��C������\�Ƃ����B����͓����f�[�^�x�[�X�Ƃ̘A�g���l�����Đݒ肳��Ă���C���F���ꂽ�����f�[�^���m�F�ł��邱�Ƃ��˂�����B�J�e�S���͂ǂ���������ݒ�Ƃ��邱�ƂŁC�o�^���̍�����h���C���쎞�̌��������������邱�Ƃ��˂�����B �Q�̃f�[�^�x�[�X�̘A�g�ɂ́C�C���^�[�l�b�g��̓��L�Ƃ��ĕ��y���Ă��Ă���blog�ɗp�����Ă���g���b�N�o�b�N�@�\�������������B�g���b�N�o�b�N�@�\���������邱�ƂŁC�Q�̃f�[�^�x�[�X���f�[�^���x���ŘA�����C���݂��ɎQ�Ƃł��邾���łȂ��C�g���b�N�o�b�N�@�\���������O����blog�V�X�e�����Ƃ̘A�g���\�ɂȂ�B �Q�̃f�[�^�x�[�X�̘A�g�̃C���[�W��}�X�Ɏ������B�f�[�^���}10�C11�Ɏ������B�ǂ���̃f�[�^�ɂ��R�����g�𑗂邱�Ƃ��ł�B�����f�[�^�ɂ͎g�p�肢��\�����邱�Ƃ��ł���B���҂̘A�g�y�ъO����blog�V�X�e�����Ƒ��݂Ƀg���b�N�o�b�N���邱�ƂŁC���L�@�I�ȘA�g���L���邱�Ƃ��ł���ƍl���Ă���B �\�R�@Jr�����f�[�^�x�[�X�ƍ�i�f�[�^�x�[�X�̓o�^���ڈꗗ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�S�D�@���H�̕��� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�@�S�D�P�@���H�̊T�v�@ �@����16�N�x�̒��쌧���w�����{�b�g�R���e�X�g�iN-robo�j�����H����ɂ�����C�O�q�i�R�D�Q�@�V�X�e���̉^�p�@�̌����j�̕���14�N�x�̎��H�������������ʁC���炩�ɂȂ����i�P�j�������Ǝ����̃n���f�B�|�C���g��A�������邱�Ƃ́C���k�̏o��ӗ~����ɗL���ł���C�i�Q�j���H�҂ƕʂɒS���҂�u���C���O�܂Ő\�����t������悤�ɂ���K�v������C�i�R�j�����̐R�������薾�m���C���ʉ�����K�v������C�̂R�_���l�����C���Z�����Đݒ肵���B �i�P�j�̒m������C�R�̃V�[�\�[�ɂQ��ނ̃A�C�e�����ڂ��Ă����C���ԓ��ɂ�������X�������������Ƃ����uPanic Seesaw 3�v�i�}�V�j�Ƃ������Z����C���Z���̂�ς��邱�ƂŁC�V�������z���������܂�邱�Ƃ����҂��C�uPanic Ring�v�i�}12�j�Ƃ����R�[�g��̃����O��_�Ɋ|����Ƃ������Z���l�Ă����B���܂ł̋��Z������Փx����⍂���C�n���f�B�|�C���g�̗L������������������̂Ƃ����B �i�Q�j�̒m������́C�ߋ��̎��H�o���҂̒����瓖�Y�N�x�Q���s�\�ł���S���҂�u�����Ƃɂ����B�\���̓��[�����O���X�g�ɓ]�������̂ŁC�Ζ��n�ɊW�Ȃ����F���邱�Ƃ��ł��邽�߁C�C�O�Ζ��҂Ƃ����B�܂��C�i�R�j�̒m������S���҂��P�l�Ƃ����B���Y�N�x�̎��H�҂ł���R���e�X�g�̏�����{�b�g����x���ɒǂ��C�P�l�Œ��ߐ�ԍۂ̑����̐\�������F���Ă������Ƃɖ�����������ƍl�����邪�C���ڃR���e�X�g�Ɋւ�邱�Ƃ��ł��Ȃ��C�O�Ζ��҂ł���Ή\�ł���Ɣ��f�����B����ɁC�摜�ƊȒP�ȕ��͂Ő\�������̓��e���C�O�ɓ`�B���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������H�́C��p�\�͂̈琬�ɂ����т��ƍl�����B
�@�S�D�Q�@���H��@
�Ώۂ͒��w�Z�Q�C�R�w�N�ŔN�Ԃ̎��Ǝ��Ԑ��͂Q�w�N��70���ԂŁC�R�w�N��35���Ԃł������B �@A���w�Z�ł́C�Q�N���͂Q���ԑ����ŏT�P��C�R�N���͂P���ԂŏT�P��̑I�����ȁu�A�C�f�B�A1st���{�b�g�R���e�X�g�v���J�݂��Ă���B�Ƃ��ɂR�O�l���C�P�V�`�[���Ŏ��g�B�Q�N���͏��߂Ă̎��g�݂ł���C�R�N���͂Q�N������p�����Ă̌o���҂��������߂�B���쌧���w�����{�b�g�R���e�X�g���ւ̎Q����O��Ƃ��C�u�p�j�b�N�����O�v�ɎQ�����郍�{�b�g���`�[���őn�������B �@�D���Ȑl��C�̍����l�ƃ`�[����g�݂����Ɗ���Ă������k�������������C���������Ń`�[����Ґ����������S�⋦�͂ɂ���ă��{�b�g�̐���ɂ��������B�����͗F�B�Ƌ��͂�����ꏏ�ɍ�Ƃ����肷�邱�Ƃ͍D���ȕ����Ƃ������z�����������k�͔����ȏア���B ���̂Â����{�b�g�Z�p�ɑ��鋻���S�́C���̍u���Ŋw�Ԃ��ƂňȑO���������Ȃ�C�L�������悤�ł���B ��u�ґS����������\�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������CJr�����\���҂́u�A�C�f�B�A�͂ŕ\���́v��u�A�C�f�B�A��}�ŕ\���́v���\�����邱�Ƃɂ���Đg�ɂ����Ǝ��ȕ]�����Ă����B�܂��C�\�����邱�Ƃɂ���đ��`�[���̐\���ɑ��Ă������悤�ȋ�J������C��Ȃ��̂ł���Ƃ����ӎ������Ă����Ƃ�CJr����DB�ɂČ��J����C���쌧���Ŏ����̃��{�b�g���������Ƃ́u���̐l�̃A�C�f�B�A�d����ԓx�v���琬���ꂽ�悤�ł���B �R�N���`�[���wTEKITO-2�x(�}13)�̗l�q���Љ��B �@����Jr���{�R���o���҂��܂ނ��̃`�[���́C�j�q�R�l���q�P�l�őg�D����Ă���B���̓��̂P�l�͗����グ�����C�u�P�l�Ő��삵�����B�S�Ă̖������P�l�ł��Ȃ������B�v�ƍl���Ă����B�������C�����u��������u����͗ǂ��Ȃ��B���������̃`�[���Ő��삷��Ƃ������[���͎�낤�B�v�ƈӌ�����C�`�[���Ŋ������邱�ƂƂȂ����B �@�o���҂��܂܂�Ă������߂��CJr�������x�Ɉӗ~�I�Ɏ��g��ł����B�\�z�����i�K����\���p���𐿋����Ă����B�\���p���ɋL�����C��o�܂ł��Ă������C�u�������ł���܂ł͗a�����Ă����B�v�Ƃ������Ƃɂ��C�l�q�����Ă����B�ŏI�I�ɂ��̐\�����ꂽ���̂͌`�ɂȂ邱�Ƃ��Ȃ������B �@�~�[�e�B���O���d�ˁC��ƕ��S���Ȃ����Ƃ��i�݁C���{�b�g�̌`�������n�߂��B�����o��̂��Ƃ͍l���Ă����悤�ł͂��邪����Jr���{�R�������ԍۂ܂ł͎��ۂɐ\������ �邱�Ƃ͂Ȃ������B �@�\���������������́C�u�Y���Ȃ��I�����ڂ�ǂ߃��[���v�u������t�g�v�u�v���_���܂��B��̓X�^�C���t�H�[���v�̂R�_�ł������B
�y���́z�u�Y���Ȃ��I�����ڂ�ǂ߃��[���v�i�}14�j �y�ۑ�z �d�݂œ��_�p�̖_�����������Ă��܂��C �����O�i���Z�A�C�e���j�������Ă������Ă��܂����B �y������i�z ��N�����g���Ă����Z�p�E�ƒ�Ȃ̋��ނ� �V���b�^�[�̃p�[�c���g���C����������Ƃ߂��B ����ɂ�胊���O�̒E����h�����B
�y���́z�u�v���_���܂��B��̓X�^�C���t�H�[���v�i�}15�j �y�ۑ�z �y�ʉ���}��C�X�^�C���t�H�[�����g�p�����Ƃ���C �����O�i���Z�A�C�e���j���������Ƃ��ɂ��Ȃ�C ���ꂻ���ɂȂ�C�����O�i���Z�A�C�e���j�� ���肨���Ă��܂����B �y������i�z �v���X�`�b�N����ځ[����܂����C�⋭�B �y�ʉ���ۂ������O�i���Z�A�C�e���j�������Ă� ���Ȃ炸��v�ɂȂ����B
�y���́z�u������t�g�v�i�}16�j �y�ۑ�z �������Ń����O�i���Z�A�C�e���j���Ƃꂽ��C ���_���ł��Ȃ����ƁB����ƍ����s�� �y������i�z �O�^�C���ɒ��ˊ�����t���C �����������C������₤�B ���̂R�_�̐\�������ɂ͋��ʓ_������B���̋��ʓ_�Ƃ́C���m�ȉۑ肪���邱�Ƃł���C���̉ۑ�͈�x���삵�I���Ă��甭���������̂ł���Ƃ������ƁB���������ŗ\�肵�Ă�������͏I���������C�v���悤�ɓ��삵�Ȃ��Ƃ��������ɒ��ʂ��C���Ƃ������������ۑ肪���������B�����Ń`�[���ŃA�C�f�B�A���o�������C�~�[�e�B���O���d�ˁC���S��Ƃ��C�ۑ���������邱�Ƃ��ł����̂ł���B �@�P�P���P�X���̒��쌧���ɂ͂P�W�S�`�[���̂����̂P�`�[���Ƃ��ē��X�ƎQ�������B�����������Q�����邱�Ƃ��y���ނƓ����ɁC���`�[���̃��{�b�g�ɍ����S�������Č��w���Ă����B �@�܂Ƃ߂̊w�K�Ƃ��āC��iDB�ւ̓��e���s�����B �i�}17�C18�j
�@����Jr���{�R���EJr�������x�Ɏ��g�݁C�\�����o�����邱�ƂŁC�����ւ̊S�����߁C���̐l�̃A�C�f�B�A�d����ԓx���琬���ꂽ�B�܂��C���ԂƋ��͂��ĉۑ����������͂��琬���C���̂Â����{�b�g����ւ̊S��ӗ~�����߂邱�Ƃ��ł����B �@�����̃L�b�J�P�ƂȂ�ۑ�̔����́C���k�����̗\��ɂ�鐻�삪�I��������ɐݒ肳���Ƃ������Ƃ����̃`�[�����玦�����ꂽ�B���ۂ̐���O�̍\�z���Ă���Ƃ��̃A�C�f�B�A������������̂͑�ϓ�����Ƃƍl������B���̃`�[���͐����̉ۑ�����������\���Ɍ��т������C�\�z������̃A�C�f�B�A���\���Ɍ��т��ꍇ������B���ꂼ��̃`�[���ɓK�����ۑ�ݒ�ӏ����x������K�v������B���k�̊��z���Љ��B
�@�S�D�R�@�������̓o�^�̒����@ �@����17�N�x�̍Z�������\������\�S�Ɏ������B�����\����77���B��������������u���F�v���ꂽ���̂�69���ł���C�ł�����������\�����ĔF���ꂽ�`�[����5���i2�`�[���j�ł������B�{�N�x�́u����Jr���{�R���������v�������h���ɐݒu�����B���k�̃A�C�f�B�A��Web��ʂ��ĕ���17�N4�����烍���h�����{�l�w�Z�ɋΖ����Ă���O�N�x���H�ҋ��t�ɑ����C�����X���ԁC�����ɂ��ĂP���L�����Ē��w���̃A�C�f�B�A�͐R���E���F���ꂽ�B �������ꂽ����Ɏ����B�̃A�C�f�B�A���������ꂽ����ɐ��m�ɓ`���邽�߁C�]���̃C���X�g��v�}�ɉ����C�f�B�W�^���J�����⓮�����g���āu����ɓ`����v�H�v�ƂƂ��ɁC�����Ǝ��Ԃ��z����l�b�g�̗����𒆊w���͎��̌��Ƃ��Ċw�Ԃ��ƂƂȂ����B�A�C�f�B�A�𐳊m�ɓ`���邽�߂ɖ{�N�̐\�����݂�Ɓu�f�B�W�^���J�����v�ŎB�e���ꂽ���̂������i55���j�C����O�̃A�C�f�B�A�X�P�b�`��v�}�ɂ��\���i14���j���͂邩�ɏ��鐔���ƂȂ����BJr�������x���{�i�I�Ɏn�������̂��x���������Ƃ����邪�C��Ԃ̗��R�͉������ꂽ�����h���ɂ�����������m�ɃA�C�f�B�A��`���邽�߁C�����ĊȒP�ɓ`���邽�߂ɂ��C�C���X�g��v�}���f�W�J���ŎB�e�����Î~�悪�m�����낤�Ɛ��k�͍l�����悤�ł���B�m���ɁC���m�ɓ`���邽�߁C�X�s�[�h���d������Ɗ����������̂��f�B�W�^���J�����ŎB�e�����Î~��⓮�悪�K���Ă���Ǝv����B�������C�A�C�f�B�A��������邽�߂ɂ��C���Ȃ��Ƃ��`�[�����ł̈ӎv�a�ʂ��K�v�ɂȂ��Ă���B���̐��ɂȂ����̂�n�肾�����߂ɂ́C���t��}�œ`���邱�Ƃ��K�v�ł���C�u���̐��ɂȂ����̂�`����́v�͍���̏d�v�ȃL�[���[�h�ƂȂ��Ă���ł��낤�B���̂��߂ɂ��CJr�������x�����p���Ă������Ƃ́u�A�C�f�B�A��`����́v�̈琬�ɂȂ���ł��낤�B �@�ȏ�̂��Ƃ���CJr����DBVer2�����H�̒��Ŋ��p���邱�Ƃ��ł����B �@��iDB�ɂ��ẮC���߂Ă̎��g�݂��������Ƃ�����C�U���̓o�^�݂̂ɗ��܂����B����͍�iDB�̊��p���ۑ�ł���B �\�S ����17�N�x�̍Z�������\����
�@�S�D�S�@���k�̒����@ �@�S�D�S�D�P�@�����Ώۂƒ����@ �@Jr�������H�Z�̗��C���k��ΏۂɎ��⎆�����������Ȃ��CJr�������H�̋���I���ʂƉۑ�ɂ��Ă����炩�ɂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��C���{�b�g����w�K��Jr�������H�������Ȃ������쌧�ɂ����āC����17�N�x�̌����ɎQ���������k��ΏۂɃq�A�����O���������{�����B����17�N11��19���ɊJ�Â��ꂽ��4�쌧���w�����{�b�g�R���e�X�g���ɂ����āC���Q�����k��ΏۂɃq�A�����O���������{�����B����͂`�D��{���C�a�D���H���C�b�D�ӌ��̂R�_�ɂ��č쐬�����B���H���̒��ł́C�m�I���Y�w�K�ň琬�ł���ƍl�������p�̎��H�͂���Љ�ɎQ�悷��ԓx�Ɋ֘A�������⍀�ڂ�ݒ肵���B �@�S�D�S�D�Q�@�������ʂƍl�@�@ �@13�Z30��������B��{����\�T�C�U�C�V�Ɏ������B�����\����77%�̐��k���ł��Ă����B�\���ł��Ȃ��������R�͎��Ԃ̖����ł������B�܂�����DB�ɂ��Ă������ȏ�̐��k���g�p�o���������Ă����B�L�т����o�������ڂ�\�W�Ɏ������B�u���`�[���⑼�Z�̓������Q�l�ɂȂ����v�ɂ���56%�̐��k���m��I�ȕ]�������Ă����B�u�����̎��g�݂͖ʔ��������v�ɂ��Ă�82%�̐��k���m��I�ȕ]���ł������B�u�����̓����ɋ������������v�u�����̓����̎d�g�݂����������v�ɂ��Ă͂��ꂼ��65%�ȏ�̐��k���m��I�ȕ]�������Ă����B�u�����̑�����������v�ɂ����Ă�91%�̐��k���m��I�ȕ]�������Ă����B �@��i�I�ƍl�����Ă��钷�쌧�̐��k��Ώۂɒ������s�����B���쌧���w�����{�b�g�R���e�X�g�����ɏo�ꂵ�Ă������k�ł��邽�߂ɁC�ǂ̍��ڂ��m��I�ȕ]���邱�Ƃ��ł��C�m�I���Y�̎d�g�݂�d�v���𗝉��ł����Ƃ�����B �����Z�œ����������L���C�����̏�ł��݂��Ɍ�������悤�Ȏ��H��ςݏd�˂Ă������Ƃ̋���I�Ȍ��ʂ������Ă���ƍl������B���ʁC�}�╶�͂ŕ\�����邱�Ƃɂ��ẮC�Ⴂ���ʂł��������Ƃ�����C�ۑ肪�c�����B
�@�S�D�T�@���t�̒����@ �@�S�D�T�D�P�@�����Ώۂƒ����@ �@Jr�������H���s���Ă��钷�쌧�̋�����ΏۂɎ��⎆�����������Ȃ��C�������H�̎��g�݂̏Ɖۑ�ɂ��Ă����炩�ɂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��C�������s�����B���쌧���w�����{�b�g�R���e�X�g���ɎQ�������w��������Ώۂɒ������˗����C����17�N11��19-20���̊ԂɎ��{�����B �@�����́C���⎆��z�z���ċL�����Ă��炢�C������яI����ɉ���������B����͂`�D��{���C�a�D���H���C�b�D�ӌ��̂R�_�ɂ��Ď��⍀�ڂ��쐬�����B�܂����H���̒��ł́C�m�I���Y�w�K�ň琬�ł���ƍl�������p�̎��H�͂���Љ�ɎQ�悷��ԓx�Ɋ֘A�������⍀�ڂ�ݒ肵���B �@Jr�������H�̌��ʂɂ��ẮCJr�������H�ɂ���ē����������L���邱�Ƃɂ��C���Z����̃A�C�f�B�A���h���ɂȂ�����C���̓��������Q�Ƃ��邱�ƂŁC�A�C�f�B�A���[�����ꂽ�肷����ʂ�����ƍl�����Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B���k�̕ϗe�����Jr�����̎��H�ɂ��C�����̏d�v���ɋC��������C�J���Ɉӗ~���킢���C�����������݂���悤�ɂȂ�����ƍH�v�ݏo�����Ƃ���p�����o�Ă������Ƃ͕]���ł���ł��낤�B �@�S�D�T�D�Q�@�������ʂƍl�@�@ �@15��������i�L����15�j�B10���͖{�N�x���߂Ă܂��͂Q�N�ڂ̎w�����ł�����(�\�X)�B�w�����Ԃ͂R�N���̑I�����W���Ɣ������߂��B�܂��������ŁC���邢�͑I�����Ƃƕ������łƂ������g�݂��V�Z�ł������B�K�C���Ƃł͎��H����Ă��Ȃ�����(�\10)�B �@Jr�������x�̏Љ��11�Z���s���Ă����B���������͏����܂��͐���̊J�n���V�Z�Ɣ����ł�����(�\11�C12)�B�����̓������x�̐����ɂ��Ă͔����ȏ�̂W�Z�͍s���Ă��Ȃ������B�o�萶�k�͂T�Z�ł�����(�\13�C14�j�B�o��ł��Ȃ��������R�ōł����������̂́C����ɒǂ�ꎞ�ԓI�ȗ]�T���Ȃ��������Ƃ��W�Z���グ�Ă����B�܂��w���m�E�n�E�̕s���ɂ��Ă��R�Z���グ�Ă���(�\15)�BJr�����f�[�^�x�[�X�͔����̂W�Z�Ő��k���g�p���Ă���(�\16)�B �@Jr�������H�̌��ʂɂ��Ă�14�Z�ƂقƂ�ǂ��m��I�ȕ]���ł�����(�\17)�B���̗��R�Ƃ��đ��Z�̓������h���ɂȂ������Ƃ�A�C�f�B�A�̐[���C�ӗ~�C�F�߂��邱�Ƃւ̎��M�Ȃǂ��������Ă���(�\18)�B�܂��������̋��L�ɂ��Ă�14�Z���m��I�ȕ]���ł�����(�\19)�B���R�ł��n�ӍH�v�̐L���⑼�Z����̎h�����������Ă���(�\20)�B�܂��u �������g���̂Ɏ葱�����K�v�Ȃ̂ŁA�ӎ������܂�v�u �m������邾���łȂ��A�L�ߐ[�߂��i�ł��邱�Ƃ�̌��ł���v�Ƃ��������ʂ��グ���Ă����B �@�����̓����̗�����13�Z�ƍm��I�ȕ]�����唼���߂����C���Ȃ�𗧂Ɠ�����������4���ɗ��܂���(�\21)�B���k�̕ϗe�ł͓����̏d�v�����R���C�J���ւ̈ӗ~���Q���ł�����(�\22)�B �@���z��v�]�̎��R�L�q�ł́u�{�N�x�͂ł��Ȃ����������N�͐���Q���������v�u�ƂĂ��ǂ����x�v�Ƃ������m��I�Ȉӌ������������B���ʁu�����Ǝ��p�V�Ă̋�ʂ������Ȃ�C�������Ƀ��x�������ł����v�u�ʐ^�ł̕\����������ɂ����v�Ƃ������ӌ�����ꂽ�B �@�ȏ�̂��Ƃ���C�^�p��\���ɉۑ�͎c�������C�{�V�X�e�������p�����m�I���Y�̊w�K�́C�{�����ňӐ}���Ă�����p�̎��H�͂���Љ�ɎQ�悷��ԓx�̈琬�ɗL���ł���Ƒ����̋��t�������Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�T�D�@�܂Ƃ� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�{�����́C�Z�������f�[�^�x�[�X�����ɂ����m�I���Y�w�K�������ʓI�ɍs�����߂ɁC�Z�������f�[�^�x�[�X�̉��ǂƍ�i�f�[�^�x�[�X�̊J���y�т��̋�����ʂ̌���ړI�Ƃ����B���H�̕��͂̌��ʁC�ȉ��̂��Ƃ����炩�ɂȂ����B �i�P�j�ړI�Ƃ����Z�������f�[�^�x�[�X�̉��ǂƍ�i�f�[�^�x�[�X�̊J�����ł����B �i�Q�j���k�ɂ�钲���̌��ʁC�n�ӍH�v����͂�A�C�f�B�A�d���邱�ƂȂǁC�m�I���Y�Ɋւ�镔���ł͐L�т��F�߂�ꂽ���C�A�C�f�B�A��\������͂ɂ��Ă͉ۑ肪�c�����B ����́C���ł̓o�^���ꂽ�����������ɁC����c�a���\�z���C�w�K�̂܂Ƃ߂Ƃ��Ċe�w�Z�œo�^�����Ă����B���k�B�̕ϗe�����O�C�r���C����̒����ŕ��͂��Ă����B�܂��A�C�f�B�A�̕\���͌���ɂ��Ă�������[�߂Ă����\��ł��� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�I���� |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�{������i�߂�ɓ�����C ���c�@�l�@�㌎�X�|�[�c�E������c���܂̑�12���㌎��猤���������܂������Ƃ� �[������\���グ�܂��B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
���p�����@�Q�l���� 1)�X���O�F���{�R�����m�̂��̍��V�_,�I�[���ЁC pp.154-200,(1999)�D 2)�����_�K�F���k�B�̃v���W�F�N�g�w�|�`�[���w�K�Ŏ��g���{�R���|�C ��17������ܓ��I�_���W�`����(���Ȏw���E�w�Z�o�c����)�E���w�Z,pp.30-27�C(2001)�D 3)�m�I���Y������ҁF�n�ӍH�v�̈琬�ƕ]���\Jr�������H�̋��t�p��������\�C �O�d��w����w�������������C(2006)�D 4)������F������\�ҁC����15�N�x�������,��w����w�������m�I���Y���猤���������C pp.4.1.�@1-1-4.1.7-6,(2003)�D 5)���쌧Jr���{�b�g�R���e�X�g���s�ψ�����ǁC ����16�N�x���쌧���w�Z���{�b�g�R���e�X�g���v��,(2004)�D �E���쌧2004�N��Jr�����W�@ ���쌧�Z�p�E�ƒ�ȋ��猤���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���쌧���w�����{�b�g�R���e�X�g������ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�d��w����w���Z�p����u���@���������� �E���쌧���w�����{�R�������ǃz�[���y�[�W�@http://www.n-robo.com/ �E���샍�{�R��Jr�����f�[�^�x�[�X�@http://www.n-robo.com/tokkyo/pub/index.php �E���샍�{�R��Jr��i�f�[�^�x�[�X�@http://www.n-robo.com/sakuhin/pub/ �E�����������i�Z��������in NAGANO�j�@http://www.n-robo.com/kcn/index.html �֘A�_���@�w��\ 1)�����_�K�E�������E�y�c�����E��_�@���C �u�Z�������f�[�^�x�[�X��p�����Z���������x�̉^�p�ƕ]���v�C ���{����H�w���20��N��C2004 2)�����_�K���_�@����y�c�����C �u���w�����{�b�g�R���e�X�g�ɂ�����Z�������f�[�^�x�[�X�V�X�e���̊J���v�C ���{�Y�ƋZ�p����w���S�V��u���u���v�|�W�Cpp48�C2004 3)�����_�K�E�y�c�����E��_���C �u���w�Z���{�b�g�R���e�X�g�ɂ�����Jr�����f�[�^�x�[�X�V�X�e���̊J���v�C ���{�Y�ƋZ�p����w���47��4��,pp281-287,2005 4)�����_�K�������y�c�������_�@���C �uJr�����f�[�^�x�[�X��p����Jr�������x�̌��ʓI�^�p�@�̌����v�C ���{�Y�ƋZ�p����w���S�W��u���u���v�|�W�Cpp3�C2005 ���{�ꏊ ���쌧�W���w�Z�i��Ɍ������w�Z�j ���S�� �牮���F�i �@�@�@�і�q�s�i ���@���l�i���쌧����ӊw�Z�E���@�j�@�@�@�@���c�l��i ���d���i �c����N�i �с@�F��i �����k�i |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2006 Team N-robo All RightsReserved