小学校におけるe‐learningの推進
一人一台の情報端末とWBTの活用
― 新たなコミュニケーションの導入で見えてきた可能性と課題 ―
追手門学院小学校 教育工学部
代表 竹内 豊一
要約
本校ではWebをベースにした学校教育の情報化の研究・実践に取り組んでいる。
今回の提案では、学校全体で情報化に取り組む中でのe-learningの位置付けや求める効果を明らかにした上で、e-learningの実践で見えた成果や課題を事例とともに紹介する。
具体的には、小学校4年生の児童(4年ろ組 39人)がWBT(WebCT)と個人情報端末(シグマリオンⅢ)を半年ほど利用して、「感想文を書く」、「計算問題をする」、「時間割や宿題を確認する」といった今までの学習や学校生活と同じことに取り組んだが、情報化を進めたことで今までにない効果と可能性を実感することが出来た。また、情報化といえば冷たいイメージを持つ方も多いが、今まで以上に人間のあたたかみを感じることのできる新しいコミュニケーションの形でもあった。そして、何よりも大きな収穫は、理想として求めていた「児童一人一人が情報端末を道具として使いこなす」という義務教育(K12)でのより高度な情報化が不可能ではなく、実現できるという手ごたえを感じたことである。
ただ、新しい取り組みだけに課題も少なくなかったが、大切なのはそれを机上で空想するだけでなく、実践の中で明らかにし解決していくこととも考える。
この実践により、情報化社会がよりよく発展していくためには小学校教育の情報化は可能かつ必要であるとの考えをさらに深め、義務教育の情報化が世界をリードする日本独自の高度なe-learningを開拓する原動力となり、激動する情報化社会を支える基盤になることを確信するに至った。
勤務先 追手門学院小学校 大阪府大阪市中央区大手前1-3-20
![]()
小学校におけるe‐learningの推進
一人一台の情報端末とWBTの活用
― 新たなコミュニケーションの導入で見えてきた可能性と課題 ―
追手門学院小学校 教育工学部
代表 竹内 豊一
要約
目次
はじめに 研究の背景にあるもの
1.本校で目指す「教育の情報化」 3つの柱
(1)教職員間の情報化
(2)学校と家庭間での情報化(危機管理)
(3)授業の情報化
2.e-learningの位置付け
(1)今までの取り組み
(2)授業での取り組み
(3)今回の実証実験について
3.実証実験について求めた効果
(1)「情報の共有」について
(2)「情報の処理」について
(3)コミュニケーションの向上
4.実践事例と考察
(1)「情報の共有」 掲示板機能の活用
①国語での実践1 「詩」の発表について
②国語での実践2 「ごんぎつね」初発の感想について
③理科での実践 「冬の星」の調べ学習について
(2)「情報の処理」 テスト機能の活用
①算数での実践 「小数のかけ算」計算練習について
(3)「コミュニケーションの向上」 メール機能 テスト機能 掲示板機能 スケジュール機能の活用
①長期欠席児童に対しての実践
②プロジェクト企画(クリスマス会)の実践
5.まとめ
実証実験から日常活用へのステップ 今後の課題
6.さいごに
はじめに 研究の背景にあるもの
本格的にパソコンを導入したのが平成9年度からであるが、そのころはTV電話を使ったプロジェクト型の授業が注目された頃で、本校も多くのプロジェクトに参加した。中でも、DTMを使った音楽の交流授業は、NHK教育テレビでも取り上げられ、成果を出すことができた。
しかし、成果を出せば出すほど教員間の温度差が開く感があり、児童に対しても参加できる、できないという不公平な部分が気になった。教育活動として定着させるためにはどの児童も平等に機会が与えられなければならず、どの教員も同じ指導力を持たなければならない。その点で、プロジェクト型の情報教育には行き詰まりを感じだした。
同時にその頃はハード面の低価格化が進んできた頃でもあり、それまでのようにハード面の環境を整えるだけで注目される時代は終わり、今後現場に求められるのは、ハードではなく指導力だとも感じ出した。
当時は、教員が「情報の授業」を指導することがパソコンに対するスキルアップにつながると考えていたが、教師の日常業務には必要がなく、負担ばかり増えるようにも感じられた。教員にとって必要なものは何か、教員に求められる指導力とは何かを考えはじめたのもこの頃であった。
また、児童がパソコンを使う「情報の時間」が1学期に4~5時間だったのをさらに週に1時間と一歩進めたところ、コンピュータ教室の空き時間がなくなり、今までのように音楽などの他教科で自由にコンピュータが使えなくなった。
情報化が進めば進むほどパソコンが使えなくなるという矛盾する問題をクリアするために、おぼろげながら個人端末を背景にした教育の情報化を考えるようになった。
「教師の統一された価値観と指導力」「理想的な環境」の問題解決を模索したことが、現在取り組んでいる「教育の情報化」「児童の個人端末の活用」を目指すに至った背景である。
1. 本校 で目指す「教育の情報化」 3つの柱
現在、効果的に情報化を進めるため、情報化の対象を3つに分けて取り組んでいる。
(1)教職員間の情報化
 日常業務の連絡や会議を情報化することで、学校全体の意識と技術を高いレベルで均一化することに取り組んでいる。現在、月例の職員会議では教員全員がグループウェアとノート型パソコンを利用し、ファイルを共有することでペーパーレス会議を実施するまで意識と技術は向上した。
日常業務の連絡や会議を情報化することで、学校全体の意識と技術を高いレベルで均一化することに取り組んでいる。現在、月例の職員会議では教員全員がグループウェアとノート型パソコンを利用し、ファイルを共有することでペーパーレス会議を実施するまで意識と技術は向上した。
今後は、個人情報保護と情報環境の向上をめざし、Thin Client Systemの効果的な活用とWindowsのシステムとの効果的な融合を目指している。
図1 職員会議の様子
 (2)学校と家庭間での情報化(危機管理)
(2)学校と家庭間での情報化(危機管理)
各家庭との連絡手段としてASPで情報を提供し、保護者はパソコンや携帯電話を使って利用している。緊急連絡をメールで一斉配信したり学年通信や学級通信を添付ファイルとして提供したりしている。現在は、1年から6年までの全学級で利用するに至った。
また今後は、アルバム機能を使ってクラスの様子や学校の様子を関係者だけに写真を提供することや、同じ機能を利用して図工や習字の作品展を開催することも考えている。学校から配布されるプリントも、将来は添付で送ることも考え、ここでもペーパーレスを目指している。
他にもICタグを利用した登下校情報の提供も実証実験中である。
図2 利用しているASPのTOPページ
(3)授業の情報化
(3-1)情報の時間
1年生から4年生まで、週に1時間「情報の時間」を設定し、技術やモラルを以下の内容で学習している。
各学年の学習概要

1年生 基本的な操作活動
2年生 グラフィックスの基本操作(GIMP)
3年生 ワープロ、プレゼンソフトの活用
4年生 ネチケット、e-learningの基本学習
5・6年生では、1から4年生で学習した技術などを
ベースに、教科学習の中でパソコンを鉛筆やノート
のような道具のひとつとして活用することを目指して
いる。
2年生のCG作品。レイヤーやフィルターを使っている
(3-2)デジタルコンテンツの活用
教師には、一人一台ノート型パソコンがあり、各教室も無線LANの環境がある。この環境を利用して授業中に、デジタルコンテンツを活用することによって授業効果が上がると考え、実践研究を推進している。
ただ、プロジェクターは各教室にまだ常設されていないため日常的な活用にまで至っていない。
2.e-learningの位置付け
(1)今までの取り組み
平成14年の9月からWebCTを導入したが、その前に研修ということで夏休みに基本操作の講習を10人で2日間受けた。その後の2日間で、テスト機能を利用して「九九の学習」というコンテンツを作成した。「実施時間の設定」や「問題をランダムに選んで出題する」「テストに合格すれば次の段が表示される」といった随分充実したコンテンツが完成した。その手ごたえを社会科の先生に話をして、社会科でも「都道府県名」のコンテンツを作ることになった。フリーの日本地図の画像を取り込み、赤い線を引いて数字を打ち込んだりして手作りのコンテンツを作成した。一度作れば手順もわかり、「都道府県名」とどまらず、わずか2日間で「半島・岬」など11の分野のテストコンテンツを作った。
2学期から教室で活用されることを考えて、児童900人近くの全員のIDとPASSを発行し、各教員に講習会と簡単なマニュアルを配布した。しかし、結果としては全然使われず、広まらなかった。
考えられる理由としては、各教室が使える環境になっていなかったことが原因のように思った。パソコンは各教室に1台あるが、それを40人近くで使いまわすのは困難であった。
また、教師側にも利用する必要感や便利という実感がなく、 次第に遠のいていった。
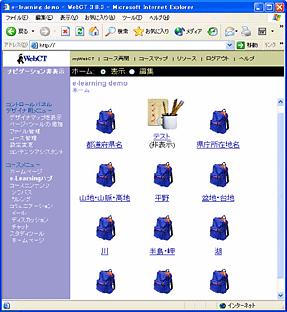
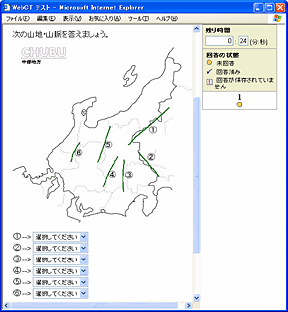
作成した社会のテストコンテンツ
(2)授業での取り組み
前回の反省から、日常の中で活用するためには使い慣れておくことが大切と考え平成15年度から「情報の時間」の4年生で基本操作を学習することに取り組んだ。WebCTは高等教育向けのWBTなので、使われている漢字や表記が難しいことはあったが、その点は使い慣れることでクリアできた。
まずは、「自己紹介用のホームページを作成する機能」を利用してホームページを作ってみた。大体のレイアウトはできているので文字を入力することで作成することはできたが、リンクを張るためにはタグを使わなければならず、指導者の工夫でグループごとのホームページが出来上がった。
また、メールを使っての伝言ゲームや掲示板を使ってのネチケットなど基本的な学習には有効であったが、学習の範囲を超えることはできず、日常のコミュニケーションツールにまで高めるためには、やはり教室に1台の環境では無理があった。
現在でも「情報の時間」に4年生でWBTの基本的なツールの学習をおこなっている。ログイン、ログアウト、掲示板、メール、スケジュール機能によるコミュニケーションやテスト機能を利用しての学習内容の定着などである。しかし、本来e-learningでめざすコース学習といった形にまでは取り組めていない。今回の報告では、一人一台の環境であるが、現状は児童向けの適当な個人端末がないことと利用できるコンテンツがまだ少ないことなどが理由で一人一台の情報端末の導入にまで至っていない。
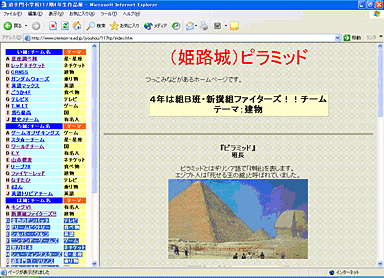
出来上がったホームページ http://www.otemon-e.ed.jp/jyouhou/117hp/index.htm
(3)今回の実証実験について
今回の実証実験が実現したのは、NTTドコモ関西が「小学校の教育にモバイル環境がどのように活用できるのか」実証したいというチャンスにめぐり合えたからだ。
本校が長年目指していた「一人一台の情報端末を活用する」ということが実現することになった。
以下の条件で行った実証実験が今回報告する事例である。
| 期間 | 平成15年10月から平成16年3月 |
| 対象児童 | 4年生(4年ろ組 男子23名 女子16名 合計39名) |
| 個人端末 | シグマリオンⅢ(OS Windows CE) 39台 |
| ネット環境 |
無線LAN(アクセスポイント2台) PHS接続(各家庭においてインターネットを利用するとき) |
| 利用ソフト | WebCT |


情報端末(シグマリオンⅢ)を配ったときの様子
3.実証実験について求めた効果
特に目新しいことを始めるのではなく、現在おこなっている授業をベースに個人端末を道具として導入することでの効果を狙った。具体的には、「情報の共有」「情報の処理」「コミュニケーションの向上」の効果に期待した。
(1)「情報の共有」について
例えば、国語の本を読んだ感想文について考えてみる。現在では、感想文を紹介するのには数人を指名して読ませたり、印刷して配布したり・・・・・。感想文という情報をクラス全体で共有するのは現在では困難だが、個人端末とグループウェアを導入すれば状況は変わる。掲示板に感想を書き込むことで、情報の共有化が実現できる。この今まで不可能であった「情報の共有」によりさまざまな効果が生まれると考えた。
(2)「情報の処理」について
本校の学力観は、基礎基本にとどまらす、いかに個人の能力を高めるかということを求めている。
今までにも高学年での専科制、ティームティーチング、6年生2学期からの受験校別クラス分けなど様々なことに取り組み、効果を上げてきた。さらに情報化を目指すことで個人レベルでの学習形態が可能になり、学習効果が向上すると考える。
例えば、テストについて考えてみる。
いうまでもなくテストで大切なことは点数ではなく、理解できているかどうかを確認し、学力を定着させることである。まちがったところ、わからなかったところを再度指導し、定着させるための労力と時間を確保することは、現場教員共通の悩みだとも考える。
しかし、WBTを導入し児童が個人端末を持てば状況はかわる。テストが終わった時点で採点でき、その場で指導することが可能になる。児童がわからない部分を自覚することは大切で、教師はすぐにピンポイントでその対応ができる。また、その後も個人のペースで学習が継続でき、その進行状況も知ることもできる。今までの環境では困難であったテストという情報のスピード処理が可能になり学習効果を上げることもできる。何よりも指導ではなくテストの処理に費やしていた教員の負担が減ることで、児童と触れ合う時間も増えれば、他の面での効果も期待できると考える。
(3)コミュニケーションの向上
児童には、e-learningのツールとして今までには提供されなかった「掲示板」、「チャット」、「メール」など新たなコミュニケーションツールが提供される。情報化というと何か冷たいイメージを持つ人も多いが、保護者との連絡で導入したASPを利用したときには、先生と保護者の距離が縮まったという感じを強く持った。というのは別に学級通信のように印刷しなくても,その日のことをちょっと掲示板に書き込むだけで何か反応があったりした。例えば,「ハリーポッターが出版されたら休み時間に何人の子供が読んでいました。」と書き込めば、家での様子を教えてくれたりと、学校の様子をちょっと紹介するだけで相手の様子がわかったりした。今回の実践でも、「児童同士の交流」「児童と教師の交流」に今までにないものが生まれると考えた。
4.実践事例と考察
実践紹介の前に、 対象が小学校4年生といったことで技術的な面での問題点にとらわれるかも知れないが、 子どもの能力はすごいもので環境さえ整えば技術的な問題は「やってみたい。」という自発的な心をエンジンに 自らのりこえていった。ローマ字入力についても、今までの「情報の時間」での学習した基礎があってのことと思うが、 個人端末を使う中でどんどん能力を伸ばして行った。お互いが教えあい、わずか10歳の子どもたちではあるがクラス 全員が技術的な問題(インターネットに接続する。LAN接続からPHS接続に切り替える。端末の画面設定や音の設定など) を乗り越えるのも5時間ほどの説明と2週間ほどの期間があれば充分のようであった。


休み時間の様子 はじめはアドレスを打ち込むのも一苦労
(1)「情報の共有」 掲示板機能の活用
①国語での実践1 「詩」の発表について
(①-1)掲示板より一部抜粋
--------------------------------------------
メッセージ番号806
投稿者: Y・Aさん (117148)(2004年1月15日木曜日午後2時11分)
件名 くも
すみきったそらに くもがぽっかりういている
とってもおおきなくもは くものおうさま入道雲
いまにもせかいをつつみそう もくもくふわふわ
さかなのうろこのうろこ雲 そらすいすいおよいでる
もくもくふわふわ
そらのうえでも いろんなくもがいきている
--------------------------------------------
メッセージ番号878[806番からのブランチ]
投稿者: N・Yさん (117135)(2004年1月15日木曜日午後2時52分)
件名 Re: くも
あ~、なんかこの詩を読むと、心が、和むな~(>~<) 気持ちを、雲になりきらせて読むと良い気持ちになるね! とっても良い詩でした!
(①-2)掲示板より一部抜粋
メッセージ番号801 投稿者: T・K君 (117051)(2004年1月15日木曜日午後2時02分)
件名 詩
やきゅうやってた
やっているうちに もめごとがおきた
きょうりょくして
もめていたことを かいけつしてみた
きょうりょくって やっぱりすごいな
--------------------------------------------
メッセージ番号822[801番からのブランチ]
投稿者: S・Tさん (117119)(2004年1月15日木曜日午後2時19分)
件名 Re: 詩 たしかにそうです
--------------------------------------------
メッセージ番号840[801番からのブランチ]
投稿者: W・N君 (117089)(2004年1月15日木曜日午後2時40分)
件名 Re: 詩 ほんとうだな
--------------------------------------------
メッセージ番号846[801番からのブランチ]
投稿者: Y・H君 (117087)(2004年1月15日木曜日午後2時43分)
件名 Re: 詩 僕も野きゅうがすきだよ
--------------------------------------------
メッセージ番号879[801番からのブランチ]
投稿者: T・K君(117051)(2004年1月15日木曜日午後2時52分)
件名 Re: 詩
自分で言うのもなんですが、これは、口語定型詩で書いています。
口語定型詩・・・今の言葉で書かれ、行ずつの音が同じの詩のことをいう。
--------------------------------------------
(①-1)掲示板より一部抜粋(①-2)掲示板より一部抜粋について
詩の発表だけにとどまらず、いたるところでこのような評価が始まっていた。今までの授業ならば考えられないことである。このように複数同時に評価が展開でき、他の児童も後からそのやり取りを確認できることは画期的なことである。
評価の態度も相手を認めた上での意見なので、みんなが積極的になってきている様子がうかがえる。
(①-3)掲示板より一部抜粋
--------------------------------------------
メッセージ番号802
投稿者: N・M君 (117057)(2004年1月15日木曜日午後2時03分)
件名 ラケット
テニスやバトミントンの ラケットは
使うほどぼろくなる
最初からあったおなかは
使うほど 張りかえられる
おなかが 強い選手ほど ゴージャスになる
強い選手に 売られるのが ラケットの望みだろう
--------------------------------------------
メッセージ番号849[802番からのブランチ]
投稿者: T・K君 (117051)(2004年1月15日木曜日午後2時44分)
件名 Re: ラケット 擬人法を使っているのは、すごくいいです。
--------------------------------------------
メッセージ番号853[802番からのブランチ]
投稿者: Y・H君 (117087)(2004年1月15日木曜日午後2時45分)
件名 Re: ラケット 僕のお母さんはテニスがうまいよ
--------------------------------------------
メッセージ番号865[802番からのブランチ]
投稿者: H・Y君 (117059)(2004年1月15日木曜日午後2時50分)
件名 Re: ラケット ラケットそのものがかいたよう
--------------------------------------------
メッセージ番号899[802番からのブランチ]
投稿者: A・K君 (117003)(2004年1月15日木曜日午後2時57分)
件名 Re: ラケット いい心もっていますねー
--------------------------------------------
(①-3)掲示板より一部抜粋について
メッセージ番号899のA・K君は、人前で発表するのが苦手であるが、このような形で参加できているのをみてうれしく思った。新しいコミュニケーションの出現は、やはり個人の可能性を広げるのにも有効な働きがあった。
①国語での実践1 「詩」の発表について 考察
ただ作るだけでなく、発表と評価ができ子どもたちも楽しみながら取り組めたようである。人前では発表が苦手な子どもが積極的に参加しているのを見て、新しい表現手段が増えたことで新しい活躍の場が出来た様に思った。
また、今までであれば、詩集や文集にまとめたりするのも、ノートをコピー機で複写したり、切り張りしたり、教師がワープロで打ちなおしたりとすごく労力がかかったが、やり取りの内容はテキストとして出力できるので、文集や資料に二次加工するのも今までとは比べ物にならないぐらい楽であった。余談になるが、学年末に作る文集の詩の作品を提出しなければならないときにインフルエンザにかかり休んでしまった。そこで自宅から、ネットで作品を選びメールで添付して締め切りに間に合った。これも今までなら出来なかったことである。
②国語での実践2 「ごんぎつね」初発の感想について
(②-1)掲示板より一部抜粋
--------------------------------------------
メッセージ番号75
投稿者: Y・Aさん (117148)(2004年2月3日火曜日午前10時08分)
件名 ごんぎつね
わたしが、ごんぎつねを読んで思ったかんそうは、ごんが兵十が「うなぎがたべたい、うなぎがたべたい」と言っているお母さんのためにはりきりあみを、もちだしてせっかくとったうなぎをごんが、かわのなかにもどしたのが、ひどいなぁとおもいました。でも、ごんは反省して兵十のいえにいわし・くり・まつたけなどを、もっていってあげたのが、えらいなぁとおもいました。
--------------------------------------------
メッセージ番号78
投稿者: K・R君 (117028)(2004年2月3日火曜日午前10時08分)
件名 「ごんぎつね」を読んで
この「ごんぎつね」というお話は、すごく悲しいお話です。なぜかというと、ごんは、兵十のおっかあに食べさせてあげる太い鰻を、勝手に食べてしまったおかげで、兵十のおっかあは死んでしまったのですけど、毎日、他界に行ったおっかあを寂しがる兵十のために、栗やまつたけを持っていってあげたのに、ごんは兵十に勘違いされて殺されてしまったお話です。ごんは最初はいたずらばかりする、悪いきつねでした。だけど、兵十と自分の気持ちがわかったのか、ごんは、とってもいいきつねになっていました。特に感動した場面は、兵十のおっかあの葬式の時、六地蔵の後ろに隠れていたごんが、おっかあの葬式だとわかって、自分のして行為を反省し、改めて心を変えたというところでした。
--------------------------------------------
メッセージ番号79
投稿者:S・S君 (117033)(2004年2月3日火曜日午前10時08分)
件名 [ごんぎつね」を読んで
ごんは、最初は、悪いことばっかりしていたけど、自分がやった罪を自覚しているのは、えらいなと思ったけれど、兵十に、償ったといっても、鰯屋さんからぬすんだのがわるいとおもいました。
--------------------------------------------
メッセージ番号105[79番からのブランチ]
投稿者: H・K君 (117066)(2004年2月3日火曜日午前10時17分)
件名 Re: [ごんぎつね」を読んでオレも同じいけんや。
--------------------------------------------
メッセージ番号127[79番からのブランチ]
投稿者: S・S君 (117033)(2004年2月3日火曜日午前10時22分)
件名 [ごんぎつね」を読んで 『続き』
兵十が、かすりきずがついていたのを見て、しまったと思って、毎日、どんぐりや、まつぼっくりをおいていったのに、兵十が、火縄銃で、打ってしまったのがかわいそうです。
--------------------------------------------
メッセージ番号80
投稿者: Y・Nさん (117153)(2004年2月3日火曜日午前10時08分)
件名 「ごんぎつね」
「ごんぎつね」の感想文
私は最初この「ごん」は、最初はいたずらが好きな悪いこぎつねだなぁと思いました。
でも読んでいくと自分がいたずらをして悪かったなぁと思ったことはなにかでつぐなって、本当はいいきつねなのかなぁと思いました。
でも兵十はこのごんが魚をにがしてしまってそのつぐないにくりやまつたけを置いているのを間違って、なにかまたいたずらをしにきたのかと思いごんを火縄銃でうってしまったのがかわいそうだなぁと思いました。
--------------------------------------------
メッセージ番号81
投稿者: H・Y君 (117063)(2004年2月3日火曜日午前10時08分)
件名 ごんぎつねのやさしさ
ぼくは、最初の方だけ見ていると「なんて悪いきつねなんだ」とごんがとても悪いように思いました。
しかし、それはちがいました。ごんは兵十のうなぎを盗んでしまいそのせいで兵十のお母さんが死んでしまった時につぐないとして毎日くりや、まつたけをどっさり持っていきました。 「ごんにもやさしいところがあるんだな」と思いました。
--------------------------------------------
(②-1)掲示板より一部抜粋について
端末を渡したのが10月末で冬休みも間にはさんでいるので実質2ヶ月ぐらいの実践でここまでしっかり書けるのかと感心した。環境が整えば、技術が身に付くのはあまり心配いらないと感じた。
また、ここではS・S君のメッセージ番号79メッセージ番号127に着目した。今までの授業では、教室全体の1つの大きな流れがあるので、個人レベルでの意見の変化などを随時発表することは出来ないに近かったが、彼のように個人レベルで意見が変わったり深まったりしたことなども主張できることが今までにない新たな可能性を秘めているように感じられた。
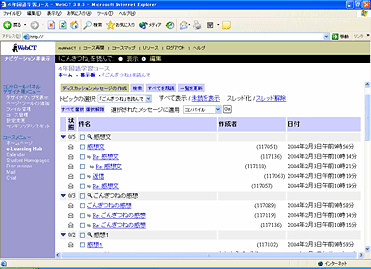
意見交換の様子
(②-2)掲示板より一部抜粋
--------------------------------------------
メッセージ番号73
投稿者: T・K君 (117051)(2004年2月3日火曜日午前10時07分)
件名 gongitsune no2
「ごんぎつね」は、愛知県のお話です。
ごんもいたずらには、「限度」あることを知ってほしい。僕は、兵十もごんもどちらも悪いと思う。
ごん・・・・・・いたずらをしなければよかった。
--------------------------------------------
メッセージ番号89[73番からのブランチ]
投稿者: S・Tさん (117119)(2004年2月3日火曜日午前10時11分)
件名 Re: gongitsune no2
1行目のこと・・・よくしってるんだなあーーー。へえーへえーへえー。
--------------------------------------------
メッセージ番号104[73番からのブランチ]
投稿者: H・Y君 (117059)(2004年2月3日火曜日午前10時17分)
件名 Re: gongitsune no2
で・で・でもつぐなった事は、認めてあげないと!
--------------------------------------------
メッセージ番号109[73番からのブランチ]
投稿者: W・N君 (117089)(2004年2月3日火曜日午前10時18分)
件名 Re: gongitsune no2
僕もそう思います
--------------------------------------------
(②-2)掲示板より一部抜粋について
以上のやり取りで感じたことは、今までのノートに書いていた文章とはずいぶん表記の仕方がちがうことである。教えたわけではないのに、よく言えばリラックスしているような感じを受ける。国語教育がこういった表現をどのように受け止めるのかは今後の大切な判断になるのではないかと考える。メールでは、絵文字やキャラクタを入れることで文章に微妙なニュアンスを加えることができるので独自の路線が認められているように思うが、学校教育では掲示板に対する記述に関してどのような指導が必要か考えなければならないように思う。
②国語での実践2 「ごんぎつね」初発の感想について 考察
今までの紙と鉛筆では、1時間の授業では書くだけで終わり、全員の友だちの意見を読むことは無理であったが、全員が意見を書き込み、意見交換まで始まっていたのには感心した。掲示板は意見交換には有効であり、これからの国語教育をも変える力があることを感じた。
③理科での実践 「冬の星」の調べ学習について
(③-1)掲示板より一部抜粋
------------------------------------------------------------
メッセージ番号5
投稿者: T・K君 (117051)(2004年2月17日火曜日午前11時31分)
件名 fuyunohoshi
2等星→1等星といくにつれて、明るさが2.5倍になる。
例えば、3等星から1等星は、6.25倍となる。
このアドレスが、冬の星座の
詳しいホームページのアドレスです。(調べてみてはいかが)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
メッセージ番号32
投稿者: S・K君 (117040)(2004年2月23日月曜日午前11時11分)
件名 冬の星について
こいぬ座は、紀元前3000年頃のギリシアで、いぬ座(おおいぬ座)より少し先に東の地平線に昇ることから、「犬の前に」という意味のプロキオンと呼ばれていました。中世のアラビアに伝わってから、こいぬ座と呼ばれるようになり、プロキオンは星の名前として呼ばれるようになりました。
------------------------------------------------------------
メッセージ番号33
投稿者: I・M君 (117010)(2004年2月23日月曜日午前11時11分)
件名 冬の星
キッズgooのキッズgooサーチで、冬の星<しぼりこんで>冬の星座で、星のお話の部屋というホームページなら結構良い話があります。
---------------------------------------------------------
(③-1)掲示板より一部抜粋について
今回は、抜粋したやり取りのように、文章などで紹介するだけでなく、アドレスや検索の仕方を紹介するといった今までにない発表が進んでいた。このような様子から、今後ますます教育におけるインターネットの著作権の問題は重要になってくるように思う。
③理科での実践 「冬の星」の調べ学習について 考察
掲示板上では、表面温度と色の関係、神話、冬の星座などいろいろな情報が提供されていた。
星座についてのコンテンツは充実しており、インターネットを利用した調べ学習は有効であった。以前、国語の意味調べでインターネットを利用してよかったのは 文字を文字で紹介するだけでなく、写真や音声など他の情報で理解できたのがよかった。やはり心配なのは、有害情報にアクセスすることであるが、検索サイトの指定やフィルタリングでカバーしたので、今回の取り組みでは特に問題はなかった。
(2)「情報の処理」 テスト機能の活用
①算数での実践 「小数のかけ算」計算練習について
当初は、この単元の学習中にテスト機能でつくったコンテンツを、授業後の確認小テストとして利用するつもりであった。しかし、テスト後に結果がすぐにわかる「自己採点の機能」がCE機であったため、うまくJAVAが動作せず、児童が自分の成績を知るための作業が複雑なものとなってしまった。そこで、この単元はこの機能になれるための計算練習として自主的に利用するということで扱った。
この実践の中には多くの有効な事例が見られるが、ここでは、ある女子児童に着目して、単元の中でどのようにテスト機能が利用されたのかを紹介する。この児童は、算数に苦手意識を持っており、そんなこともあってか宿題などの忘れ物も目立った。
(①-1) 1時間目の学習での利用の様子
単元の一番初めの授業時間の最後に小テストを実施させたのであるが、この児童の取り組みは、特に特徴があった。他の児童は多くても5回ぐらいしかやっていないのに、この児童はなんと24回も実施しているというデータが記録されていた。さらに、利用した時刻を追っていくと
1回目から3回目:
学校の授業でとりくむ 10月31日(金)
4回目:
学校から帰って、午後5時3分からはじめる。 10月31日(金)
5回目:
11月2日に家庭で実施 11月2日は日曜日である。
休日の昼からテストの続きをはじめたことがわかる。
(以下に5回目小テストのデータ一部抜粋)
| 2003年10月31日午後5時09分 | テストを開始 | 00時00分 | 05時00分 |
| 2003年10月31日午後5時09分 | 次の質問を保存: 1 | 00時12分 | 04時48分 |
| 2003年10月31日午後5時10分 | 次の質問を保存: 2 | 00時58分 | 04時02分 |
| 2003年10月31日午後5時10分 | 次の質問を保存: 3 | 01時15分 | 03時45分 |
| 2003年11月2日午後1時46分 | テストを再表示 | 44時37分11秒 | -44時32分11秒 |
| 2003年11月2日午後1時46分 | 次の質問を保存: 4 | 44時37分32秒 | -44時32分32秒 |
| 2003年11月2日午後1時46分 | 次の質問を保存: 5 | 44時37分43秒 | -44時32分43秒 |
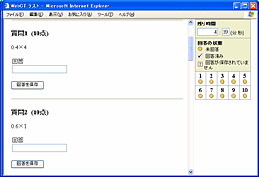
利用した小テスト問題例
(乱数を利用するので同じ問題にならない)
7回目:
11月3日(月)この日は、文化の日で休みであるが、やはり午後1時27分からはじめている。
8回目:
11月4日(火)この日は、学校から帰って、午後5時14分からはじめている。
以上のような感じで、1日にたくさんするのではなく、少しずつ24回も繰り返していたのである。成績も安定して100点を取っていた。宿題を忘れることが多い彼女が、これだけ繰り返し勉強していたことはうれしい反応であり、やはり「自分のペースでできる」など今までの環境とは違ったものがあってのことだ、とこの時は考えた。
(①-2) 単元途中での利用の様子
この単元では、前半は「小数×1けた」、後半は「小数×2けた」「小数×3けた」と進んでいく。
前半の「小数×1けた」では、全部で9回分の小テストを用意してあった。問題はどんどん難しくなるにもかかわらず、この児童は第4回から第9回の小テストをすべて1回で100点を取っていた。
それも詳しく調べてみると、第9回の小テストは11月3日の休日に合格していた。これは、 まだ学校で学習していない部分も先に進んで取り組んでいたことをあらわしている。
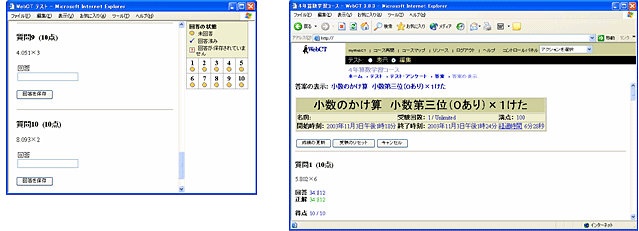
第9回のテスト内容とその結果
そこで不思議に思うのは、より難しいテストに合格しながら、なぜ何度も第1回目のテストを繰り返し受けていたのかということである。いままではなかなか取れなかった100点という評価を求めての取り組みであったのだろうか。
その後の取り組みを分析してみると、手順が複雑になる後半の「小数×2けた」になったとたんに状況は変わる。一度も練習しなくなっていたのだ。「小数×2けた」は、彼女にとっては難しかったのか、そのことに私は気が付かずフォローができなかった。授業が先に進む中、何度も第1回のテストを受けていた彼女の気持ちに近づけていなかった。彼女のやる気をもう一押ししてあげることができていれば、彼女は算数が好きになっていたかもしれない。そのことに気づいたのは、単元も終わって、このデータを分析してからである。授業を進行する中で、データを瞬時に分析し、児童の気持ちにまで近づける力を持ちたいと心から思った。
①算数での実践 「小数のかけ算」計算練習について 考察
テスト機能には、児童たちの取り組んださまざまなデータが蓄積される。それらのデータをうまく使いこなせば、効果的な指導ができるのであろうが、思った以上にデータ量も多く複雑で教師がデータを把握するのが困難であった。当たり前ではあるが、データには目的を持って向かわなければならないと考える。彼女の気持ちの変化についても、もっと早く気づけばよかったのにといまさらながら後悔する。このことは、単元が終わってデータをいろいろと分析する中ではじめて見えてきた。今までとは違った情報化の環境に対応できるデータ分析や活用能力が教師にも求められると感じた。しかし、今回の実践を通し、当初期待していた情報を自動的にすばやく処理するということだけでなく、いままでは漠然と感じていたことがデータとして分析できるのではと、学力の定着にとどまらずデータは気持ちの変化までも表現するといった可能性も感じた。うまく活用できれば、絶大な効果を発揮することは間違いないように思う。
(3)「コミュニケーションの向上」 メール機能 テスト機能 掲示板機能 スケジュール機能の活用
①長期欠席児童に対しての実践
実践をはじめた頃一人の児童が自宅のガラスで足の神経を切る怪我をし、1ヶ月ほど欠席することになった。その間、WebCTのいろいろな機能を使って子ども同士、また教師とその児童がコミュニケーションを図った。その実践を紹介する。
(①-1) メール機能の利用について
今回利用したメール機能は、グループ内のユーザー同士しかやり取りができない。児童がまったく知らない人にメールを送ることもできないので、あまり制限をかけないで自由に利用させた。まず、欠席児童の様子をクラスで話をし、メールを利用してお見舞いをしょうと呼びかけた。以下に、その内容の一部を紹介する。中には、学校に行ったときの友だちの様子に感謝して彼の父親がメールを送ったこともあった。
------------------------------------------------------------
メッセージ番号30
投稿者: H・Y (117059)(2003年10月29日水曜日午後2時57分)
件名 前、元気か.
M君、あんな、劇の練習で、俺、コールになってん、ほんまは、子供に、なりたかったんやけどなーーーーーーー。まあ、そんなことはいいねんけど......M君、ほんま、大丈夫か、いちおう、せんせいには、話、きいてんけど.... とにかくはやく、元気にこいよ。
------------------------------------------------------------
メッセージ番号49[30番からのブランチ]
送信先: H・Y (117059)(2003年11月1日土曜日午後6時06分)
件名 Re: 大丈夫。
元気やし足も大丈夫や。靱帯・腱・神経が切れてるけどな。
------------------------------------------------------------
11月12日に約1ヶ月ぶりに登校した。その後のメール
メッセージ番号120[30番からのブランチ]
送信先: H・Y (117059)(2003年11月16日日曜日午後8時29分)
件名 Re: お礼
Mの父です。 学校に行けるようになってMは喜んでいます。
Y君にはとても親切にしてもらっているようですね。
給食のお皿を運んでくださったそうですね。 ありがとう。
------------------------------------------------------------
メッセージ番号126[120番からのブランチ]
投稿者: H・Y (117059)(2003年11月19日水曜日午前10時45分)
件名 Re:M君のお父さんへ
いや、そんなたいしたことは.......まあそれはいいんですが、わざわざお礼をありがとうございます。
------------------------------------------------------------
(①-2) メール機能とテスト機能の利用について
テスト機能の成績をチェックしていると、まだ欠席していたM君の成績が記録されていた。私の方は、テスト機能の使い方どころかテスト機能があることも説明していなかったのだが、私の知らないところでこんなやり取りがあったようだ。
------------------------------------------------------------
メッセージ番号41
投稿者: K・R (117028)(2003年10月31日金曜日午後5時25分)
件名 メールのやり取り
M君、見たよ。あんがとさん。これから、メールのやり取りせえへんか?やるなら送ってね。
K・Rより
------------------------------------------------------------
メッセージ番号42[41番からのブランチ]
送信先: K・R (117028)(2003年10月31日金曜日午後8時15分)
件名 Re: メールのやり取り
もちろんやるよ。僕なお父さんの医院の奥の部屋にいてたから電波通じへんかってん。
メールサンキュー今見たとこやねん。で算数の問題のやり方はどうやったらええん。
------------------------------------------------------------
メッセージ番号45
投稿者: K・R (117028)(2003年11月1日土曜日午前10時28分)
件名 宿題のやり方
1.算数学習コースを開く 2.小数のかけ算を開く 3.目次で、数字4から7をノートに写しながら、問題を解いていく
4.(例)4が全部解けたならば、下に、答案を提出をクリックする
5.そのことを、4から7を全部やる
------------------------------------------------------------
メッセージ番号46[45番からのブランチ]
送信先: K・R (117028)(2003年11月1日土曜日午後5時51分)
件名 Re: 宿題のやり方
うーんなんとなくわかった。
------------------------------------------------------------
①長期欠席児童に対しての実践について 考察
子ども同士でメールの交換を行い、欠席している間のクラスの様子もよくわかったようで保護者も安心したようだ。一般的に、子どもがメールを使うことにはどちらかといえばよくないイメージがあるが、それは正しい使い方をきちんと指導する場所と機会が確保されていないからであり、正しい使い方をすれば技術は人にやさしいと実感した。また、教師の期待を超えてのやり取りの中で、欠席中の授業内容のテストを受けていたことには驚いた。想像の世界のなかにあった「e-learningの秘めた可能性」を体感した瞬間でもあった。
②プロジェクト企画(クリスマス会)の実践
(②-1)スケジュール機能の利用について
普段は、スケジュールの共有を利用して、毎日の時間割・宿題・持ち物などの情報をスケジュールに書き込んだ。子どもたちはそれを家庭でインターネットに接続して確認していた。今までは、自分でノートに写して毎日提出していたのだが、写さなくていいので子どもたちはその分遊べると大喜びだった。しかし、保護者の中には、自分で書き込むことが大切と考えて否定的な感想を持った方もいた。
2学期も終わりに近づいたある日、このスケジュールに次のような書き込みをした。
今日の秘密指令:
楽しいクリスマス会を考えるのだ!
掲示板の「クリスマス会」を利用せよ。 ただし、書き込みは夜の9時まで
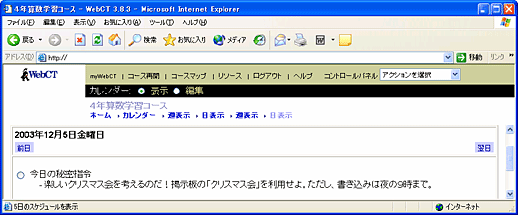
スケジュールに書き込まれた秘密指令
(②-2)掲示板機能の利用について
「クリスマス会」の掲示板より一部抜粋
メッセージ番号221
投稿者: Y・Aさん (117148)(2003年12月8日月曜日午前11時17分)
件名 クリスマス会について
私のクリスマス会についての意見は、ツリーのことです。
ツリーの飾りだけは、本物で木は、ダンボール・ペットボトルなどでつくります。
------------------------------------------------------------
メッセージ番号453[221番からのブランチ]
投稿者: K・Rさん (117110)(2003年12月10日水曜日午後7時10分)
件名 Re: クリスマス会について それいいね。
------------------------------------------------------------
メッセージ番号222
投稿者: W・N君 (117089)(2003年12月8日月曜日午前11時19分)
件名 新しいクリスマス会の意見 図書館でリサイクルの本をかりて家に持って帰って作ってくる
------------------------------------------------------------
メッセージ番号195
投稿者: S・Aさん (117118)(2003年12月6日土曜日午後12時18分)
件名 楽しいクリスマス会
みんなでできるゲーム(いすとりゲ-ム、オセロ、すごろく、漫才、工作・・・)をやりたい。
メッセージ番号196[195番からのブランチ]
投稿者: S・Tさん (117119)(2003年12月6日土曜日午後1時05分)
件名 Re: 楽しいクリスマス会 漫才は当然あの二人だよね。いいと思うな。
------------------------------------------------------------
メッセージ番号228[196番からのブランチ]
投稿者:I・Y君 (117006)(2003年12月8日月曜日午前11時22分)
件名 Re: 楽しいクリスマス会 なに~~~~~~~~!?勝手に決めるな!!!!!!!!!!
------------------------------------------------------------
メッセージ番号242[228番からのブランチ]
投稿者: K・R君 (117028)(2003年12月8日月曜日午前11時30分)
件名 Re: 楽しいクリスマス会 まぁ落ち着いて、落ち着いて=====
------------------------------------------------------------
メッセージ番号238
投稿者: I・Y君 (117006)(2003年12月8日月曜日午前11時29分)
件名 やっぱり・・・
やっぱり、S君と、漫才やろっかな~・・・・・・・・あ、決まったわけじゃないから!
------------------------------------------------------------
メッセージ番号239
投稿者: H・Y君 (117059)(2003年12月8日月曜日午前11時29分)
件名 ???より
今度のクリスマス会、みんなは、何をやりたいですか?僕は、ひげつけたりしたいなあ~^?^


グループごとの手作りクリスマスツリー 結局ひげをつけて漫才をした男の子
②プロジェクト企画(クリスマス会)の実践について 考察
本校は私学であるため、大阪、奈良、京都、兵庫と広い地域から子どもたちは通学している。そういったこともあり地域のかかわりよりも、学校での友達関係が中心となる。時間と場所を飛び越えて楽しく交流できているのは理屈ぬきでほほえましい。しかし、中には名前を偽ったり、調子に乗りすぎてふざけたメールを送ったりした子どももいたが、お互いの中で注意しあっていたことに子供の成長を感じた。思いやりや自己責任といった人間関係のマナーの本質は変わらないが、あたらしい技術に対する道徳観を早い時期に指導する必要性も感じた。
まとめ
今まで何年もかけて、「小学校における個人情報端末をベースにしたe-learning」の準備を進めてきた。少人数でのデスクトップを利用した事例はいくつかあったが、小学校での日本の一斉授業の形態にあったPDAやノート型パソコンでの事例は世界的にもほとんどなく、多くの人の意見ではNOであった。しかし、この実証実験を通して、小学校でも日本の授業形態に即したe-learningの展開は十分に可能であるとの手ごたえを感じることができた。何の保障もない信念を確信に変えることのできる取り組みであった。
実証実験から日常活用へのステップ 今後の課題
この実証実験を行った翌年度(平成16年度)、1クラスでの取り組みから5年生という学年全体への取り組みに展開しようと進めてきたが、今まで以上に現実的な問題にぶつかり、現在も実現はしていない。
大きな問題点としては以下の2点があった。
問題点1 児童用に適切な端末がない。
インターネットへの接続は、無線LANでカバーできるが電力の供給は無理である。そのため毎日持ち帰り充電しなければ利用できない。その点、シグマリオンⅢは、携帯にもすぐれ、少しぐらいのところから落としても壊れることはなかった。しかし、画面が小さいことと、利用したWebCTの画面のフォントサイズは変更できないこともあり、他の教員からも視力低下につながるのではと指摘されたこともある。また、現在は携帯電話の高機能化でCE機やPDAなどの機種が減少しており、シグマリオンⅢも現在は生産されていない。パソコンについては高価であり、小学生にとっての携帯性、堅牢性についても問題点は多いように思う。
問題点2 教員の共通認識に時間がかかる。
「導入後に利用できるコンテンツは充分か?また使いこなせるか?」「効果を保護者に納得させることはできるのか?」そういた声が導入を検討する会議の中で聞こえてきた。その背景には、やはり共通認識ができていなかったことがある。それまでにも、教職員に対して公開授業を4回、実技研修3回など行ったが、半年の取り組みの中では共通理解を得るまでには至らなかった。しかし、この問題は新しい取り組みの中ではいつも出会う問題であり、今までものりこえてきた。平成17年度中には、1年生から6年生までの算数の計算分野のコンテンツを作成し、児童が自主的に自分のペースで学習を進められる環境を作ろうと考えている。できれば、ツールの活用から総合的なコース学習にも高めてみたいと考えている。
さいごに
以前、ハワイの学校と共同研究したことがあり、その取り組みを発表するためにE-schoolといった研究会に参加したことがある。その共同研究でお世話になった先生に「パールハーバー」に連れて行って頂いた。日本の平和教育では、広島や長崎がよく取り上げられるが、ハワイの平和教育は「パールハーバー」なんだとそのとき初めて気がついた。求めるものは同じであっても、通る道のりはそれぞれがちがうことを実感した。今後世界はもっと身近になってくる。近づくことではじめてわかることがたくさんあり、世界には様々な価値観がある。それをうまく受け入れ糧とするためには、今まで以上に相手を思いやる柔軟な心が必要になってくる。素直で多感な時期に、自分の意見を主張し、多くの価値観に触れ、それを柔軟に受け入れる経験を積み重ねていくことが、世界の視野にたって考える人を育てることにつながるのではないかと考える。
時代は、インターネットを有効に活用することで、いつでもどこでも世界への扉を開けることができる。はやく子どもたちにも世界に羽ばたいて、世界中に友だちをたくさん作ってもらいたい。そういった思いが情報化を進める原動力である。