|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,はじめに | |
| 学校教育における大きな課題として,「生きる力」の育成が叫ばれている。「生きる力」として,厳選された基礎基本を着実に身につけさせるとともに,「自ら課題を見つけ,自ら学び,自ら考え,自主的に判断して行動し,よりよく問題を解決する資質や能力」を育てることが挙げられる。こうした「生きる力」を念頭に子どもたちの情報活用の能力を伸ばしていかなければならない。 | |
| 以上2点に加え,さらに情報活用の日常化を図るための取り組みをどう仕組んでいくのかを模索した。そこで,情報活用の能力をさらに伸ばすために,情報教育のカリキュラムにある「ホームページ作成」を工夫できないかと考えた。 | |
| ホームページは情報発信手段の一つとして広く活用されている。学校においてもホームページを使い,家庭・地域社会とのコミュニケーションを大切にしてきた。子どもの学習活動及び教育活動を公開したり,様々な方々からの意見や助言をいただいたりする中で「開かれた学校」「地域の拠点となる学校」を推進していくことをねらっている。また各教科や総合的な学習のまとめの一つの手段としてもホームページ等を使い,状況に応じた発信手段を選択できる基礎を培ってきた。家庭,地域社会に学校ホームページへの理解が高まり,それの持つ役割が伝わると,「子どもたちのメッセージを特集して欲しい。」「子どもの生の声が伝わるよう工夫して欲しい。」「子どもが取材した学校の様子を知りたい。」といった要望が多く出てくるようになった。また子どもたちからは,「先輩たちのように学校の楽しいことを伝えたい。」「わたしたちも自分たちで学校ニュースをつくりたい。」とアンケートで答えるようになってきた。このため家庭・地域や子どもたちの願いを汲み取り,本校情報教育の新しい第一歩を踏み出す必要性を感じた。 それは子どもたちが学校ホームページの企画,制作に関わるということである。出発時点から問題点も考えられた。「子どもたちにどの程度企画を任せられるのか。」「情報モラルの指導はおこなっているものの,実際の活動においてそれを生かすことができるのだろうか。」「継続的な指導が可能なのだろうか。」などである。しかし,企画・制作に関わらせるにあたり,しっかりとした指導および運営方針を持ち,情報モラルの学校教育全体を見通した活動を行うことで解決できるものと考えた。具体的には,ホームページ作成を生徒指導,特別活動などをふくめた統合的な取り扱いとするカリキュラムとして再編成し実践するのである。 このことにより, ・子どもたちが集団の一員としての自覚を持ち,相手を思いやり自分を大切にするなどモラルを持ちながら主体的に活動すること ・家庭,地域との関わりを大切にしながら活動すること ・ある期間だけの取り組みだけでなく,日常的に活動することにな  るので,これまで以上に「情報活用の実践力」「情報社会の創造に参画しようとする態度」を高めていくことができるのではないだろうか。 るので,これまで以上に「情報活用の実践力」「情報社会の創造に参画しようとする態度」を高めていくことができるのではないだろうか。 |
時配 |
情報教育計画 |
特別活動計画 |
生徒指導 との関わり |
|||||||||
1 |
実態調査 ・情報モラルへの意識 ・各種ソフトでの表現力 等 |
|||||||||||
2 |
○以前に行った情報モラルでの学習を振り返る。 ・教材用の校内Webページで 掲示板やアンケート,懸賞ページへ個人情報を入力することの問題点を確認する。 ・誹謗中傷することの問題点。 ・人のものを勝手にコピーしてしまうことの問題点。 |
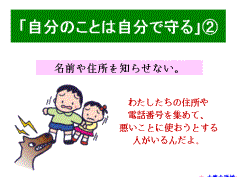 図ー2 情報モラル教材 |
・自分のことは自分で守る。 インターネット上にも陰の部分があることを知り自分を守る手段を知る。 ・相手を思いやる。 現実社会で許されないことはインタ ーネット上でも 同様であることを理解する。 |
|||||||||
3 |
子どもホームページをつくろう | |||||||||||
 図ー3 学級での話し合い |
学級活動(事前話し合い) ○学校生活や学校をよくしていくためにどんなホームページにすればよいだろう。 ・事前話し合いからテーマを絞り込む。 (学級) 1学校の一員として学校や地域のよさをつたえたい。 2地域の人に学校の様子を知ってもらいたい。 3自分たちへの意見も伺いたい。 ・コンテンツとしたいテーマを整理し,まとめる。 |
|||||||||||
4 5 |
個人情報の保護2 (1は5年生前半時に学習) ○個人情報とは何だったろう。 ・振り返り。 ○個人情報がもれるとどんな問題があるのだろう。 ・ページを作成,発信する際に個人情報が掲載された場合について考える。 ・校内Webページを閲覧し,その問題箇所をグループで探し指摘する。 ○ホームページを作るときに気をつけることをまとめよう。 ・学校のホームページが公的なものであることを自覚しまとめる。 ・実際にページを作るときに守らなくてはならないことについて,学校のホームページ運用規定を照らし合わせながら考えさせる。 ・以下の表ー3の事項を確認する。 ○誹謗中傷をしない |
 図ー4 学級活動 |
・相手を思いやる。 相手の権利を守ることはその人を大切にすること,思いやりの心を持つことと同じことを知る。 ・自分のことは自分で守る。 ・被害に遭った場合,おかしいなと思った場合は,すぐに家族や先生,警察に相談することが大切であることを理解する。 |
|||||||||
・学校ホームページを制作する際の個人情報の取り扱い |
||||||||||||
氏名 |
掲載しない(必要な場合は,許可を得る) |
|||||||||||
住所,電話番号, |
掲載しない |
|||||||||||
メールアドレス,年齢など |
掲載しない |
|||||||||||
個人写真 |
許可を得る |
|||||||||||
集合写真 |
個人が特定できないもの |
|||||||||||
家族情報,個人生活 |
掲載しない |
|||||||||||
| ※人の悪口やいやな気持ちになることは掲載しない。 |
||||||||||||
| 表ー3 個人情報の取り扱い | ||||||||||||
6 |
学習したことをもとに子どもホームページのコンテンツテーマを見直し,実際に作成するときの注意点も確認しよう。 | |||||||||||
| 学級活動(話し合い) 学校のホームページが公的なものであることを自覚し以下の点について学ぶ。 ○自分たちの考えたコンテンツテーマは適切であるかを話し合う。 ○個人情報の取り扱いを確認する。 |
||||||||||||
| 代表委員会とは,4年生以上の学級代表児童によって組織される学校生活に関する諸問題について話し合い,学校生活を向上させていく委員会のこと。 |
代表委員会での討議 ○学級から出された案を検討する。 ・各学年から,アドバイスを得る。 ・情報モラルに照らし合わせて。 |
 図ー5代表委員会 |
||||||||||
7 |
学級活動(代表委員会案の修正) ・代表委員会案を学級におろす。 ・6年生から受けたアドバイスもとにテーマを修正,決定する。 |
|||||||||||
8 |
修正案提出 ・修正案を学校ホームページ作成委員会へ提出。 テーマ決定 ・最終決定(校長) |
|||||||||||
※決定されたテーマ(今後の話し合いで可変) |
|||||||||||
| 地域とのコミュニケーションづくり | 総合的な学習の時間での学 習のまとめ テーマと 結びつく |
||||||||||
日記 コーナー |
学校の 様子 テーマ可変 |
こども ニュース |
先生紹介 |
みんなの声 テーマ可変 |
地域の 人たちへ テーマ可変 |
||||||
学 級 |
ホームページ作成委員会 |
学 級 |
|||||||||
班ごとに 更新 |
自分たちから見た学校の様子を広く知っていただく。 |
学校全体に関わるような内容を伝える |
定期的にテーマを決め,4年生以上を対象に声をあつめる |
まちのよさ 不思議だなと思ったことを調べたり,取材し 伝える。 |
|||||||
| 個人情報や著作権についての学習をしているものの、子どもたちによる学校ホームページのテーマを決定するための話し合い活動および事前指導をおこなったときには、実際のテーマと学習したことを具体的に結びつけて考えるのが難しい子どもたちもいた。そこで,サンプルWebページなどを使ったり,すでにある学校のホームページを閲覧し学習したことを関連づけるたりしながら学習を進めるようにした。個人情報の取り扱いについては,判断が難しいところもあるので,学校ホームページ運用規定の存在を知らせ,内容を確認させていった。そのため,子どもたちにの中に個人情報の取り扱いについて,具体的な判断基準が生まれてきた。 また著作権については、次の学習過程においてさらに掘り下げて学習をすることにした。 |
|
 学級で作成する内容と計画委員会(子どもホームページ作成委員会)で作成する内容を明確にした。 (表ー4) まず学級全体で、「日記」と「学校の様子」を制作更新していくことにした。 |
|
情報教育計画 |
特別活動計画 |
生徒指導 との関わり |
||||
1 |
日記や学校の様子をどのようにつたえていけばよいだろう。 | |||||
| 事前指導 ○取材の時に気をつけることは何だろう。 (総合的な学習の時間で指導済み) ○内容は先生に見ていただこう。 ○個人情報公開の許諾ルートを確認しよう。 ルートを確認する。 先生→ 本人→ 先生 |
|
|||||
2 |
 図ー7 取材する子ども |
学級活動(話し合い) ○どんな内容にするか話し合おう。 ・行事,学習場面,友だちとの生活を日記調に。 ○だれに一番読んでもらいたいのか ・子ども,おじいちゃんやおばあちゃんにも読んでいただけるように。 ・字の大きさやふりがなに気をつける。 ○他に気をつけることはないだろうか。 ○更新をどのように行うか。 ・日記はほぼ毎日,班ごとに交代して更新。 ・学校の様子は グループごとに取材加工。 ・日記の内容は,その日の帰りの会で学級全員に伝える。 ・学校の様子は仕上がり次第,学級全員で相互確認する。 |
発信相手のことを考え相手の立場に立った表現にするとよいことに気づく。 |
|||
3 ~ |
情報収集,加工 ○学校でのできごと観察しよう。 ・受け手も楽しくなるような観点で観察,情報収集を行う ○思いを伝える方法を考えよう。 ・見たもの感じたものを自分なりに表現できるように。 ・グループでの内容決定をおこなう。 ・表現するものが情報モラルに照らし合わせてどうか判断する。 |
元気よくあいさつをすることができる。 マナーを守ることができる。 相手を思いやる。 相手の権利を守ることはその人を大切にすることを理解する。 |
||||
| 友だちが書いた絵(作品)を日記に紹介してもよいだろうか。 | ||||||
| ○著作権を思い出そう ・出版物にかかれているものをそのままコピーしたりしてはいけなかった。 ・でも私的使用なら一部の場合を除きコピーは許される。 ○友だちの作品はどうだろう。 ・絵,作文や感想文などは,ほとんどのものが著作物である。 ・インターネットで発信するということは,私的使用とは言えない。 ・作品をつくった人の承諾が必 要である。 |
||||||
| ○日記のページをまとめよう ・ホームページ作成ソフトを使ってまとめる ○できあがったものは学校ホームページの一部であるので,必ず,先生に確認をしてもらう。 |
学級活動(帰りの会) ○友だちのページについてアドバイスをしよう。 評価点(帰りの会にて報告) ・情報モラルについて ・表現のわかりやすさ ○改善すべきところはきちんと修正しよう。 |
相手のよさを認めることができる。 |
||||
 図ー8 代表委員会 |
代表委員会での途中報告 ○学級でつくった日記のページを評価する。 ・6年生を交えて,アドバイスを得る。 ・情報モラルに照らし合わせて。 |
|||||
6 |
○学校の様子のページをまとめよう ○みんなが作ったページを閲覧し,よいところやなおした方がよいところを確認しよう。 ・一人一人のページをグループで相互閲覧し次の観点にそって評価する。 |
相手のよさを認めることができる。 |
||||
・最終更新(担当教員) |
||||||
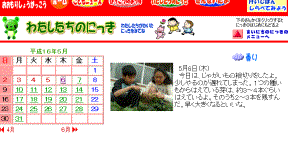 「日記」にはその日のできごとや思いなどの他,天気も入れている。はじめのうちは,更新は毎日で無くてもよいと子どもたちに伝えたが,子どもたちは,更新を大変楽しみにしているようで,意欲的に毎日おこなっている。そのため,更新にかかる時間は休み時間に行える程度ですむようになるなど,リンクをはったりフレームにページを読み込んだりする技能は,簡単に身につき,高まっていった。継続的に更新することで,機器などの取り扱いやソフト上の操作はもちろん,
様々な情記報収集や整理などの能力向上,また情報モラル の高まり及び定着をねらっている。 「日記」にはその日のできごとや思いなどの他,天気も入れている。はじめのうちは,更新は毎日で無くてもよいと子どもたちに伝えたが,子どもたちは,更新を大変楽しみにしているようで,意欲的に毎日おこなっている。そのため,更新にかかる時間は休み時間に行える程度ですむようになるなど,リンクをはったりフレームにページを読み込んだりする技能は,簡単に身につき,高まっていった。継続的に更新することで,機器などの取り扱いやソフト上の操作はもちろん,
様々な情記報収集や整理などの能力向上,また情報モラル の高まり及び定着をねらっている。
図ー9 毎日更新されているこどもの日 |
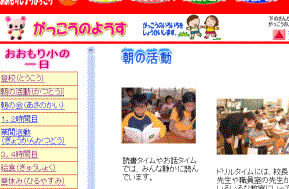 「学校の様子」には,学校の一日や校舎の様子など子どもたちの案で様々なコンテンツが生まれてくるようにしている。コンテンツの内容がきまると,グループごとに協力しあいながら活動していく。 「学校の様子」には,学校の一日や校舎の様子など子どもたちの案で様々なコンテンツが生まれてくるようにしている。コンテンツの内容がきまると,グループごとに協力しあいながら活動していく。 発信前に友だち同士の相互評価を行わせよい点を認め合ったり,改善点などを修正したりする。ただし「日記」「学校の様子」を含め,こどもページは最終的に教師のホームページ作成委員会(校長を含む)が確認した上で,発信することになっている。
図ー10 学校の様子にある大森小の一日のページ |
 「日記」を進める上では,身近にパソコンがあると更新しやすいと考えた。しかし,本校はパソコン室と子どもたちが普段利用する教室とは少し距離があり,またパソコン室にしか子どもたち用のパソコンがない。そこで5,6年教室の廊下に自前のパソコンと寄贈されたノートパソコンあせて4台配備した。さらにLAN敷設をおこなった。それぞれのパソコンからサーバー機にファイルをロードしたりアップしたりできるため,休み時間など空いている時間に手軽に更新できるようになった。 図ー11 教室廊下に設置されたパソコンで活動 |
| ○ 長期的・継続的なカリキュラム |
| これらのカリキュラムの特徴は,期間限定ではなく,長期的・継続的に情報教育における指導を行えるところである。子どもたちに学校ホームページの企画,運営,制作等を行わせるのは,日常生活や社会の動きに目を向け,適切に取材をしたり自分たちの考えを話し合い整理する機会をふやすためである。新しいコンテンツを企画する上では、情報の収集整理活用を見通した動きが必要となり、「相手を思いやる」豊かな心も大切にしなくてはならない。この活動は、これらの力を養うため、継続的にしかも子どもの実態に合わせ段階的に指導を行うことができる。 |
| 次に述べるのは,1学期半ばに話し合いにより新しく加えられたコンテンツである。 |

・「みんなで考えたこと」
これは、情報モラルの基本である「相手を思いやる気持ち」を高めるために、学級での話し合いを行い、そして適切に発信するという一連の活動を報告したものである。ホームページのコンテンツづくりを核として活動したことにより、話し合ったことを実践に結びつけるという流れがスムーズに行えた。
上記以外にも、新聞クイズやBLOGなど子どものアイディアを生かして生まれたコンテンツを更新している。 |
| 計画委員会(子どもホームページ作成委員会)の動き |
| 子どもホームページ作成委員会は「こどもニュース」「先生紹介」「みんなの声」などを更新している。 これらテーマも可変するものとする。(「みんなの声」は地域からのアンケートによって実現したものである。 |
 行事予定(図ー12)には今後の取材予定が書かれており,見通しを持って活動することができるようになっている。 図ー12 子ども用取材作成スケジュール |
 学校と地域との行事へ取材する子どもたち(図ー13)。こういった場での行動の仕方,取材の仕方は普段の学習だけでは,不十分に終わることが多く,また場の設定も難しい。幸いこのような取材を快く受けてくれるので助かっている。ほどよい緊張の中,マナーを守って活動している。 学校と地域との行事へ取材する子どもたち(図ー13)。こういった場での行動の仕方,取材の仕方は普段の学習だけでは,不十分に終わることが多く,また場の設定も難しい。幸いこのような取材を快く受けてくれるので助かっている。ほどよい緊張の中,マナーを守って活動している。図ー13 行事での取材活動 |
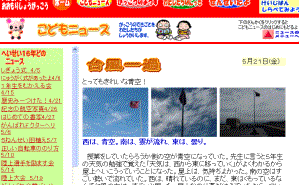 こどもニュース(図ー14)はこどもホームページ作成委員会が,学校の出来事を中心に 取材し,週に1~2回更新している。写真を効果的に挿入したり,友だちにインタビューする内容を事前に決め,友だちの声としてニュースの中に紹介したりしている。 図ー14 こどもニュース |
校内掲示板には,高学年の子どもたちが教室廊下におかれたPCから自由に書き込むことができるようにしている。これは,個人情報の取り扱いを始め,ネットの向こうにいる人たちにも思いやりの心を持って行動することを実践する場である。何でも自由に書き込みというわけではなく,期間をきめて,ホーム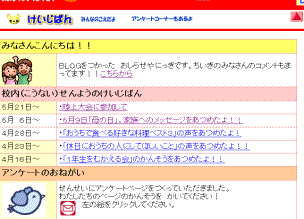 ページ委員会の子どもたちが話題を提供する形をとっている。PCのそばにあるお知らせ板に「今回の話題は○○○です。」といった掲示をする。たとえば「母の日,家族へのメッセージを書こう」などである。それを見た子どもたちは,話題にあった書き込みを行うのである。書き込みの内容を見ると,そこには家族への暖かい言葉がよせられていた。不適当な書き込みは全くなかった(他の話題でも同様)。この掲示板のアイディアは地域からのもので,それを実際に形にしたものである。保護者への反応もよく,「ハンドルネームを使っているが,どれが自分の子どもかすぐわかる。」とうれしそうに話していたのが印象的であった。 ページ委員会の子どもたちが話題を提供する形をとっている。PCのそばにあるお知らせ板に「今回の話題は○○○です。」といった掲示をする。たとえば「母の日,家族へのメッセージを書こう」などである。それを見た子どもたちは,話題にあった書き込みを行うのである。書き込みの内容を見ると,そこには家族への暖かい言葉がよせられていた。不適当な書き込みは全くなかった(他の話題でも同様)。この掲示板のアイディアは地域からのもので,それを実際に形にしたものである。保護者への反応もよく,「ハンドルネームを使っているが,どれが自分の子どもかすぐわかる。」とうれしそうに話していたのが印象的であった。図ー15 校内掲示板,BLOG,アンケート |
| ホームページ上のコンテンツを変更または,新規にテーマを決める場合,学級での話し合い ~代表委員会~ホームページ作成委員会~学級という基本的な流れをとる。その都度情報モラルに照らし合わせながら話し合いを進めることができるようにする。 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月の感想(表ー7)は,子どもたちの感想の抜粋である。情報を発信することのすばらしさ,外部からの評価をうけることの喜びを感じている子が多かった。実際に情報を発信することで情報発信の責任の重さに気づいた子どもも多くいた。 |
|
5月感想から ①いろいろな取材をしたり,資料を探したり大変だったけれど,みんなに見てもらえるようにがんばってまとめました。 ②一つのホームページを作るのにたくさんの時間と努力が必要だとわかりました。これからも自分たちの手でしっかり続けていきたいです。 ③近所の人にいつも見ているよと言われたときはとてもうれしかったです。みんなに喜んでもらえるように工夫したいです。 ④自分のつくったページが学校ホームページにのるなんてすごいと思いました。それだけに作ったページに責任を持たないとだめだと思いました。 |