

[写真1]来校したSedwick先生による表情の指導
[写真2]ホーリークロス校の「職場のいじめ」
Sedwick先生による日本からの指導


[写真3]メールで送った精神的ないじめの
ストップモーション
[写真4]メールで送った肉体的ないじめの
ストップモーション
|
5.実践事例 |
|
(1)社会問題「いじめ」をテーマとする共同学習 |
|
平成12年度の後期に日英両国に共通する社会問題の中から「いじめ」の問題を取り上げ、互いにドラマで演じ合うことにより両国の文化を学ぶ取り組みを行った。その中で、本校は「学校におけるいじめ」、ホーリークロス校は「職場におけるいじめ」をテーマにした。ホーリークロス校からドラマ担当のSedwick先生を本校に招き、オフラインでの国際ティームティーチングの授業[写真1]も行えた。授業は数人のグループ毎にいじめの場面を設定し、演じた直後に、聴衆が演じた者一人ひとりに、役柄についてのプロフィールの設定や心境を質問し、質問される者はその役になりきって答えるという「ホットシーティング」で他者理解、自己認識の視点を発見していく方法で進められた。テレビ会議による共同授業ではSedwick先生がテレビを通してホーリークロス校の生徒を指導するという興味深い場面[写真2]も観られた。それぞれのグループは、事前に自分たちの発表するドラマのストップモーションの写真[写真3,4]にキャプションをつけてホーリークロス校の生徒にメールで送りコミュニケーションの効率化を図った。 |
|
|
|
|
[写真1]来校したSedwick先生による表情の指導 |
[写真2]ホーリークロス校の「職場のいじめ」 |
|
|
|
|
[写真3]メールで送った精神的ないじめの |
[写真4]メールで送った肉体的ないじめの |
|
また、評価についてSedwick先生は良いところを褒める。改善点は、範を示して学び取らせる方法を一貫して行っていた。本校の生徒は演じた後Sedwick先生から次の課題をもらえると思っていたが、Sedwick先生は良かったところを褒めるだけの評価しか返さなかった。本校の生徒はこのことを不思議に思い、ホーリークロス校の生徒に、Sedwick先生はホーリークロス校でも同じ評価の仕方をするのかを聞いた。答えは「The Same. 同じ」であった。このやりとりを聞いていたホーリークロス校のLawrence先生から以下のような「だめなところを直させる指導より、良いところを徹底的にほめて自信をもたせる指導を大切にしている」という以下のようなメールが来た。 |
|
Regarding the drama performances,it will
surprise you that we NEVER makeSevere comments on the work of
students.At the end we say what is GOOD,ONLY. |
|
(2)社会問題「ジェンダー」をテーマとする創作ドラマ |
|
平成13年度の前期から、新3年生はホーリークロス校と共同で一つのドラマを上演したいという意見が高まった。本校の生徒がホーリークロス校のLawrence先生に直接メールで相談して「ジェンダー」をテーマとした創作ドラマ「CHANGE」の台本[表4]を本校が作り、ホーリークロス校と共同で上演することになった。本校の生徒たちで話し合った結果、大道具や、衣装などスタッフの手間を省くため場面設定を学校での出来事とし、衣装も制服ですませるように考えた。このドラマはビデオ作品と舞台上演の両方で発表し、その表現の違いを学ぼうという意図もあった。生徒たちは「シナリオ作成チーム」「シナリオ英訳チーム」「小道具作成チーム」「ビデオ撮影チーム」「音声録音チーム」「ビデオ編集チーム」「演出チーム」「キャストチーム」を考えたが人数が少ないため生徒は複数のチームを担当することになった。あらすじは、男女がぶつかった瞬間に互いが入れ替わり、男子は女子のグループ、女子は男子のグループを体験し、社会的性差を理解しようとする気持ちなるまで元に戻れないというストーリーである。 |
[表4]本校の生徒が作成した創作ドラマ「CHANGE」のシナリオ
|
日本語のシナリオ |
翻訳したシナリオ |
|
シ-ン2 <廊下を二人で歩いている--チャイムがなる> まな 「あつやく~ん、バイバ~イ」 ようこ 「今日も、かっこいいわぁ」 まりあ 「きゃ-っ!手ふってぇ~
<男ゆい、苦笑しながら手を振る> 男ゆい 「はあ。(ためいき)」 <男ゆい、振り返ってボソっと言う> 男ゆい 「こんな人のどこがいいのよ」 <聞こえていた女あつや、男ゆいをにらむ> 女あつや「悪かったな」 男ゆい 「ハハっ・・・(苦笑)でも、それよりさ--」 女あつや「ん?」 男ゆい 「これから、どうするよ-」 女あつや「え・・・・ん・・・あっ!!」 <女あつや・男ゆい、顔を見合わせる> 男ゆい・女あつや「オカルト研究部!! |
Scene 2 <The two are running through the hallway when the bell rings> Connie: Bye Jake! Joyce: You're lookin' hot Jake ! Tiffany: Wave to us Jake! <Lea puts a smile on her face, and waves> <The three disappear laughing> Lea: (sighs) <Lea turns her head and mutters> Lea: What's so good about this guy? <Jake heard this, and stares at her> Jake: Well, sorry if I'm not your dream guy Lea. Lea: uh, well any ways... Jake: What? Lea: What are we going to do now? Jake: um, well......hey I know! <Jake and Lea look at each other> Jake and Lea: The occult club! |
|
全14シーンで上演時間が15分ほどのシナリオと英訳シナリオが完成した。オリジナルはマッキントッシュのクラリスワークスで作ったため、英訳シナリオをテキストファイルに変換し、念のためFDFファイルに変換したものと一緒に、ホーリークロス校にメールで送った。ホーリークロス校の生徒から御礼のメールが来たが、登場人物の人間関係が複雑で、人間関係がよく分からないというメッセージが付いてきた。そこで、生徒たちは登場人物の人間関係を図で表し[図4]、画像ファイルに加工してホーリークロス校に送った。 |
[図1] ホーリークロス校に送った、登場人物の人間関係を表す「リレーション」
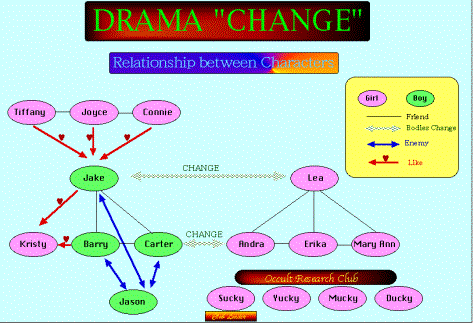 |
|
打ち合わせのためのテレビ会議では、このリレーションを基に、いろいろな質問が取り交わされた。「ハートマーク」の大きさも個数も同じだが、Likeの強さは皆同じなのかという質問に、相手の気持ちを想像し、情報を作り伝えることの深さを学んだ。このリレーションは翻訳チームが中心になって作成したが、「Jake」が好きな人という括りで考え、3人の個性まで考えてなかったのである。 |
|
|
|
|
[写真5]外部マイクをモップの柄に |
[写真6]テレビ会議での評価会 |
|
このような取り組みを経て平成13年度の秋に、共同上演を予定していたのだが、9月の中頃に、ホーリークロス校のカリキュラムおよび教員人事の都合で、Sedwick先生が低学年のドラマの授業の担当に変更になり、共同上演ができなくなったという連絡が来た。 |
|
また、Lawrence先生から来たお詫びのメールには「国際交流学習の妨げになるのは時差ではなく、学校のシステムである。」というメッセージも添えられていた。生徒を集めてその旨を伝え、国際交流ではよくあることなので、次に何をするべきかを考えようと呼びかけた。生徒は一度は落胆したが、共同上演ができないならば、自分たちが作ったビデオ作品と、舞台上演した様子をビデオで撮影したテープの両方をパルシステムに変換してホーリークロスに送り、観ることのできる人だけにでも観てもらい、テレビ会議で評価をもらった。[写真6] |
|
(3)キャラクター作りを題材とした共同授業 |
|
「かさ地蔵」と”The Elves and the Shoemaker” |
|
平成14年6月29日に”London Grid For Learning”のオープニングイベントが行われ、国際共同授業の事例として、本校とホーリークロス校とのテレビ会議によるドラマの授業[写真7]が行われた。事前にホーリークロス校から呼びかけがあった際、テーマを「それぞれの国で昔から小さい子供に話して聞かせる物語」と提案してきた。本校のメンバーはミーティングを開き、要望も含めて以下のことを決め、ホーリークロス校に伝えた。 (1)自分たちは今「キャラクター作りの学習」に取り組んでいる。この学習を共同授業の中で行いたい。「白雪姫」 (2)本校は、「かさ地蔵」で6体のお地蔵さんそれぞれに、異なった個性を持たせる。 (3)「かさ地蔵」のストーリーを事前に理解しておいてもらうために「かさ地蔵」を英語で紹介してあるウエッブ (4)「かさ地蔵」イメージの固定化を避けるため、URLの紹介だけではなく、英語で書かれた「かさ地蔵」の絵本 (5)互いに台本を事前に送る。 この連絡に対してホーリークロス校は以下のことを伝えてきた。 (1)ホーリークロス校は” The Elves and the Shoemaker”で、妖精たちにそれぞれ異なるキャラクターを持たせる。 (2)ホーリークロス校は台本を作らず、全て即興で行う。 (3)さまざまな種類の靴のイラストを描いて送って欲しい。 (4)ドラマを演じあった後、テレビ会議上で評価会を行いたい。 このようにして、メールや国際エクスプレスメールを駆使してプロジェクト型の国際共同授業が進められた。 |
|
|
|
|
|
[写真7]ホーリークロス校クロス校が |
[写真8]本校から送った靴の絵 |
|
|
|
(1)(本校の質問)キャラクターの違いを表現する時に注意していることはなにか。 |
|
(2)(ホーリークロス校の質問)シナリオを作るときに注意したことは何か。 |
|
(3)(本校の質問)気持ちを表すときに一番効果的な表現は何だと思うか。 |
|
(4)(本校の質問)妖精たちの思いの違いを具体的にどのように表現したのか。 |
|
(5)(ホーリークロス校の質問)靴の絵はコンピュータで描いたのか。 |
|
この実践事例は、共同授業の場が初めてホーリークロス校の外に出て、公的なイベント会場において21世紀型の新しい授業としてイギリスで紹介された事例である。ホーリークロス校から参加依頼があってから本番まで、日数があまり無かったが、生徒は、インターネットで打ち合わせを行い、絵本などの資料は国際エクスプレスメール(EMS)で郵送した。また、いつもならば、ホーリークロス校がテレビ会議の最中にマイクロホンを移動させる時にノイズが聞こえてくるのだが、今回はイベント会場に放送専門の技術者がいて、機材等の調整まで全てを担当してくれたので、ノイズがなかったのが印象的であった。 |