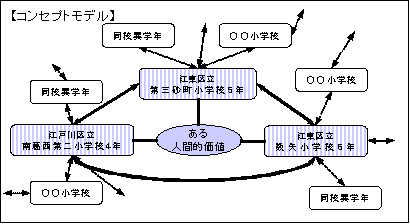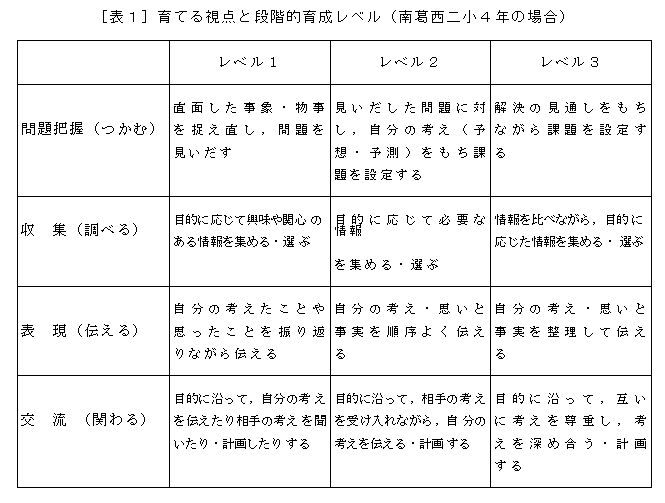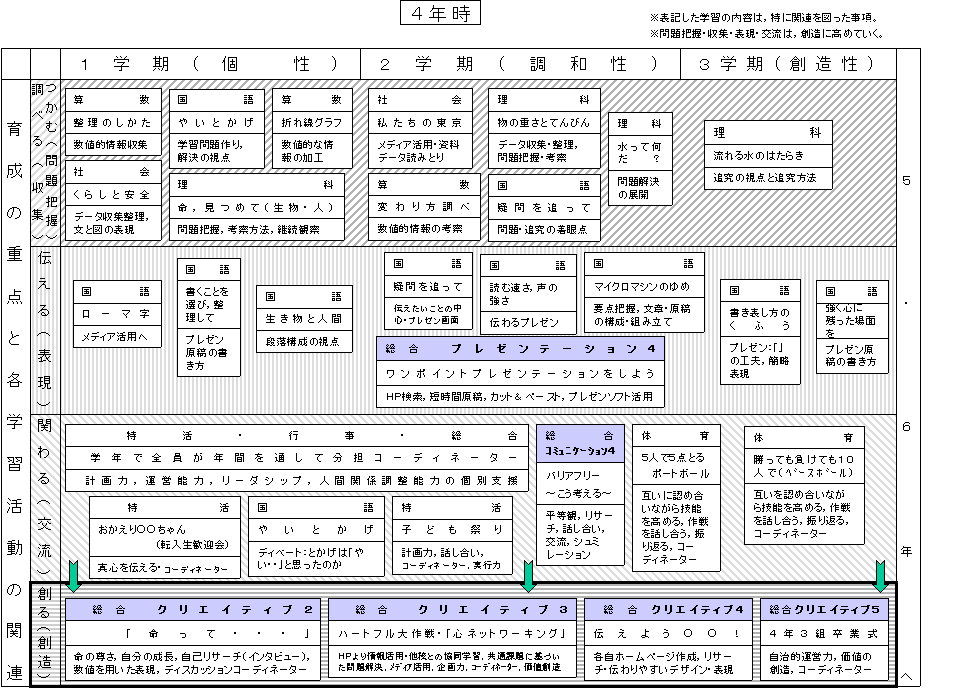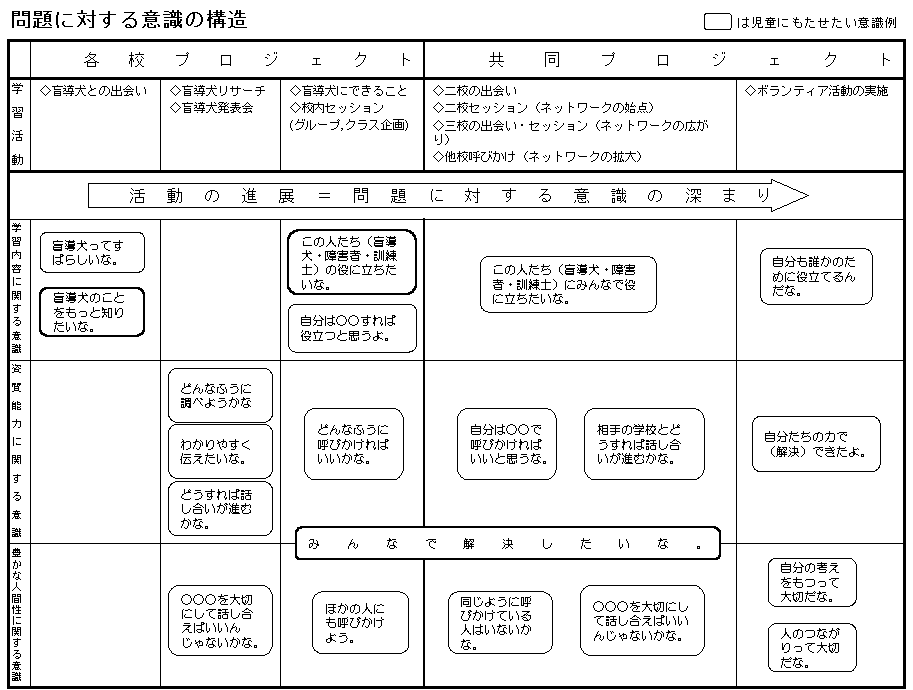| Ⅱ.本実践の基本的な考え方 情報活用の実践力や問題解決能力,豊かな人間性を着実に養うために,「実践のコンセプト」と,授業設計の具体的な手だてとして,「実践の柱立て」を明確にして取り組んだ。 1.実践のコンセプト 本実践は,下記の三つの視点をコンセプトにし,3校の共同プロジェクト学習として構成した。
これはICTの時代と言われる昨今,メディアを活用しながら様々な人々と協調して活動することにより,これからの時代に必要な「問題解決能力」や「豊かな人間性」を養うことをねらいとしている。 (1)ネットワーキングの捉え方 今回使う「ネットワーク」という言葉は,単なるコンピュータのつながりではなく,「人のつながり」という意味で捉えている。また,「ネットワーキング」とは,子どもたち自ら「人のつながりを創り出していく活動(個性+調和性+創造性)」を意味している。 (2)心・ネットワーキングの活動概要 今回は「盲導犬の活動と実状」をテーマに,自分たちにできるボランティアを周囲の人と協調して計画・実行する活動を学習内容とした。 ・それぞれの学校で企画する(個性)。 ・次に同じような発想をしている学校に呼びかけ,共同企画を話し合う(調和性)。 ・決定した企画にもとづき活動する。またネットワークを更に広げていく(創造性)。 (3)ヒューマンネットワーキング 無機質な機械の体験ではなく,ある人間的価値を軸にして人のつながりを深め広げていくためにネットワークを利用していこうと考えた。 子どもたちは今回の活動を実現させるためには仲間を増やしていく必要に迫られる。 その活動を通して,「盲導犬や障害者に喜んでもらおう」「そのためには人のつながりが大事だな」「自分も誰かのために役立てるんだ」というような心情や態度(人間的価値=豊かな人間性)を養いたいと考えている。 (4)オープンネットワーキング 今回は,特定の学校間のみで収束を迎える,クローズされたネットワークではなく,人間的価値が共感的に広がっていくネットワーク(オープンネットワーク)を想定した。 これは,様々な人々と協調し,様々な今日的課題を解決していくことが,これからの時代を生きる子どもたちにとって必要な資質能力であると考えたためである。 尚,実際の学習場面では,3校の異学年(4・5・6年)の共同プロジェクトとし,その他の学校にはメールやWebページなどで協力を呼びかけるようにした。 (5)メディアネットワーキング インターネットの活用を中心としたコミュニケーションネットワークとしてメディアを活用するようにした。 今回の活動は校内のみでも行うことができる。しかし,これからの高度情報社会では,様々な人々とメディアを通して交流を図ることが求められる。そこで一つのモデルとして,学校間でインターネットを活用して共同プロジェクトに取り組み,児童自らネットワーキングできる力を育成したいと考えている。 (6)一人の発想から世界へ未来へ 今回の学習では,いきなり学校間で企画立案をするのではなく,前段階として個々の発想を大切にしながら同様の活動をクラス内でも行ってきた。いわば一人の発想の延長線上の活動と捉えたのである。 子どもたちには,自分の発想や思いをもち,様々な人々と共感的に調和し,時代や社会を変革できる人間に育ってほしいと願っている。 2.実践の柱立て 情報活用の実践力や問題解決能力,豊かな人間性を育成するため,実践を組み立てる際の具体的な手立てとして,3校共通の「実践の柱立て」を明確にして取り組んだ。 具体的には,それらの能力を育成するために長期・短期における「学習計画の工夫」を行い,児童が一連の活動に取り組む中で育てたい力を着実に高められるようにした。 (1)長期しかけ1(情報活用の実践力や問題解決能力の段階的育成) 情報活用の実践力や問題解決能力を着実に養うために,育てる視点を明確にし,「総合的な学習の時間」の諸活動を中心に段階的に学習できるようにした。[表1] |