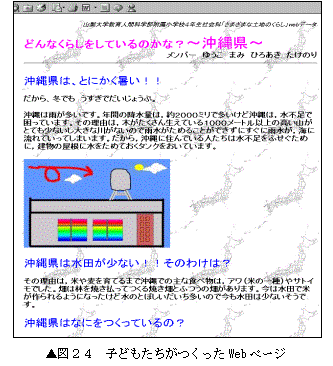(1)無線LANを使った学習活動
昨年度実施した無線LANを活用した6年生の社会科の実践について具体的に報告する。
○小単元名 「天下統一のゆくえ」
○小単元について
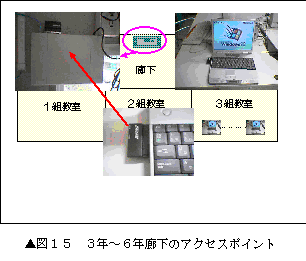
本小単元では,戦国時代から武士による天下統一に至る過程を,郷土の名将「武田信玄」,そして信長,秀吉ら3人の人物の働きを中心に取り上げ,追究させていくことにした。
また,この学習には,図書を教室に複数持ち込むのと同時に,情報機器を積極的に導入することで,情報検索での調査追究活動を豊富化する方途を子どもたちに与え,それらの情報を加工し取得する過程に置いて,自分たちの考えや感想を高めようとするねらいを持っている。さらに学習の成果をワープロソフトや手書きによる「新聞づくり」を行うことによって,互いに学習した内容を還元し合うように本小単元を設定した。
○情報機器の取り扱いについて
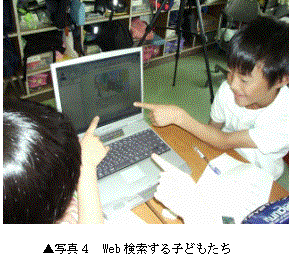
今回は,無線LAN機器としては次のものを使用している。
・メルコ製アクセスポイント AIRCONNECT・WLA-L11 1台
・メルコ製無線LANカード AIRCONNECT・WLS-L11 11枚
また教室には,以下の機器を設置した。
・教材提示用に書画台 1台
・提示用TVモニタ33インチ 1台
・TVゲーム機器及びゲームソフト 1セット
・児童用ノート型コンピュータ無線LANカード8台
・教師用ノート型コンピュータ無線LANカード1台
・予備用ノート型コンピュータ無線LANカード2台
・デジタルカメラ(教師用) 1台
教科書等の挿し絵を拡大表示するため,書画台と33インチTVモニタを使用する。また,TVゲーム機器の表示用としてもモニタを使用する。児童用ノート型コンピュータは,グループ(生活班)に1台ずつ渡し,電子メールに書かれたURLをコピー&ペーストして,Webページを検索させ,フォーマットされたワープロファイルを使って,新聞づくりを行い,校内のデータサーバに保存するようにしている。これらのノート型コンピュータは廊下に設置された無線LAN基地局(アクセスポイント)を介して校内LAN及びインターネット接続できるようになっている。<図15>
○実際の授業の様子
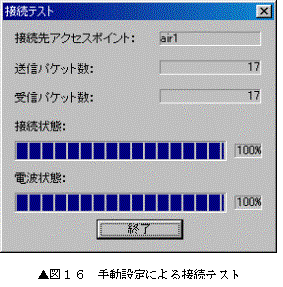
<1>日時:平成12年6月23日(金) 1〜2校時(8:55〜10:20)
<2>場所:山梨大学教育人間科学部附属小学校 6年1組教室(本館3F)
<3>題材:長篠の戦いから戦国時代について考えよう
<4>展開:
a TVゲーム「プレステーション2:決戦」
b 長篠の戦い(どの武将同士の戦いか)
c 武田信玄,織田信長,豊臣秀吉の中から一人をグループで選択。
d その人物について調べ学習
・学習プリントとメールで指示。
・図書資料やWeb検索
e ワープロソフト(Word)で新聞作り
g NTサーバにファイル保存。
○無線LAN使用端末との接続状況
接続テストは,手動設定により実施しなければならないが,子どもたちの手でも実施することはできた。(不便さは感じられる。)<図16>
接続状況及び電波状況は各ノート型コンピュータともどちらも95%から97%であり,有線でLAN接続しているときと大差なく使用できた。送信パケット数及び受信パケット数も15から17あった。アクセスポイント1台に対して14台の無線接続が可能とあるが,今回常時接続は9台で行っている。
11台中3台が起動不良。→無線LAN用のドライバの問題?(強制終了をかけ起動しなおし,セーフモードでの起動後,再起動をかけると直る。)
電子メールソフトの設定ファイルがNTサーバに保存されている。→初めて設定ファイルを読みに行ったので,アイコンがこのソフト用になっておらず,子供たちが戸惑う場面が見られた。(電子メールをこのクラスのメーリングリストに配信し,調べようとする人物について掲載されたWebページのURLを記しておいた。このURLをコピー&ペーストすることでWeb検索をスムーズにしている。また添付書類として学習プリントが送られた。)
また,添付書類として送られた書類を利用して作成した文章(歴史新聞)は,8グループのうち6グループはNTサーバ(ファイルサーバ)に保存された が,2グループはノート型コンピュータのHDDに保存してしまった。ノート型コンピュータは,バッテリー駆動させたが,約50分の使用時間は問題なく駆動しつづけた。
○実践を終えて
今回の実践では,教室内でノート型コンピュータを利用して学習活動を行うメリットとして以下の点が確認できた。
(イ)複数台のノート型コンピュータが無線LANによりインターネット接続が可能である。
(ロ)動きのある学習形態において配線が伴わない使用が子どもたちの学習活動を保障できる。
(ハ)ファイルサーバへの保存により継続学習ができる。
(2)ホームページを活用した学習活動
昨年度実施した天気情報のホームページを活用した5年生の理科の実践について,具体的に報告する。
○単元名 「天気の変化(2)」
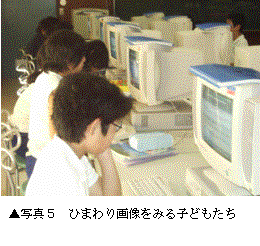
○単元について
子どもは,「天気の変化(1)」で春の頃の天気の規則性(「雲は西から東に動く」等)について学んできている。またその規則性をもとに気象衛星「ひまわり」の雲画像やアメダスの雨量データなどの気象情報を活用して天気を予想することも経験してきて,秋の頃の天気の変化を調べたりして,その規いる。
本単元では,気象情報をもとに台風がきたときの雲の動きや天気の変化を調べたり則性に気づいたり天気の変化を予想したりする活動を行う。また,情報の科学性について考えるために「100%正確な天気予測」についての討論をする。
○単元目標
コンピュータ・ネットワークなどの情報を活用し,天気の変化を調べることができるようにする。
○成果と課題
理科の領域区分でいうC領域「地球と宇宙」,中でも気象教材や天体教材は直接観察や実験が非常に困難である。これらの学習において,情報機器,特にコンピュータを使って雲や天体の動きを視覚的に捉えられるようにすることは,大変有効である。
今回活用したWebページ「TBS weather guide」では台風アニメーションを4つみることができた。4つの台風の動きを比較してみることができ,共通性を理解しやすかった。
単元の終わりに,「100%正確な天気予測」についての討論をしたことにより,科学万能主義になりがちな児童には「科学的な情報も絶対とはいえない」という考えにふれ,情報の科学性について考える機会となった。5月に気象の学習をしてから,行事前などにコンピュータを活用し天気を調べる児童が目立つようになってきたが,今回の学習を通して,コンピュータの積極的な活用をしつつ「夕焼け」にも興味を持つ児童が目立ったことは大変意義があった。
(3)Web/E-mail/テレビ会議を用いた学習活動
昨年度本校6学年で実施した,パソコンタイム」で培ったリテラシーを「総合的な学習の時間」で活かす様子について,具体的に報告する。主な活動として
a 自己紹介ホームページを作成し,それを通じて他校と交流をする活動。
b 学習活動の深まりの中で,他校とテレビ会議などで意見交換をする活動。
c 学習の経過をWeb化し,さらにメーリングリストを活用して学習を深める活動。
以下に,それぞれの活動の概要を記す。
○実践の概要
a 自己紹介ホームページを作成し,それを通じて他校と交流をする活動について。
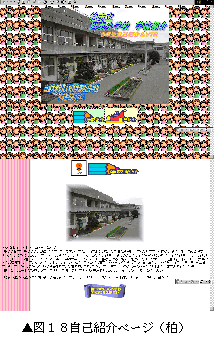
| 
| 総合学習で「社会問題に目を向ける」ことを計画したときに,せまい範囲(校内・学級)での交流よりも,より広域的に多方面の子どもたちと意見を交流させたいと考えた。その際,今までパソコンタイム・総合学習の時間などに培ってきたコンピュータ・リテラシーも活用できることをめざしたいと考えた。 そこで,学習テーマを決めて追究活動を行った後取り組んだことは,自分たちの自己紹介ページの作成である。〈図17〉他校の友だちに自分たちのことを知ってもらい,「○○について一緒に学習をしていきましょう。」というお誘いの内容のページである。千葉県柏東小学校6年生とその内容を交換した。〈図18〉 |
以下に紹介するのは,交流相手の旭東小学校の子どもたちからのE-mailである。
(1)こんにちは,○○○○です。
メールを送らせていただきます。私は□□さんのグループに興味を持ちました。実は私も社会問題を中心とした活動をしています。もしよかったら私の資料集めに協力して下さい。待っています。お返事まっています。では,さようなら・・・・
(2)こんにちは。はじめまして,『○○○○』です。
□さん,△さん,●さん,■くんこれからも,よろしくお願いします。私たちも,環境のことについて調べています。私たちのグループは,《□□と,○○と,わたしで,やっています。私たちは,ごみ0運動のほかに,リサイクル運動をやっています。これからもよろしくお願いします。お返事待っています!! (^o^)
(3)○○さんへ □□です。
あれから,地域の名物を調べてみました。まず,北海道です。ここは,じゃがいも,牛乳などの乳製品,かに,たまねぎなどです。青森は,りんごです。岩手は,わんこそば,米,りんご,牛乳などの乳製品,さけ,わかめなどです。宮城は,米ぐらいだと思います。秋田は,りんご,きりたんぽ,米,めろん,はたはた,ふきなどです。山形は,さくらんぼ,りんご,米,かき,ぶどう,さんさい,米沢牛,西洋なし,すいかなどです。時間がないので,また,メール送りマース。 返事,待ってまーす!
このように,お互いの学校で興味をもった内容について,それぞれが意見や調査結果を交流した。
b 学習活動の深まりの中で,他校とテレビ会議などで意見交換をする活動について。

5年生の時に,学年全体で宮城教育大学附属小学校の5年生とテレビ会議での交流活動をした。子どもたちは初めての経験ということ,大人数であったこと,お互いの活動の接点が見つけにくかったことなどの原因で,決して十分な成果が上がったとは言えなかった。
そこで今年度は,宮城教育大学附属小学校の6年生と,小人数のしかも共通項が見出しやすいと考えられる課題に取り組んでいるグループ同士による,テレビ会議を行った。〈写真6〉
課題が似通っており,しかも地域での差もまた多いに学習の参考となる追究課題であった。渋滞緩和問題のように,本校で問題となっていることが宮城では一つの打開策が見つかっていたり,宮城で問題となっていた路面電車復活のことが山梨の子どもたちの参考となったりするなど,活発な意見交流が行われ双方にとって有意義な交流となり,今年度の追究活動を深める意味でも大いに役立った。〈図19〉
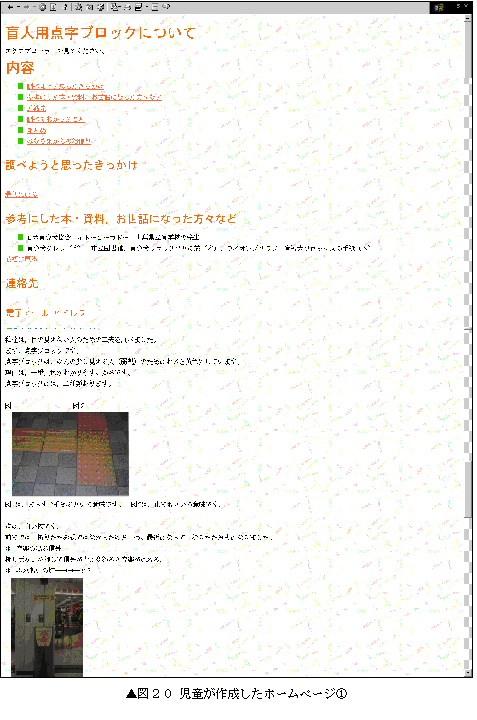 c 学習の経過をWebにし,さらにメーリングリストを活用して学習を深める活動について。
c 学習の経過をWebにし,さらにメーリングリストを活用して学習を深める活動について。
子どもたちが学習を通して学んだことを目に見える形で表すことに取り組ませ,さらにそれを周りの人に見てもらい,意見交流の場を設定した。具体的には,本校児童が学習したことをWeb化し〈図20〉,それに対する意見を求めその意見を元にさらに交流し,しかもその交流の様子をそのWeb上に紹介していくこととした。
以下に,交流したメールの一部を紹介する。
(1)少年法の事について
私達は少年犯罪のホームページを見て,私達も,日ごろのストレスが原因で,犯罪をする人がいるのではないのかなあと思います。なぜなら,私達もストレスがたまってムシャクシャすると,物や人にあたったりするから,犯罪をした人達も同じなんじゃないかなと思いました。私たちは,今の少年法は,おかしいと思います。少年が守られていて大人と同じ罪にならないのなら,少年だけの,大人より少し軽い罰を,作ればいいんじゃないかと思います。 (少年法を見直してほしいと思います。)
(2)ホームページの感想
「ストレスだけで犯罪をおかしたわけじゃない」というまとめが書いてありましたが,私たちも賛成です。ストレスの他にも,環境の変化や,人とのかかわりでのトラブルみたいなもので,おかしたような気がしました。少年犯罪が,このごろ続発しているけど,絶対やめたほうがいいのはあたりまえだけど,やってしまうのはきっと何かあったんだと思うから,カウンセラーみたいなもので,気持ちを聞いてあげればいいのかなとも思いました。もし,すごいストレスとかで犯罪をおかしたとしたらちょっとその人が
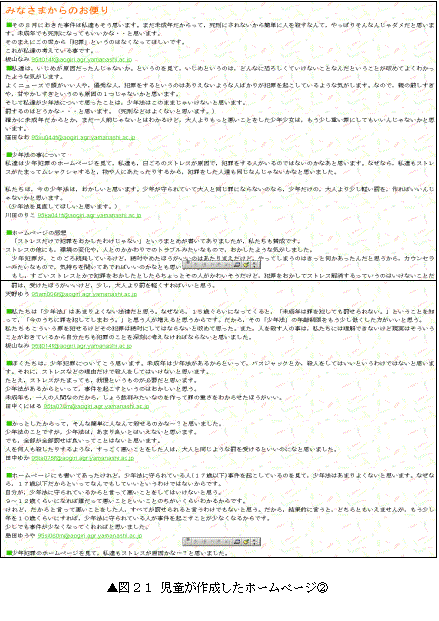 かわいそうだけど,犯罪をおかしてストレス解消するっていうのはいけないことだと思う。
かわいそうだけど,犯罪をおかしてストレス解消するっていうのはいけないことだと思う。少年法についての意見です。子どもでも,犯罪をおかしたのに,罰せられないのはおかしいと思う。『子どもは,守られている。』でも,守られているなら,守られているなりに,きちんとした,罰みたいなものを,きちんと受けなければならないと思う。
悪いことをしたのは,やったひとも分かっているはずだから,罰したほうがいいと思う。子どもは子どもでも,悪いことは,悪いことだから,怒るときは怒らなければいけないと思う。(罰を受けさせるべきだと思う。) 罰は,受けたほうがいいけど,少し,大人より罰を軽くすればいいと思う。
交流をしている過程で,話題となっていた「少年法」の改正が国会で決まったことなどもあり,議論は大いに高まった。(図21)
○実践を終えて
子どもたちが,パソコンタイムなどを通して培ってきたコンピュータ・リテラシーを,これらのように教科・総合学習などで多用に活用し,しかも,そのことで普段接することができない地域の子どもたちとともに学ぶことができることは,その活動を仕組んできたものにとっても大変喜ばしいことである。交流を通して、考えを発信し、議論し、修正していく過程を体験しながら、自分の考えを高めたり、他人を認める態度が高まったと言える。子どもたちが十分に活用できるツールとしてのコンピュータの有用性を改めて感じる実践となった。
(4)サークル型交流を実現した学習活動
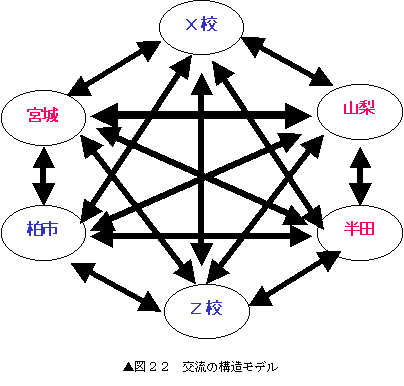
本校では,交流活動は一つの学校が活動のすべての中核となるのではなく,互いに必要な学習活動を保障し合いながら進めて交流することが望ましいと考えている。<図22>。
ここでは,具体的事例として,4年生社会科で実践した,「どんなくらしをしているのかな?」について報告する。まず,はじめに,各地の様子を調べる学習環境として,無線LAN対応ノート型コンピュータの活用を計画した。
資料活用能力,調査能力を伸ばすには,即コンピュータではなく,地図や図書資料,過去の調査ファイルを大切に学習をすすめることが必要であると考える。
そこで,日頃の学習材が身近に揃っている教室(学級・図書室)へ,無線LAN対応ノート型コンピュータを持ち込み,既存資料で解決できない各地の様子について,Webで検索したり,メールでの問い合わせをしたりして調査活動を行った。
無線LAN対応ノート型コンピュータの導入メリットは,配線が不要であり,場所にとらわれることなくコンピュータ利用活動ができるところにある<写真7>。(しかし,バッテリー駆動の時間が短いことがまだ課題となっている。)
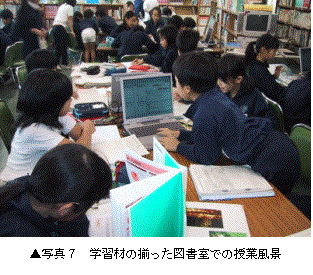
| 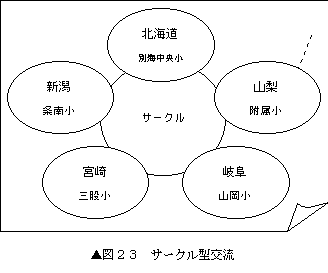
|
時間をおいたり,場所を移したりすることなく,各地の様子について問題解決している子どもたちの姿がみられるようになってきた。
つぎに,収集データをより正確なものにしたり,未解決問題について問い合わせをしたりするために,積極的に他校と交流活動を行った。
本校では,1対多(複数校)の関係で進む1校集中型の学習から,複数の交流校がお互いに同等な立場で,それぞれと情報交換できるサークル型交流学習への転換をはかった<図23>。メリットとしては,交流校のすべてが,様々な情報を入手する事が可能となり,積極的な学習が期待できることがあげられる。
交流の場面では,自分たちの思いを相手に伝えていくために,電子メールと連動させながら,デジカメ画像を交換しながら,その地の様子を学習したり,TCP/IP上でのNet meetingを活用して,交流学習をスタートさせたりした。
それぞれが得た情報や思いについては,Webページとして保存した(図24・・この図をクリックすると子どもたちのつくったWebページへリンク)。電子メールなどを使ってコミュニケーションすることで,情報や思いを共有し,社会的事象の見方・考え方を深めることができた。