本校では,特設時間として『パソコンタイム』(総合的な学習)を時間割に位置づけている。<図5>
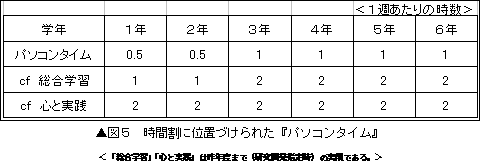 |
コンピュータの基本的な操作方法に慣れさせると共に,情報の取り扱いに関するモラルやマナーの育成をはかり,コンピュータを情報の獲得や思考の表現のためのコミュニケーションツール及び表現ツールとして,教科学習や総合学習の問題解決に利用できるようにしている。
パソコンタイムの位置づけは,以下の内容を実現させるためである。
(1)自己表現を行う時間の確保
毎週1時間(1・2年生においては,隔週1時間),コンピュータを使って自分の好きな絵を描いたりメールを送ったりすることを通して,ソフトの使い方を覚えると同時に,自分の中にある思いを表現させることができるようになった。「使い方」を覚えたあとは,「それぞれの思い」を表出させ綴っていく時間となっている。
(2)学習に生かす表現方法の獲得
調べ学習において「情報を獲得するための方略」・「集めた情報を加工する(グラフ作成・作表など)技能」・「まとめた資料を提示する方法」などを取り立てて学ぶことが可能となっている。
(3)コンピュータ・リテラシーの計画的指導
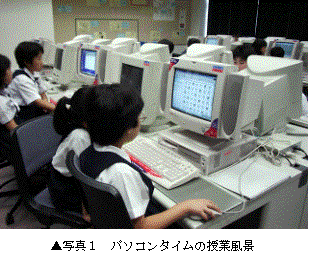 コンピュータそのものの操作方法から,ソフトの使用方法などを計画的に習得することが可能となってきた。情報獲得手段の一つとして他の媒体と同様にインターネットを活用することを可能としている。また,同じ学年内でコンピュータ利用がある程度一様になってきているために,クラス替えがあってもコンピュータ・リテラシーの差が少ないという効果もある。
コンピュータそのものの操作方法から,ソフトの使用方法などを計画的に習得することが可能となってきた。情報獲得手段の一つとして他の媒体と同様にインターネットを活用することを可能としている。また,同じ学年内でコンピュータ利用がある程度一様になってきているために,クラス替えがあってもコンピュータ・リテラシーの差が少ないという効果もある。
(4)教科学習・総合学習の学習内容を発展させる時間の確保
「パソコンタイム」の指導項目<図6>では,4年生までに一通りの機器操作方法やソフト扱いについてふれることにしている。5・6年生においては,4年生までに身につけたものを生かして,教科学習や総合学習の学習内容を発展させることができるように,活動内容を敢えて特定せず,むしろ総合学習等の実際場面で生ずる問題に対応させながらモラルの育成を中核にしている。これにより,例えば総合学習で「環境問題」について考えている子どもが環境問題を扱ったホームページの検索を行ったり,友達に協力を呼びかけるために電子メールを送ったりする姿も見られるようになってきている。同時に電子メールの送受信で起きるトラブルについて学級で考える場面がありモラルの育成をはかっている。
 |