![]()
問題解決の道具として、インターネットを活用したり、レシピ作りにコンピュータを活用し、データーベース化した例(仮説1の検証)
1 コンピュータの活用方法 (使用ソフトウェア キューブワード)
(1) インターネットなどで得たいろんなサラダ料理の調理のポイントや、食材などの情報を活用したり、データーベース化した去年の5年生が作っ
たレシピを検索し、自分たちが作ってみたいレシピに取り入れる工夫をした。
(2) 調理実習で作った野菜サラダをデジタルカメラで撮影し、材料・調理法・シェフのおすすめの一言をレシピにまとめた。
(3) 学習のまとめ時に、各班のオリジナル野菜サラダのレシピを活用し、それぞれの工夫している点などについて話し合う。そして、家族のため
に作って みたいレシピを印刷して持ち帰ることにより、家庭での実践化が図られた。
(4) 家庭での実践をデジタルカメラに記録させ、朝の会で、教室のテレビを利用し紹介をすることにより、次時以降の実践化へのきっかけとなっ
た。
2 研究のねらい
家庭科では、子どもが自分のよさや可能性を発揮しながら、豊かに自己実現ができるよう学習を創造することをねらっている。そのためには、児童一人一人が自分の家庭生活の中から課題を見つけ、家庭生活に対する自分なりの思いや願いを持ち、その実現に向けて試行錯誤しながら、人や環境と豊かに関わり、課題解決したり、創造したりするような児童主体の学習活動を展開することが大切であるととらえ、野菜サラダ作りの学習を通して研究を進めた。
3 研究の視点
(1) 創意を生かした指導計画の作成と実践
(2) 児童が自分のよさを発揮できる実践的・体験的な学習の工夫
(3) よりよい生活をめざして実践する児童を育てる指導の工夫
4 題材目標
(1) 野菜の栄養の特徴を知り、体に大切な働きをしていることがわかる。
(2) 野菜サラダ作りに必要な用具や計量器の安全で、衛生的な取り扱いができる。
(3) 調理の手順と方法を理解し、協力して野菜サラダ作りをする。
(4) 進んで野菜サラダを作ろうとし、学習したことを家庭生活の中で生かすことができる。
5 題材観と児童の実態
(1) 本題材は、初めての調理実習によせる期待と意欲を学習の取り組みに生かして、調理の基礎的な知識と技能を習得するとともに、作る喜びを味わい、家庭生活の中で生かすことをねらいとしている。さらに、新鮮な野菜や旬の野菜の選び方、無駄のない購入の仕方などを考えることにより、消費者として必要な態度を育てることができる。また、調理後の油汚れに対する洗剤の使用の仕方やゴミの分類を考えることにより、環境に配慮する態度も身に付けることができる。それは今後家庭生活に生きる力となると考えた。
(2) 5年生になって新しく始まった教科学習とあって、どの児童も大変意欲的である。特に調理に対する興味や期待は大きく、家庭で食事の準備や片づけの手伝いを選び、実践している児童も多い。しかし、野菜を洗う、切るなどの調理の経験をもたない児童や、野菜が嫌いな児童も多くみられる。また、 菓子類などの買い物の経験はあるが、野菜類を買ったことのある児童は少ない。ゴミの分類については、清掃指導や給食指導を通して行っているので、意識は高くなっている。だが、洗剤の使い方に関する知識はほとんどない。
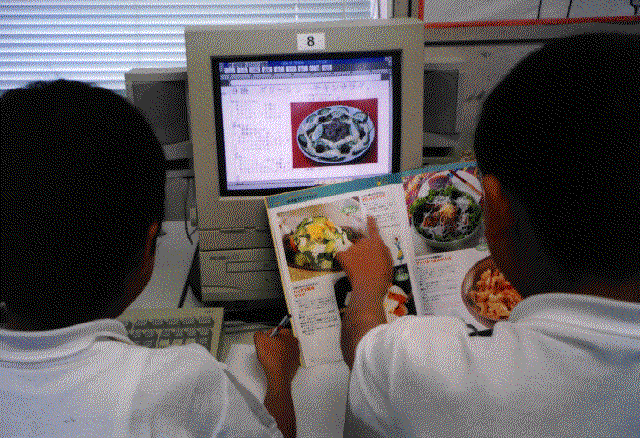
レシピの例
12班トマトサラダ シェフのおすすめ 「手作りマヨネーズがおすすめ!」
材料 (3人分)
トマト 3こ ジャガイモ 2こ 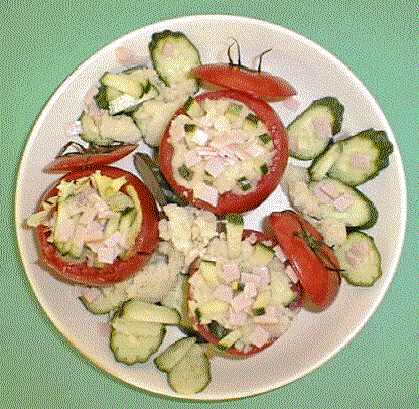
ハム 2枚 レタス 2枚
きゅうり 1/2本 プチトマト 1こ
調理法
1トマトをくりぬく
2手作りマヨネーズを作る
(1)ボールに卵の黄み1個、塩小さじ1/3 こしょう少々を入れて、あわだて器で1
分ぐらい混ぜる
(2)す(大さじ1)を半分だけ入れて1分ぐらい混ぜる
(3)油を1てきずつ入れる
(4)油が大さじ1ぐらい入ったら油を糸のようにちらしながら、まぜる
(5)残りの酢を少しずついれてよくまぜる。
3ジャガイモをレンジでむしてつぶす
4野菜を切る 5トマトの中にジャガイモと野菜を入れる 6もりつける
感想
美味しかった( )とてもおいしかった( )いい感じ!( )
6 児童の意識と学習の流れ(全12時間)
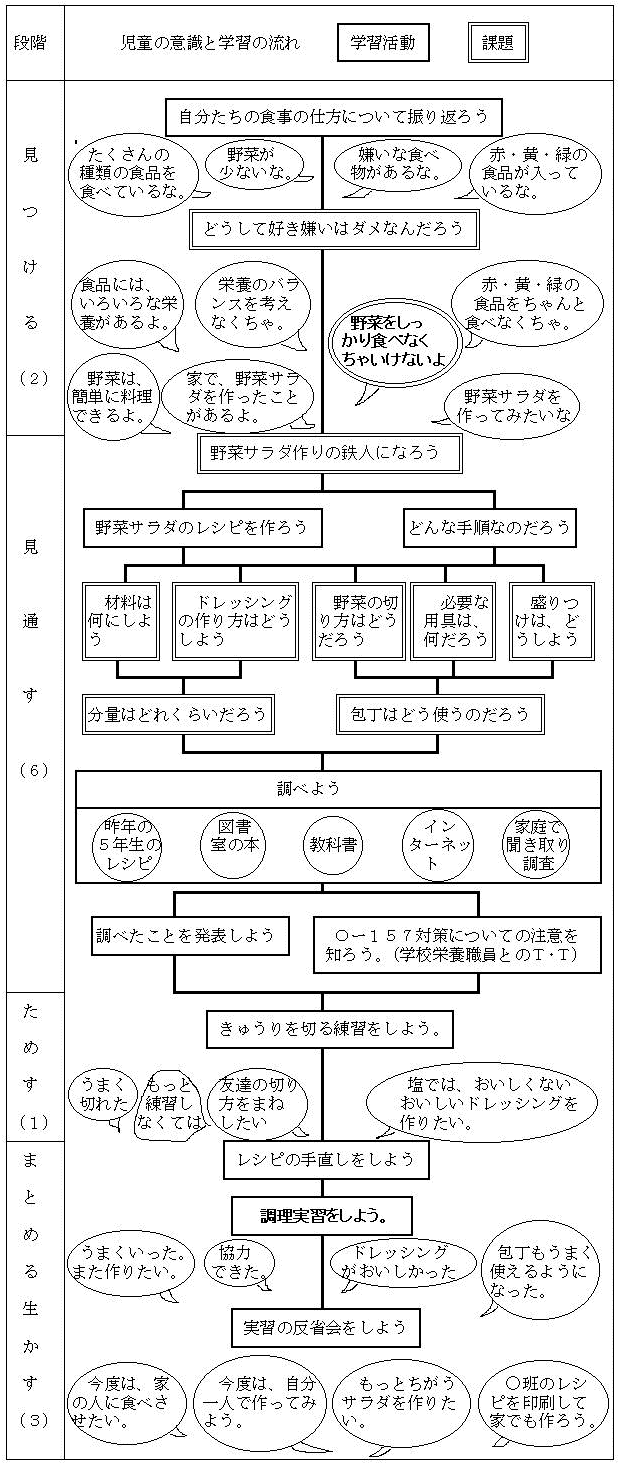
7 考察と今後の課題
(1) 初めての調理実習であるこの単元では、基礎基本の技能をしっかり身に付けさせることが大切なことであると考え、十分時間をとって用具設
備の使い方について指導した。そのことにより、調理実習の楽しさだけでなく、安全・衛生面の必要性にも気づくことができた。
(2) 自分たちの課題を本や聞き取り調査やインターネットを使って調べ、解決したことで、野菜サラダ作りの鉄人になろうとする意欲・関心を
めることできた。
(3) 自分が作ろうとするサラダのイメージに合うように、切り方や盛りつけ方などさまざまに工夫するなかで、単に包丁の使い方や切り方に
ず、自分のよさを発揮しようとする子どもの姿が感じ取らた。
(4) 学習を通して、消費者としての望ましい態度、環境に配慮する態度や人との関わりを大切にする気持ちを育てることができ、よりよい生活
くろうとする実践意欲が高まった。
(5) 家庭生活に密着した課題を工夫し、児童一人一人の問題意識をより高める手だてや導入の方法をさらに研究したい。
(6) 家庭科学習を通して身に付いた力が、家庭生活の中で生きて働く力となるよう家庭との連携のあり方を工夫していきたい。
![]()