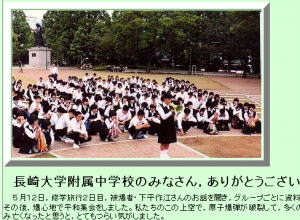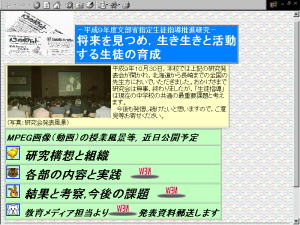長崎平和学習プロジェクト(平和学習) (平成10年度,対象第3学年)
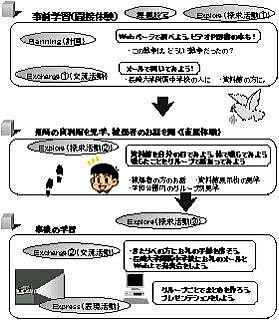
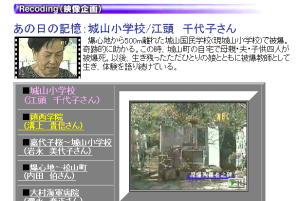
|
<長崎大学附属中学校・選択社会履修の生徒→高梁中学校3年生徒> ○修学旅行生の長崎でのマナーについてどう思いますか。(高梁中生徒) >本当にぴんからきりまでです。せっかく来たんだから,調べたことを生かして長崎の人に話しか けたりしながら,いろいろな思い出を作って欲しいです。一つだけお願いしたいのは,原爆資料 館や平和公園は特別な場所だということを考えて欲しいということです。(長崎大学附属中生徒) ○原爆のことをどう思いますか。何か学校で取り組んでいる活動がありますか。(高梁中生徒) >原爆は二度とあってはいけないと頭で分かってもだめだと思います。感情も含めてだめだという 気持ちをもつため,つらくても被爆者の苦しみに目を向け耳を傾けて欲しい。学校では,夏休み に被爆者への聞き取りやレポートづくりなどに取り組んでいます。(長崎大附属中生徒) ○原爆のことを「頭じゃなく,感情で」というのがとても分かる気がしました。被害の大きさがど んなに分かっても,被爆者からお話を聞いて,苦しみが分からなければ意味がないと思いました ○「決してつらくてもその(原爆の)事実から目をそむけないで」「特別な場」。特に平和公園で のマナーはきちんとする。長崎の人たちに二度とくるなといわれないよう。(高梁中生徒) |